最近のコメント一覧
最近投稿された読者の皆様からのコメントをご紹介!たくさんのコメント、お待ちしています。
-
EH
2026-01-08
当たりますように
-
たけちゃんマン
2026-01-08
昨年暮れに退院しました虫垂炎でしたが色々有り三週間入院してしまいました医者や看護師さんには感謝しかありません^_どんな場面でも笑顔でありがとうと言う言葉に勇気を貰い自分を見つめる事が出来改めて病気を理解して退院に至りました、自分の置かれた立場を理解する事は大変でしたが介護をしてくれた人達がいたからの退院だと思います自宅静養では病気の苦しさを思い出し健康的に毎日を過ごしております。
-
ピカピカ
2026-01-08
最近目がどんどん見えなくなってきている父おやの介護がそろそろ必要なのかなと思っています 体も脳も健康で目だけなので必要ないといいますが勉強するのに登録してみようかな
-
梅干しババア
2026-01-07
柴田理恵さんの暗くて悲しい老後に涙が出てきました。
-
倉島孝幸
2026-01-07
興味がある
-
アレックス宝力
2026-01-05
親子ほどかなり年下で生意気かもとおもいましたが記事を読みコメント致しました。子供の頃から知っている女優さんです。本郷さん相手の怪談映画は最近、ネットで観ました。あれがデビュー当時ですか? 不気味な初代女性ストーカー話ですが、美しく、はかなく、せつないヒロイン姿が良かったです。ご病気されてからの数々の取り組み、よく吟味されていると思います。私も黒酢をよく摂りますが、黒いものを積極的に摂るようにしています。黒ごま、黒豆、シイタケなどです。それに野菜は、これからのまだまだ長い私の半生のよき味方になってくれると思っています。これからも赤座さんの元気さと更なるご活躍を期待していますよ!
-
高橋 修
2026-01-05
介護をする方にならないように頑張り売ます!
-
石井一見
2026-01-05
素敵なプレゼント有難うございます、当選を目指して応募させて応募させて頂きます
-
菊次郎
2026-01-04
介護職をしています。心身共に疲弊する仕事です。職員が少なくやる事が多く、人の命を預かる仕事で気が抜けない、利用者から暴力暴言を吐かれる事もある、力仕事で体を壊してしまう可能性あり、休みが少なく、その割に給料が安く、ベテラン職員の当たりが強く、ブラック。 今までこの人数で出来ていたのだからと、これからもこの人数でやっていっては、何も改善されない。 職員を一人増やせば、余裕も出来て、事故も減らせる、職員間で争うことも無くなると思う。
-
ぴー
2026-01-04
かなり古い記事に今更コメントするのは気が引けますが(笑)、ランキング見て目が点になりましたよ。 ロングセラー、シェア率大きくどこでも手に入る「マルちゃん焼きそば」が入ってない?どういう事?? 代わりに見たこと無い物が多数を占めており頭の中は?の嵐。コレって案件記事なのかな。 個人的に焼きそばの太麺が嫌いなので日清さんは敬遠してます。太麺好きなら焼きうどんで良いのでは(笑)。
-
みけ
2026-01-04
ぐれちゃん、女の子だったんですね 体が大きくて甘えっこなので男の子だと思ってました。 次は隊長ちゃんですね。 6ヵ月までに避妊手術をしておくと乳癌の発生率が下がりますよ。
-
nurarin
2026-01-01
nurarinです。あけましておめでとうございます。お正月はお休みをいただいて、もうすぐお別れのぐれと隊長とまったり過ごしています。年越しは2匹とも私の脚の上に乗っかったままでした。今年が皆様にとっていい年になりますように。 (=^x^=)(=^x^=) (=^ェ^=)
-
りんりん
2026-01-01
新年あけましておめでとうございます。 お兄様にあれだけ振り回され続けたツガエ様がお兄様のことを嬉しそうに綴られていて読んでいる私もホッとします。良い年になりますように! で、些細そうでいてなんとも大変なことって多いですよね、スプレー缶の扱い。ク〇CRC、消臭剤、静電防止、防虫剤、そしてガスボンベ!結構、扱いが違いました。ク〇CRCは夫が実家の田畑の隅でボロ布に浸み込ませていたようです。防虫剤は私、庭の隅でスーパーの袋をかぶせて穴をあけ液を袋に溜めやはり新聞か何かに浸み込ませました。ガスボンベ、私も実家の片付けで見つけました。サビてボロボロなので穴をあけて…ン⁇もしかして爆発的な❓これは生産者に聞くしかないと思いTELしましたら会社がありました。無くなっているかもいるかもと心配しましたが良かった!無いならないで他社のガスコンロ会社に聞けば同じように教えてくれると思います。市(区)役所のゴミ担当者さんに聞いてもいいかもしれません。
-
山田貴実子
2025-12-31
興味深い。
-
山田博文
2025-12-31
介護気になる!
最新記事














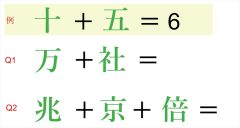






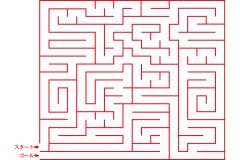


シリーズ







