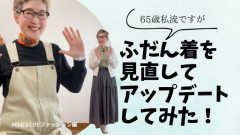《楽しみにしていたデザートを勝手に食べられていたら許せる?》哲学研究者が解説する“共同的分かち合い”とそれを拒む“貸し借りの呪い”
パートナー、友人、同僚──。継続する人間関係において最初こそ相手にやさしくできても、それをずっとつづけられる人は多くない。自分の意思ではないのに、その意思に反して相手をコントロールしてしまうことにこそ、悩ましく厄介な点がある。それは日々ともに暮らす人間関係に起こりやすい。
ものごとをありのままとらえようと試みる「現象学」を専門とする哲学研究者、東洋大学文学部哲学科教授・稲垣諭さんが、やさしいの内実にせまり、読んだらやさしいがつづく確率が高まるという『やさしいがつづかない』(サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。
教えてくれた人
哲学研究者、東洋大学文学部哲学科教授・稲垣諭さん
北海道生まれ。青山学院大学法学部卒業。東洋大学大学院文学研究科哲学専攻博士後期課程修了(文学博士)。自治医科大学総合教育部門(哲学)教授を経て、現在、東洋大学文学部哲学科教授。専門は現象学、環境哲学、リハビリテーションの科学哲学。著書に『大丈夫、死ぬには及ばない 今、大学生に何が起きているのか』(学芸みらい社)、『絶滅へようこそ 「終わり」からはじめる哲学入門』(晶文社)、『「くぐり抜け」の哲学』(講談社)、翻訳書にドン・アイディ著『技術哲学入門:ポスト現象学とテクノサイエンス』(晶文社、増田隼人・沖原花音との共訳)など。
* * *
身近な関係を知る:共同的分かち合い
どうして家という居心地のよい空間に支配の力が入ってくるのか。
そもそも仲がよくなるということは、どのようなことなのでしょう。一概に答えることは難しいですが、ひとついえるのは「共同的分かち合い(communal sharing)」の関係が強くなるということです。
この「共同的分かち合い」関係とは、自分の利益や取り分などを考えずにすべてを共有し合う関係のことです。
典型的には、家族内で親が子にすべてを分け与えたり、家の中にあるものは誰が使っても大丈夫だったりする関係です。トイレットペーパーやシャンプーを誰が使おうが、冷蔵庫の中にあるものを誰が食べようが問題ないのが分かち合い関係です。
この分かち合い関係において人々は、一心同体の共同体として、同じ行動をし、同じものを食べ、身体的な距離の近さや接触を介して、きずなを強化し合います。
もちつもたれつの関係であると同時に、相互にフリーライドし合う関係でもあるので、基本的には家族や血縁、パートナー関係にだけ許されるものです。
友人同士や近所付き合いなどでも、これに近いことは起こります。でも、たとえば飲み会の食事代や、同僚のひとりにプレゼントを一緒に買って渡すときなどは、きっちりとワリカンにして公平・平等にするのが普通です。分かち合いにまではいたりません。
またたとえば、あなたが高級レストランで食事をした後、その店のオーナーに「おいしかったので、今度はぜひうちにも遊びにきてください。お礼にご馳走しますから」と伝えて、お金を払わず帰ったらどうなるか、考えてみてください(*1)。すぐに警察に通報されて逮捕されるのがオチです。そんなのは当たり前です。
しかし、この当たり前ということの中に隠されているものが実は重要になってきます。レストランの例では、オーナーとあなたの間には共同的分かち合い関係が存在せず、別の人間関係が設定されているということなのです。
ですから、もしあなたがそのレストランのオーナーとものすごく仲がよかったり、親族であったりする場合、先のことは十分に起こりえます。私もそのようにして知り合いのレストランが新規オープンするときにご馳走になったことがあります。そうしたさいには、貸し借りとかとは関係なく善意の分かち合いが成立するものです。
つまり「共同的分かち合い」という関係は、通常は極めて特殊な範囲、メンバー間だけでしか成立しません。そこには明文化されたルールも法律もありませんし、貸し借りの義務や規範が発生することもありません。
だからこそ、身近な人ではなく、見知らぬ人にも発揮される、貸し借りのないマイクロ・カインドネスはとても不思議で、奇跡的なことだったのです。本来、親密な人同士の共同的分かち合いの関係性の中でだけ、そうしたやさしさは発揮されると思われていたからです。
……いえ、共同的分かち合いに貸し借りの義務が発生することはないというのは、真実ではないかもしれません。
これはある知人女性から聞いた話ですが、彼女は中学生の頃に、母親から「あなたを育てるのにかかったお金、いつかその負担分、3000万円を返してね」と言われたことがあるといいます。それがあまりにも衝撃的で、今でも彼女の頭を悩ませ、苦しめているとのことでした。
フリーライドは許さないといわんばかりのこの親の発言は、子どもにとってはトラウマになるほどの呪いとなるはずです。
この事例はたしかに極端かもしれません。
しかしもしかすると現代社会では、共同的分かち合いが許されるはずのゾーンにさえ「貸し借り」というやさしいがつづかなくなる規範が入り込んでいる可能性があります。
ここでいう「貸し借り」とは、未来への約束です。もう少し強いいい方でいえば負債を負う/負わせることです。
「貸し借りはいずれ返す/返されるべきだ」という規範が現れると、共同的分かち合い関係は一挙に変化してしまいます。あるいは、その「貸し」や「借り」を利用して相手をコントロールしようとする欲望が動き始めるでしょう。
あなたが買ってきて、後で食べようと楽しみにしていたコンビニのデザートが、家族の誰かやパートナーに勝手に食べられてしまっていたとき、あなたはそれを許すことができますか?
これはとても些細な事例にすぎません。
しかし、そのような小さな事件の中にこそ、分かち合いを拒む貸し借りの呪いが入り込んでくるものです。もし許せないとすれば、デザートでさえ自分のコントロール下においておきたいということです。そこにあるのは、セルフコントロールできる領域をきっちり確保しておきたいあなたの欲望です。
やさしいがつづかないという悩みを正確に把握するには、あなたの日常生活における人間関係がどのようなものとして営まれているかを知ることが、とても重要です。
(*1)スティーブン・ピンカー『暴力の人類史 下』(幾島幸子、塩原通緒訳、青土社、2015)460頁以下