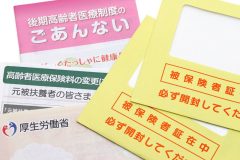介護施設の食費が6万円も安くなるのはどんな人?|知らないと損する介護保険の話
介護施設に支払う食費や居住費は、原則自己負担だが、実は所得が一定以下なら減額される制度がある。人によっては、1か月で6万円以上も安くなるという。どんな人が使える制度なのか、ファイナンシャルプランナーの大堀貴子さんに解説いただいた。
施設の食費や住居費は意外と高い!?
特別養護老人ホーム(特養)などの介護保険施設は、市区町村や社会福祉法人が運営する公的な施設であり、利用料が比較的安いのが特長だ。介護保険施設とは、大きく分けて以下の3つがある。
介護保険施設とは?
・特別養護老人ホーム(正式名称:介護老人福祉施設)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
→介護施設の種類・選び方【最適施設がわかるチャート付】費用・親の状態で施設を見つける
介護サービスの費用は、所得に応じた負担割合を元に負担が軽減されており、高額になった場合には、高額介護サービス費として自己負担上限額を超えた分が還付される。
→2020年8月から介護保険料の負担が8万円も増える! 値上げのからくりとは
さらに、生活保護受給者は、介護サービス費用は生活保護から支給されるため負担はない。
食費や居住費は実際いくらくらい?
施設の利用料には、介護費用とは別に、食費や居住費(滞在費)などがかかる。これら介護費以外の費用は、介護保険の対象外となり、全額自己負担となっている。
食費と住居費がどのぐらい大きな負担となるのか。以下は、標準的な食費・居住費の金額だ。
なお、実際には利用者と施設の契約で金額は決まる。ただ、利用金額は適正な金額であることが求められているため、大きくここから乖離することはない。
例えば、特養の従来型個室に入所した場合、1か月で居住費が5万40円、食費が4万1760円で合計9万円程度かかる。
月9万円とは、意外と負担が大きいと感じる人もいるだろう。そこで、介護保険施設に限って、食費・居住費を軽減する制度がある。以下で解説しよう。
食費や居住費の負担を軽減する制度とは?
大きな負担となる自己負担の食費と居住費だが、介護保険施設に入所、またはショートステイした場合には、食費と居住費を軽減する制度がある。「特定入所者介護サービス費」と呼ばれるもので、低所得の人向けのサービスとなっている。
特定入所者介護サービス費が使える人の条件は?
該当する施設の利用者で、かつ以下の用件を満たしている人が対象となる。
・生活保護受給者
・世帯全体が市民税非課税
・配偶者が市民税非課税
・本人・配偶者の金融資産(現金・預金・有価証券・金等の貴金属等)が 2000万円以下であること (配偶者がいない場合は1000万円以下であること)
繰り返しとなるが、市民税が世帯全員非課税で、金融資産は、配偶者がいない場合は1000万円以下、配偶者がいる場合は2000万円以下である必要がある。
この金融資産には、預貯金だけでなく、タンス預金などの現金、株式や投資信託等の有価証券、金・銀などの貴金属(積立含む)まで含まれる。ただし、住宅ローンなど債務がある場合にはこれらの資産から差し引くことができる。また、保険、自動車、腕時計、宝飾品などは含まれない。
実際どのぐらい負担が軽減されるのかを表したのが以下の表だ。
軽減制度で1か月で6万円以上も安くなる!
例えば、世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入が80万円以下の場合(年金以外に所得がないとする)、通常特養の従来型個室に入所した場合、1か月で居住費が5万40円、食費が4万1760円の合計9万1800円かかるところ、1か月の居住費が1万2600円、食費が1万1700円、合計2万4300円となり、6万円以上も安くなるというわけだ。
もし、低所得の方向けの軽減制度の要件に当てはまらなくても、社会福祉法人や市区町村が独自で行う軽減制度もある。これを「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度」という。
市区町村、または入所する社会福祉法人独自で自己負担となる食費・居住費の負担を軽減してくれるところもあるので、所得が該当しなくても、市区町村・入所予定の社会福祉法人に問い合わせをしてみることをおすすめする。
軽減制度には申請が必要
高額介護サービス費は対象となれば利用月の2か月後程度で、市区町村から支給申請書が送られてくるため、自分から申請する必要はない。
一方、今回の食費・居住費軽減制度では、自分から申請が必要となる。
低所得の方向けの軽減制度を受ける場合、申請にはマイナンバーが分かる書類、本人確認証が必要な他、金融資産が要件以下であることを証明する通帳など預金の残高がわかるものが必要だ。
認められると、市区町村から「介護保険負担限度額認定証」が交付され、利用者が負担限度額のみを支払えば良いことになる。
なお、申請からすぐに認定されるわけではないため、介護保険施設への入所・ショートステイの利用予定があれば利用する前月までに申請しておくとよいだろう。
文/大堀貴子さん
ファイナンシャルプランナー おおほりFP事務所代表。夫の海外赴任を機に大手証券会社を退職し、タイで2児を出産。帰国後3人目を出産し、現在ファイナンシャルプランナーとして活動。子育てや暮らし、介護などお金の悩みをテーマに多くのメディアで執筆している。