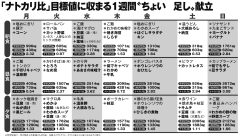《意外と知らない》「健康保険」の制度や給付内容をイチから解説 医療費が高額のときに戻ってくる「高額療養費制度」の損しない使い方も
病院や薬局で当たり前のように提示しているが、実はその制度や給付の内容を詳しく知らない人も多い「公的医療保険(健康保険)」。加入している健康保険の種類によっても給付内容は異なり、受けられる給付内容を知らずに、申請をしないことで損をしている場合もある。そこで、節約アドバイザー・ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに、健康保険の制度について詳しく教えてもらった。
* * *
教えてくれた人
丸山晴美さん/節約アドバイザー。ファイナンシャルプランナー
22歳で節約に目覚め、1年間で200万円を貯めた経験がメディアに取り上げられ、その後コンビニの店長などを経て、2001年に節約アドバイザーとして独立。ファイナンシャルプランナー(AFP)、消費生活アドバイザー、宅地建物主任士(登録)、認定心理士などの様々な資格を持ち、ライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなどをテレビやラジオ、雑誌、講演などで行っている。
健康保険があれば医療費の支払額が安くなる
健康保険に加入し、健康保険証を持って病院に行くと、支払額が自己負担分のみとなります。自己負担額は年齢や所得によって異なり、原則6~70歳未満の場合は3割、70歳以上75歳未満は所得により2割または3割、75歳以上は所得により1割または3割の負担割合となっています。
公的医療保険の種類は3つ
公的医療保険の種類は大きく分けて3つあります。1つ目が、会社員や公務員などが加入する「被用者保険」、2つ目は自営業者や未就業者などが加入する「国民健康保険(国保)」、3つ目が職業に関わらず75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」です。保険の種類によって一部給付内容などが異なります。
これとは別に、自治体(市区町村)が保険者となって運営する「介護保険制度」があります。40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを利用することができます。
公的医療の主な給付内容
健康保険の主な給付内容は、診療、薬剤または治療材料の支給、処置、手術その他の治療、在宅医療・看護、入院・看護などを受けた際に一部負担金を払うことで医療を受けることができる「療養の給付」があり、健康保険の代表的な給付です。
そのほか、医療費をすべて立て替えたときに、かかった費用の一部が払い戻される「療養費」、病気やけがで移動が困難な患者が、意思の指示で一時的・緊急的に移送された場合に支給される「移送費」、子どもが生まれたときに支給される「出産育児一時金」、本人や家族が亡くなった時に支給される「埋葬料」や「葬祭費」などもあります。
健康保険が使えないケース
健康保険の制度の目的からはずれるような病気やケガをしたときは、給付が制限されることがあります。健康保険の給付の対象となるのは、治療方法として安全性や有効性が認められ、あらかじめ国によって保険の適用が認められている療養に限られます。また、労働者が業務中や通勤中にケガなどをした場合は、健康保険を使うことができず「労災保険(労災)」を使って治療や療養等と行うことになります。
健康保険が使えない一例として、入院時の食事代、入院したことによってかかる雑費や日用品代、差額ベッド代、保険適用外の治療費や手術代の例として、仕事や日常生活に差し障りのないニキビやホクロ、そばかすの治療、健康診断、生活習慣病検査、人間ドック、予防注射、高度先進医療費です。他にも、正常なお産や日常生活や疲労による肩こり・腰痛等の整骨院、針・きゅう、マッサージ等の施術、美容のための整形手術など、医師が必要な治療と認めないものです。
国民健康保険(国保)の加入者は対象外の手当
ケガや病気の治療のために仕事を休んだ際、もらえるはずだった給与の一部が給付される「傷病手当金」や、出産のために働く女性が仕事を休んだ際、もらえるはずだった給与の一部が支給される「出産手当金」などもありますが、これらは国民健康保険(国保)では給付されません。
なお、「傷病手当金」、「出産手当金」の支給対象は給与の支払いのない被保険者(本人)
のみで、家族は対象外です。また、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金もしくは出産手当金から、給与支給分を減額して支給されます。
医療費が高額な場合に利用できる「高額療養費制度」
支払うのは自己負担額のみとはいえ、医療費自体が高額になった場合は、自己負担額も高額になります。そんなときは、「高額療養費制度」を利用することで、1日から末日までの1か月で医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた分が後で払い戻されます。
医療費が高額になることがあらかじめわかっている場合は、「限度額適用認定証」を事前に申請し、保険証と併せて窓口に提出することで「高額療養費制度」を利用でき、1か月の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
国民健康保険の場合、保険証に記載されている自治体の窓口(区役所など)に直接持参するか、郵送で申請します。会社員の場合は、会社の総務課を通して申請するか、健康保険証に記載されている協会もしくは組合の各都道府県支部へ郵送にて手続きをします。
マイナ保険証(健康保険証を紐づけているマイナンバーカード)の場合、これらの手続きは不要です。ただし、低所得者の場合は申請が必要です。
複数受診や同一世帯分も合算可能
1人1回分では上限額を超えない場合でも、複数回の受診や、同じ世帯で同じ医療保険に加入しているほかの家族に関しても、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1か月単位で合算することができます。ただし、共働きでそれぞれ健康保険に加入している場合は、同一世帯とみなされません。国民健康保険の場合は、同じ保険証の番号を持つ家族を同一世帯とします。
また、過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります。医療費負担が重くならないための制度がさまざまあるため、該当する場合は忘れずに申請するようにしましょう。
申請先は保険の種類によって異なりますが、会社員の場合は健康保険組合または協会けんぽ、国民健康保険の場合は市町村の国保担当窓口となります。
医療費と介護費を合算して払い戻しを受けられる制度も
毎年8月から翌年7月までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が高額になる場合は、自己負担限度額を超えた金額が、医療保険と介護保険の比率に応じて両方から払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」というものもあります。
限度額は年額56万円を基本として、医療保険の各制度や所得・年齢区分に応じて細かく設定されます。上限を超えたら自治体から申請書が届き、申請書に必要事項を記入したものを郵送し、自治体が申請書を受理すると、介護自己負担額証明書が届くので、それを医療保険者へ申請します。
こうした制度をきちんと把握し、必要に応じて申請したり、利用したりすることで、医療費や介護費用における家計の負担を抑えることができます。