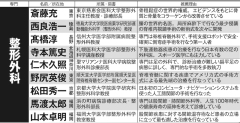血糖値を下げる“簡単な習慣”を糖尿病専門医が指南「3食の比率は3:2:1」「食事はゆっくり」「飲み物は水、お茶、りんご酢」
健康のために注意したいのが、血糖値を上げないことだ。その対策として糖質摂取を抑えることなどが知られているが、日々のちょっとした工夫だけでも血糖値を下げることができるという。『ミスター血糖値が教える 7日間でひとりでに血糖値が下がるすごい方法』(アスコム)を上梓した、糖尿病専門医の矢野宏行さんに詳しい方法を教えてもらった。
教えてくれた人
糖尿病専門医・矢野宏行さん
やの・ひろゆき。やのメディカルクリニック勝どき院長、医学博士。日本医科大学卒業後、同大学附属病院に勤務。その後、国立国際医療研究センター研究所の糖尿病研究センターで糖尿病について研究。24時間の血糖値の動きを調べつくし、血糖値について熟知していることで、「ミスター血糖値」の異名を持つ。著書に『ミスター血糖値が教える 7日間でひとりでに血糖値が下がるすごい方法』(アスコム)など。
糖質がどのくらい含まれているか把握することから
血糖値を下げるためにまず行いたいのが、「糖質が何にどれくらい含まれているか」を把握することだ。ご飯や麺、パンといった主食になる食品、ピザやお好み焼きなどの小麦製品、お菓子やジュースなどの砂糖が含まれたもの、さつまいもやかぼちゃなどの甘味がある野菜などに糖質が多く含まれていることは何となく知っている人も多いだろうが、1食、または100gあたりどのくらいの糖質が含まれているかを大まかに把握しておくと、より効率的に血糖値をコントロールすることにつながる。
「糖質量をメインテーマにした本はありますし、『糖質量』で検索すれば詳しいデータを載せているWEBサイトがいくつもヒットするので、そういったところから、情報を得るといいでしょう」(矢野さん・以下同)
3食の比率は3:2:1に
忙しい朝は軽めに、昼はそこそこ、夜一番しっかり食べるといった食生活を送っている人は多いだろう。しかし、血糖値を下げたいのであれば、朝はしっかり、昼はそこそこ、夜は軽めに食べるという、比率で言えば「3:2:1」の食生活が望ましい。
「1回の食事の量を減らし、回数を増やすという方法も効果的です。一度に摂取する糖質の量を抑えることにより、血糖値スパイクの波を穏やかにする(上下動の幅を小さくする)ことが期待できます」
スローフードとカーボラストを徹底
食事にかける時間と食べる順番も重要だ。矢野さんは、食事の時間はできるだけ長くし、ゆっくりと食事をとる、「スローフード」を意識することをすすめている。また、食べる順番に関しては、たんぱく質を含むおかずや野菜、汁物や副菜などを食べてから、最後に主食を食べる「カーボラスト」を徹底するのがおすすめだという。
「同じ食事内容でも食べる順番を工夫するだけで食後血糖値の上昇を抑えることができます」
子ども用の茶碗を使う
さらに、矢野さんは子ども用の茶碗を使うことをすすめている。子ども用の茶碗を使えば盛られるご飯の量は少なくなり、完食しても、大人用の茶碗の半分くらいの量にとどめられるためだ。
「加えて、よく噛んで咀嚼回数を増やすことを心がけましょう。満腹中枢を刺激すると、物足りなさが軽減されます。せっかく子ども用のお茶碗を使っても、おかわりをしてしまったら元の木阿弥なので、1杯で済ませることが鉄則です」
飲み物で血糖値の上昇を予防する
1日の食事の比率を変えたり、食事のペースを変えたりする習慣は、定着に時間がかかることも多いだろうが、意識的に飲む物、飲まない物を決めて取り入れることならば、すぐ始められて継続しやすいだろう。
飲み物は水かノンカフェインのお茶
ジュース類には非常に多くの糖質が含まれているため、これをやめるだけでも糖質の摂取量を減らすことができる。
「ベストは水。これが唯一無二の正解です。コーヒーやお茶を飲む場合は、ノンカフェインのものにしましょう。お酒を飲む場合は、醸造酒よりも蒸留酒。これが定石中の定石です」
食事の前にはリンゴ酢や炭酸水を飲む
矢野さんによれば、食事の前に、リンゴ酢や炭酸水を飲むのも血糖値を下げることにつながるという。リンゴ酢に含まれる酢酸は糖質の分解と吸収を緩やかにする働きがあり、血糖値の上昇を抑える効果があるためだ。また、定期的にリンゴ酢を摂取することで、インスリン抵抗性も改善するそうだ。
「リンゴ酢は、市販のもので問題なく、どのメーカーのものでも構いませんし、ガブガブ飲む必要もありません。1回につき大さじ1杯(15ml)程度でOK。継続すれば、徐々に効果を実感できるようになるでしょう」
一方、炭酸水は直接糖質に影響を及ぼすわけではないが、空腹感を減らすことにつながるため、食事の量を抑えやすくなる。
「こちらもリンゴ酢同様、たくさん飲む必要はありません。コップ1杯でじゅうぶんです」
●脳トレは認知症予防に効果がない? 医師がすすめる有効な予防法は“外出”、その理由とは
●シニア世代におすすめ!お粥をおいしくする100円ショップのちょい足し食材と活用法を節約アドバイザーが指南
●《年を重ねても元気でいるカギは“肝臓”》肝機能が弱る原因はアルコールと脂肪肝 対策には青魚や魚介類を、サプリのとりすぎは注意