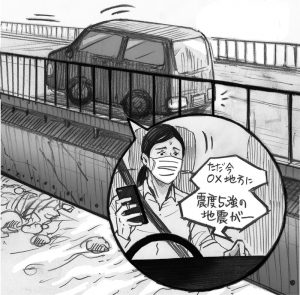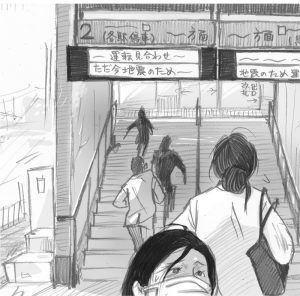追悼|田村正和さん 歴代主演1位の「日曜劇場」など数々の名作を振り返る【まとめ】
名優・田村正和さんが4月3日に亡くなっていたことが、5月18日に報じられた。映画、ドラマ、演劇と幅広い分野で活躍した田村さん。介護ポストセブンでは、昨年からテレビドラマ「日曜劇場」シリーズの名作を、ドラマレビューで定評のあるライター・近藤正高さんにご紹介していただいている。これまでに掲載した田村さん主演作品をまとめて振り返る。ここまで田村正和主演作品を考察しているレビューはない。二枚目からコミカルな役まで幅広く演じてきた田村さんの魅力をお伝えしたい。
田村正和はモテ男の象徴!?出演ドラマから紐解くそのスター性
田村正和という俳優は、スター不在といわれる時代にあってスターであり続けた稀有な存在であった。田村は本連載のテーマであるTBS系の「日曜劇場」でも、1993年に連続ドラマ枠となって以降では歴代最多の8作で主演を務めている。
ここで田村正和の経歴を簡単に振り返っておこう。生まれたのは1943年。9歳のときに亡くした父親の阪東妻三郎(本名・田村伝吉)も、戦前から戦後にかけての映画界の大スターであった。兄の高廣、弟の亮も俳優となったが、スターとしての資質は誰よりも彼に引き継がれている。1961年に松竹大船と専属契約を結び、木下惠介監督の『永遠の人』で本格デビューした。NHKの大河ドラマ第1作『花の生涯』などテレビにも出演を始め、1966年にはフリーとなる。
ブレイクしたのは、1972年、テレビ時代劇『眠狂四郎』(関西テレビ・フジ系)で主演したのがきっかけだった。原作者の柴田錬三郎は、田村の狂四郎を甘さとニヒルを兼ね備えていると可愛がり、「10年経ったら素晴らしい狂四郎になるだろう」と家族にも洩らしていたという(能村庸一『実録テレビ時代劇史』ちくま文庫)。柴田の予想は的中し、狂四郎は田村の当たり役となり、後年にいたっても特番ドラマとして放送されている。劇中、狂四郎がゲスト女優の着物をはぐ「帯解き殺法」がエロティシズムの匂いを漂わせた。おそらく田村はモテるというイメージは、このあたりからできあがっていったのだろう。
狂四郎にしてもそうだが、田村はデビュー以来二枚目で売ってきた。そんな彼に転機が訪れる。それは1983年、TBS系の金曜夜8時台のドラマ『うちの子にかぎって…』に主演したことだ。『3年B組金八先生』をはじめ学園ドラマが多かった同枠だが、このドラマでも小学校を舞台に、田村が子供たちに振り回されるという教師を好演した。二枚目半というべきその役柄は、視聴者に親しみを与え、以後、『パパはニュースキャスター』をはじめ田村がホームドラマに出演する端緒となる。
田村に新たな路線を敷いたのは、当時まだ30代だった八木康夫プロデューサーである。八木は、同じく1983年に放送された単発ドラマ『昭和四十六年 大久保清の犯罪』で初めてプロデュースを手がけ、主人公の凶悪犯にビートたけしを起用していた。お笑い芸人であるたけしにはシリアスな俳優としての道を拓いたのに対し、田村は逆の方向へと導いたともいえる。
もっとも、二枚目を演じても、二枚目半を演じても、田村はどこまでも田村だった。独特のしゃべり方はモノマネの格好の対象となった。『ニューヨーク恋物語』をパロディに仕立てたとんねるずをはじめ、近年におけるハリウッドザコシショウの「誇張しすぎた田村正和のモノマネ」にいたるまで(これは後年のヒット作『古畑任三郎』の田村を真似したものだった)、彼をネタにしたタレントや芸人は数多い。そんなふうに笑いのネタにされるのは、田村が謎めいたところを残し、現実感がないからでもあるのだろう。そうした存在は、すでに80年代に入るころにはテレビでは貴重になっていた。
田村正和・篠ひろ子主演『カミさんの悪口』は夫婦あるある満載で今こそ必見!
TBS系の「日曜劇場」(当時は「東芝日曜劇場」)では1993年10月から3か月間、田村正和・篠ひろ子主演の『カミさんの悪口』(全11話)が放送された。単発ドラマ枠から連続ドラマ枠に移行した「日曜劇場」では第3作にあたる。原作は直木賞作家・村松友視(視の表記は正しくは「示」に「見」)の『小説・カミさんの悪口』。ちなみに主演のひとり、篠ひろ子はこのドラマに出演する前年、1992年に直木賞を受賞した作家の伊集院静と結婚している。
本作で篠が演じたのは専業主婦の小泉由起子。田村が演じるのはその夫の小泉肇で、工業用塗料の専門メーカー(TBSチャンネルのあらすじ紹介などでは「中堅商社」となっているが誤り)に勤務している。夫婦は、18年前に駆け落ちして、結婚式も挙げないまま入籍したという過去を持つ。子供はおらず、1匹の子猫を飼いながらの2人暮らしだ。
名作ドラマ『カミさんの悪口』が主婦の心をつかんだ時代背景とその仕掛けを解析
『カミさんの悪口』が放送されたのは1993年10月〜12月。バブルが崩壊して2〜3年ほど経ち、不景気が続いていたころである。しかしドラマのなかに不況の影はまったくといっていいほど感じられない。現実の企業では広告費が削減され始めたころだが、田村演じる小泉肇の勤務する塗料メーカーは新たに開発した芳香剤を売り出すにあたり、テレビCMを中心に大々的な宣伝活動を展開しようとしていた。
肇はこの宣伝プロジェクトで本部長に抜擢され、商品のネーミングやCMづくりのため大勢の部下たちと日々議論を重ねる。ただ、商品名を社内公募で決めたあたりを見ると、予算の額は当初から抑えられていたのかもしれない。それでも、肇は同期の2人……常務の茂木(橋爪功)と社長室長の片桐(角野卓造)とよく連れ立って豪華なランチをとっているし、クラブ(ホステスがいるほうのクラブ)で夜遅くまで飲んではタクシーで帰宅しているところなどを見ると、不況どこ吹く風で、まだ時代的に余裕が感じられる。そもそも出張先で常務が浮気し、その相手が東京まで訪ねてきて騒動が起こるという展開からして、いまから見るとどうも牧歌的だ。
茂木の浮気相手である大場咲(松本明子)は、前回説明したとおり、ひょんなことから肇の家に転がり込み、妻の由起子(篠ひろ子)とは家事の手伝いをするうちに親しくなっていく。子供のいない夫婦にとって、咲は緩衝剤のような役割も担うことにもなる。思えば、TBSのホームドラマでは、主人公の家族が外部からやって来た人間によって活性化するという展開がよく見られた。たとえば、70年代の『寺内貫太郎一家』や『ムー』『ムー一族』といったドラマでは、家業(それぞれ石屋と足袋屋)に従事する職人に、お手伝いさんも加わって、さまざまな騒ぎを引き起こした。『カミさんの悪口』も、咲の役どころを見るかぎり、この流れを汲んでいるといえる。ちなみに、本作の脚本を手がけた山元清多は、『ムー』『ムー一族』の脚本陣にも参加しているから、そこでのお手伝いさん(樹木希林と岸本加世子が演じた)のイメージが、咲の設定にも反映されたのかもしれない。
『カミさんの悪口』は配信サービス「Paravi」で視聴可能(有料)
名作ドラマ『夫婦。』のセリフが時を超えて心に響く理由
『カミさんの悪口』(1993年)から11年後、2004年の10月期には黒木瞳との夫婦役でその名も『夫婦。』が放送された。「日曜劇場」における田村の主演作はこれで6作目、黒木と夫婦を演じたものとしては3作目だった。この間、2002年10月には同枠が1956年にスタートして以来、単独でスポンサーについていた東芝が降板、名称も「東芝日曜劇場」から現在の「日曜劇場」に改められている。改称して最初の作品は、やはり田村・黒木主演の『おとうさん』だった。
劇中に登場する家電やメディアも『カミさんの悪口』から『夫婦。』では大きく変わっている。洗濯機は縦型からドラム式になり、テレビはブラウン管から薄型のハイビジョンテレビになった(『夫婦。』放送の前年、2003年12月には地上デジタル放送も始まっている)。それ以上に大きな変化は、携帯電話とインターネットの普及だろう。とくに携帯は、ドラマに出てくる登場人物全員が持つまでになった(まだスマホではなく二つ折りの携帯が主流の時代だが)。『夫婦。』で田村演じる通販会社の社長・山口太一は、携帯メールのおかげで浮気がバレてしまう。
そういえば、『夫婦。』と、タイトルに「。」が入るのも時代を感じる。人気アイドルグループのモーニング娘。の影響もあるのだろう。「日曜劇場」ではこれ以前にも、2000年に同じく田村・黒木主演で『オヤジぃ。』が放送されている。こちらはセリフと考えれば、「。」がつくのも違和感はない。では、『夫婦。』の「。」はどう解釈すべきなのか。まず思いつくのは、このころすでに一般化していたウェブ検索への対処である。夫婦は普通名詞なので、そのままでは検索すると夫婦に関するあらゆるページが引っかかってしまい、ドラマの情報にたどり着けない。そこで「。」をつけたのではないか(ただし、実際にいま『夫婦。』で検索しても、上位にはドラマに関するページは出てこない)。
さらに、ここで使われる「。」は、英語の「the」のような定冠詞とほぼ同じという解釈も成り立つように思う。すなわち『夫婦。』は『ザ・夫婦』に等しく、特定の夫婦を描きながらも、そこに普遍性をも浮かび上がらせようという意図を示しているのではないか。事実、このドラマを全編通して見ると、そのような内容になっている。
小説で復活が話題『古畑任三郎』は田村正和と日曜劇場にも意外な影響!?
田村正和を語る上で欠かせない作品『古畑任三郎』シリーズ。製作局も違うフジテレビの作品だが、のちに日曜劇場の田村主演作品にも大きな影響を与えていることがわかった。
脚本家の三谷幸喜も、自作の人気ドラマの主人公・古畑任三郎を、テレビではなく新聞の連載エッセイの特別編という形式で発表した新作小説「一瞬の過ち」の中で復活させた(『朝日新聞』2020年4月23日~)。まさかこういう形で古畑と再会するとはファンも思いもしなかっただろう。三谷もおそらく、こういう不安な時期こそ、昔馴染みのキャラクターを登場させれば人々もいっときながら落ち着けるのではないかと、本能的に察知したのではないか。
ドラマ『古畑任三郎』(フジテレビ系)が田村正和の主演によりスタートしたのは1994年。同じく田村主演で、本連載で前回までとりあげた『カミさんの悪口』が「日曜劇場」で放送された翌年のことだ。よく知られるように本作は、毎回豪華ゲスト扮する犯人が事件を起こし、その動機やトリックを警部補の古畑任三郎があばいてみせるという1話完結型の連続ドラマであった。これが好評を博し、1996年と1999年に再び連続ドラマとして放送されたほか、その間にスペシャル版も何作かつくられ、2006年に3夜にわたって放送された『古畑任三郎FINAL』をもって一応の完結を見た。
田村は、黒ずくめの衣装に現場へは自転車に乗って現れるという風変わりな刑事を好演してみせ、古畑任三郎は彼の代名詞のひとつとなった。以前書いたように、田村はドラマでプレイボーイを演じることが多かった。そんな彼を、独身で女っ気もほぼ皆無の古畑役に起用するというのは、まさにコロンブスの卵的な発想の転換であったといえる。ふたを開けてみれば、どこか世間離れした古畑のキャラクターはむしろ田村に適役であった。
ついでにいえば、『古畑任三郎』というタイトルもかなり思い切ったものだった気がする。おそらく時代劇や大河ドラマ以外で、登場人物のフルネームのみのタイトルはほとんどなかったのではないか。たしかに過去にも『寺内貫太郎一家』のような例はあるにはあるが、それにしたって「一家」とつけてホームドラマとわかるようになっていた。『古畑任三郎』も刑事物と認知される以前、新聞の番組表などでは時代劇と間違われないよう『警部補・古畑任三郎』と表記されていたという。
もっとも、『古畑』のヒット後もこの形のタイトルは存外少ない。映画では高良健吾主演で『横道世之介』(2013年)というのがあったが、ドラマでは新シリーズの放送が待たれる「日曜劇場」の『半沢直樹』ぐらいだろう。思うに、この手のタイトルをつけるのは、つくり手によっぽどこの登場人物は絶対視聴者に受け入れられるという自信がないかぎり躊躇してしまうのではないか。
話が横道にそれたが、再び本題に戻ると、田村は『古畑任三郎』と並行して、「日曜劇場」でも『カミさんの悪口2』(1995年)、『カミさんなんかこわくない』(1998年)、『オヤジぃ。』(2000年)、『おとうさん』(2002年)、『夫婦。』(2004年)、『誰よりもママを愛す』(2006年)とほぼ2年おきに出演してきた。いずれも八木康夫がプロデューサーを務めたホームドラマだが、『オヤジぃ。』以降は脚本に遊川和彦、妻役に黒木瞳を迎え、作品ごとに人物設定や世界観こそ違うもののシリーズ物的な雰囲気を漂わせていた。
なお、遊川和彦の脚本家としてのデビュー作は、同じく田村主演、八木プロデューサーによる『うちの子にかぎって…スペシャルII』(1987年)であった。以後彼は、TBSでは『オヨビでない奴!』(1987年)、『ママハハ・ブギ』(1989年)、『予備校ブギ』(1990年)、『ADブギ』(1991年)、『人生は上々だ』(1995年)など八木プロデューサーのもとで頭角を現していく。『オヤジぃ。』の前年、1999年には、松嶋菜々子演じる高校教師が、滝沢秀明演じる生徒と禁断の恋に落ちる『魔女の条件』で大ヒットを飛ばした。
『古畑任三郎』リメイクの噂で木村拓哉新キャストの期待も。田村正和につながるものは?
『古畑任三郎』のドラマの続編がつくられるかもしれないという噂が流れ、もし本当に実現するなら、すでに高齢で再登板が難しそうな田村に代わって誰がやるのかという話題でSNSは持ちきりとなった。もっとも、『古畑任三郎』は、当連載のテーマである「日曜劇場」のドラマではないので、これ以上とりあげると“これじゃ「水曜だけど日曜劇場研究」じゃなくて「日曜劇場研究だけど古畑任三郎研究」だ”などと言われてしまうかもしれない。それでもせっかくの機会なので、今回はまずこの話題に乗ってみようと思う。
じつは作者の三谷幸喜は、古畑の役を当初、玉置浩二で考えていたという。三谷いわく《もっと悪魔みたいな、真っ黒い服装で無表情で淡々と事件を解いていく、そういうイメージだった。/でもそのイメージを膨らませているうちに田村正和さんがピッタリだなと思うようになった》。だが、最初に田村にオファーした時には、従来の刑事ものと思われたらしく、断られてしまう。そこで三谷は、何とか田村に演じてもらうべく、スタイリッシュでおしゃれな刑事にしようと、田村を想定した台本を書き、《古畑は今までの刑事ドラマとは違って、ピストルも持たないしアクションシーンもない。論理的に事件を解決する刑事です》と説明したという。台本を読んだ田村はその意図を理解し、一転して引き受けてくれたのだった(三谷幸喜・松野大介『三谷幸喜 創作を語る』講談社)。
いま思い返せば、古畑の登場は画期的だった。それまでアクションシーンが目玉となることが多かった日本の刑事ドラマの流れを変えたといってもいい。おそらく古畑がいなければ、『踊る大捜査線』(フジテレビ系、1997年)でサラリーマンから刑事に転職した織田裕二演じる青島俊作も、『ケイゾク』(TBS系、1999年)における生活力はまるでないが天才的な頭脳を持ち、過去の迷宮入り事件を解決していく中谷美紀演じる柴田純も生まれなかっただろう。テレビ朝日系で2000年より続く人気シリーズ『相棒』で水谷豊演じる杉下右京にいたっては、独特のしゃべり方といい、浮世離れしたキャラクターといい、また演じ手の代名詞となるほどハマり役となったことといい、古畑の直系と位置づけられそうだ。
田村正和さんのご冥福をお祈りいたします。
文/近藤正高 (こんどう・ まさたか)
ライター。1976年生まれ。ドラマを見ながら物語の背景などを深読みするのが大好き。著書に『タモリと戦後ニッポン』『ビートたけしと北野武』(いずれも講談社現代新書)などがある。