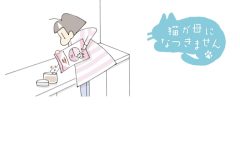猫が母になつきません 第406話「いわない」
『医療法第1条の4第2項「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。(*1)』
前回も冒頭に載せましたが、何度読んでも虚しさを覚えます。
認知症ではありましたが体はとっても元気だった母。私と暮らしていた頃はまったく薬も必要なくて、健康でいてくれることはありがたいと思っていました。しかし、施設ではそれは問題でした。コロナ禍で外には出られず、エネルギーがありあまっている母…妄想いっぱいなので現実では対処のしようがないような要求をしてくる。入所したころは「教員採用試験を受ける」と毎日言っていて受験票を探したり、明日試験だからバスに乗ると言ったり、でもそれはそれで、その場をしのぐような対応はしてくれていたようです。夜中に起き出してくるので朝までドアに鍵をかける許可を出しましたが、母はけっこう高めの位置にある窓から中庭に抜け出し、朝方発見されたこともありました。とにかく元気すぎたのです。
薬にさまざまな副作用があるとして、その説明を受けたとして、それを拒否する選択肢はあったのか? その施設に居続けるかぎりはなかったと思います。母がかかった認知症外来はその施設と地域連携している認知症医療センターでした。その施設と認知症外来は本当にしっかり「連携」していて、毎回私が母に付き添って診察を受けにいくのですが、いつも事前に施設とその病院のソーシャルワーカーが下打ち合わせをしているらしく、私と母は一応そこに連れてこれらただけで医師は私たちの話はほとんど聞いておらず、診察するまでもなくすでに母への処方は決まっているようでした。
施設「活発に動かれるので、このままではご本人が怪我されるかもしれません(元気すぎて困ってます)」
医師「それは危ないですね、薬で調整しましょうね(じゃ、薬で動けなくしましょうね)」
↑あくまで私の悪い想像の会話です(失礼)。
でも私が感じた《プロ》の怖さはこんな感じ。私はいつも彼らの《言い換え》に惑わされたし、彼らが《あえて言わないこと》の中に私がほんとうに知らなくてはならない事実がありました。私は途中でそれに気がつきましたが、はじめてのことでもあり対応はいつも後手にまわってしまいました。プロを信じようとした結果です。まかせっきりにしてはいけなかった。無知でもいけなかった。
認知症医療というのは特殊だと思いました。患者が働き盛りで社会復帰を目指している人だとか、果てしない可能性を秘めた子供だとか、そういうケースとは違うぞんざいさを感じました。彼らにとって母は「わけがわからなくなった人」で私は「母の面倒がみれなくて施設にあずけた人」で、「私たちがどうにかしてあげないと困りますよね」という態度があからさまでした。
言葉は丁寧でやさしくてもそこに《尊厳》はありませんでした。もちろんそういうところばかりではないと思います。私は母のための《尊厳》を求めてかけずりまわりはじめました。しかし薬を飲み始めてからの展開はとても早く、ついていけなかったのです。
12年前の私へ
「病院には《医療法第1条の4第2項》をTシャツにして着ていくべし」
↑そのくらいの気持ちでってことです(押忍)
*1(厚生省HP《医療法》https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80090000&dataType=0&pageNo=1)
【関連の回】
作者プロフィール
nurarin(ぬらりん)/東京でデザイナーとして働いたのち、母と暮らすため地元に帰る。ゴミ屋敷を片付け、野良の母猫に託された猫二匹(わび♀、さび♀)も一緒に暮らしていたが、帰って12年目に母が亡くなる。猫も今はさびだけ。実家を売却後60年近く前に建てられた海が見える平屋に引越し、草ボーボーの庭を楽園に変えようと奮闘中(←賃貸なので制限あり)。
※現在、1話~99話は「介護のなかま」にご登録いただいた方のみご覧になれます。「介護のなかま」のご登録(無料)について詳しくは以下をご参照ください。
https://kaigo-postseven.com/156011