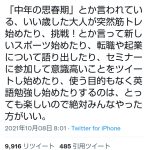「健康は他者とのかかわりにも影響を受ける」世界的な長寿研究の第一人者が解説する“社会的孤立”と健康の関係
私たち人間は、自分が集団のなかで尊重されているかどうか、そして社会的階層のどのあたりに位置しているかを本能的に知ることができるようだ。社会的立場に関する考えは、目に見える認知的影響に直接変換される。たとえば、休憩時間のドッジボールでチームメンバーを決めるときに、なかなかメンバーに入れてもらえずに身もだえた経験のある人(メンバーの指名順が校庭における社会的立場のバロメーターなのは明らかだ)は、小さな子どももチーム内での人気を意識しているとわかっているだろう。
人気のない子どもたちは、ごく幼いうちからアウトサイダーの立場を内面化する。ただ不幸せなだけではない。社会に関する新たな情報が入ったときの脳の処理が、人気のある子どもの脳と違ってくるのだ。ある研究では、人気のある子どもとない子どもに単語の羅列を見せて、単語そのものではなく文字の色を言うように指示した。この実験アプローチは「ストループテスト」と呼ばれ、特定の刺激に対する認知感度を評価するために広く使われている。
非合理的な恐怖に苦しむ人は、「蛇」や「蜘蛛」といった単語が含まれていると、文字色を答えるのが遅くなる。抑うつ状態にある人は「悲しい」といった単語があると文字色を答えるのが遅くなる。そして、人気のない子どもは、「孤独」や「拒絶」などの単語が含まれていると文字色を言うのが遅くなる。情緒的な干渉を受けてしまうからだ。数ミリ秒の違いなので、子どもたちは反応が遅くなっていることに気づかないが、脳は自身の弱みに関連する単語の意味に敏感になっている。
健康は他者とのかかわりにも影響を受ける
大人もまた、みずからの社会的立場を深く認識している。カリフォルニア大学サンフランシスコ校の心理学者、ナンシー・アドラーは、社会的ステータスを認識する際のシンプルで巧妙な尺度として、10段のはしごの絵を開発した。アドラーは被験者に対し、このはしごは最も社会的に恵まれた人たちをいちばん上の段、最も恵まれていない人たちをいちばん下の段で表していると説明する。それから、被験者本人がはしごのどの段にいるかを尋ねる。被験者ははしごのたとえを容易に理解し、自分自身をすばやくその上に配置する。驚くべきは、配置された場所によって狭心症やうつ病など心身の健康状態だけではなく、どれだけ長生きするかも予測できることだ。
アドラーが開発した社会的立場の主観的尺度は、より客観的な社会的地位の指標である収入や職業などよりも、健康状態の行く末を正確に予測していた。これは、健康状態は本人がもっているものだけではなく他者とのかかわりにも影響されるという、抗いがたい指標だ。
科学者たちは、社会的孤立が健康状態の悪さに結びつく理由を追求してきた。人は孤立したと感じるから病気になるのだろうか。それとも、実際に孤立することの作用で──たとえば、具合が悪くなったときに回復を助けてくれる社会的ネットワークがないゆえに──病気になるのだろうか。つまるところ、社会集団に属することのポジティブな影響の一部はわかりやすく、行動にかかわってくる。ほかの人と一緒に食事をする人は、前日のピザの残りを食べるのではなく、バランスのよい食事をとる可能性が高い。また、具合が悪くなったときに病院に行く可能性も高い。
愛する家族にとやかく言われてようやく自分自身の面倒をみるようになるのはよくある話だ。たとえ何も言われなかったとしても、人に頼られているとわかっていると、生活習慣が向上する。私は、子どもが生まれて運動を始めたり禁煙したりした親をたくさん知っている。自分たちなしでは子どもがどれほど無防備になるかに気づいたので、子育てをまっとうできるような生活習慣を確立したわけだ。
◆著者・監修者・訳者情報
【著者】ローラ・L・カーステンセン(Laura L. Carstensen)さん
スタンフォード大学心理学部教授、ならびに同大学フェアリー・S・ディキンソン・ジュニア記念講座公共政策学教授。スタンフォード大学長寿研究所の設立者で所長も務める。カーステンセン博士の研究は20年以上にわたってアメリカ国立老化研究所から支援を受けている。グッゲンハイム・フェロー、アメリカ国立衛生研究所(NIH)メリット賞受賞者、マッカーサー財団高齢化社会ネットワーク会員でもある。カリフォルニア州ロス・アルトス・ヒルズ在住。
【監修】
米田隆さん
早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所招聘研究員、公益社団法人日本証券アナリスト協会プライベート・バンキング(PB) 教育委員会委員長、株式会社青山ファミリーオフィスサービス取締役。早稲田大学法学部卒業。日本興業銀行の行費留学生として、米国フレッチャー法律外交大学院修了、国際金融法務で修士号取得。金融全般、特にプライベート・バンキング、ファミリービジネス及びファミリーオフィスの運営、ファミリーガバナンスの構築、新規事業創造、個人のファイナンシャルプランニングと金融機関のプライベート・バンキング戦略などを専門とする。著書に『世界のプライベート・バンキング[入門]』(ファーストプレス)、訳書に『新版 究極の鍛錬』(サンマーク出版)、『50 歳までに「生き生きした老い」を準備する』(ファーストプレス)、『ファミリービジネス 賢明なる成長への条件』(共訳、中央経済社)などがある。
【訳者】
二木夢子さん
国際基督教大学教養学部社会科学科卒。ソフトハウス、産業翻訳会社勤務を経て独立。訳書に『スケーリング・ピープル』『TAKE NOTES!――メモで、あなただけのアウトプットが自然にできるようになる』(ともに日経BP)、『Creative Selection―Apple 創造を生む力』(サンマーク出版)、『われわれは仮想世界を生きている』(徳間書店)、『EMPOWERED』『両立思考』(ともに日本能率協会マネジメントセンター)、『オリンピック全史』(共訳、原書房)などがある。