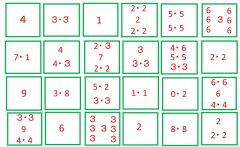精神疾患や認知症患者の「閉じ込め」は社会への過剰配慮
昨年12月23日大阪・寝屋川市の住宅街に建つ一戸建てで、柿元愛里さん(享年33)が、自宅敷地内のプレハブ小屋で、衣類も身につけず眠るように亡くなっているのが発見された。発見時の体重は19kg。司法解剖の結果、死因は凍死。極限の栄養失調状態で、極寒の環境に置かれていたという。
同居する両親が「娘が死んだ」と寝屋川署に自首したことで発覚したこの事件は、その後、衝撃の事実が続々と明らかになっている。
本人ではなく、「周囲への迷惑」優先になる社会
愛里さんが過ごしたプレハブ小屋は、簡易トイレと給水タンクを備えただけのわずか2畳半の空間で、二重扉で仕切られ、中からは開けられない仕組みになっていた。室内にもカメラが設置され、常時監視。食事は1日に1食。風呂にもほとんど入れてなかった。愛里さんはこのような状況下で15年前から監禁されていた。
監禁と保護責任者遺棄致死罪で逮捕された父親の泰孝容疑者(55才)、母親の由加里容疑者(53才)はともに容疑を否認し、「すべては娘のためだった」と供述している。
夫婦は娘を閉じ込めた理由について、愛里さんが15才頃に発症した精神疾患が原因だと供述している。暴れ回って家族に危害を加えることもあり、自傷行為も頻発していたためやむなく監禁状態としたと説明したのだ。すでに小6の頃から病の兆候があり、複数の病院で『統合失調症』と診断されたと話す。監禁も「療養目的だった」と語った。
同様の監禁事件としては、2007年、千葉県の介護施設「ぶるーくろす癒海館」で、入居する認知症患者をペット用の檻に閉じ込めた写真が流出し、騒動になったものがある。
同様の事件はその後も絶えず、厚労省の調査では介護施設の職員による入居者への虐待は2015年度に408件(前年比36%増)と、9年連続で増加。虐待を受けた高齢者のうち、約3割は身体拘束を受けていた。介護サービス会社「(株)大起エンゼルヘルプ」取締役で、介護福祉士の和田行男氏が語る。
「人手不足の問題もあるのですが、認知症のかたの“閉じ込め”が発生する最大の原因は、日本の介護施設が本人ではなく『周囲の迷惑』を考えざるをえない状況にあるからです。
本来、認知症の入居者が外出したいのであれば、職員が付き添って行動を支援すればいい。
しかし、そうなると1人職員が取られてしまい、他の仕事が滞る。予期せぬ外出は周辺住人からの苦情になりかねないし、事故のリスクも高くなる。結果、施設に鍵をかける、身体を拘束する、投薬で動けなくするなど、本人の意思を鑑みない行動が起きてしまう。支援の主体が認知症当事者ではなくなっているわけです」
「警察や探してくれた地域住人のかたがたにあまりにも申し訳なくて…」
認知症の母親(83才)を自宅で介護する専業主婦のA子さん(埼玉県在住・53才)もこう語る。
「母は1年ほど前から徘徊を始め、一度行方不明になり、警察に相談して防災無線で呼びかけたほどです。運よく自宅から1km離れた農道で見つかったのですが、その日以来、出かける時は自宅の玄関に南京錠をかけ、母親が物理的に外に出られないようにしています。警察や捜してくれた地域住人のかたがたにあまりにも申し訳なくて…。もし2度目が起きたら、と思うと心が耐えられないのです」
精神疾患、認知症の現場でともに見られる、社会への過剰なまでの配慮…。こうしたことに日本特有の「恥の文化」がここに表れていると言うのは、精神科医の香山リカ氏だ。
「行動基準の源が自己ではなく“世間”にあるのです。とりわけ精神疾患や認知症は伝統的に身内の責任との偏見が根強く、一族郎党にまで迷惑がかかるので、患者を世間の目から遠ざけようという風潮が根強い。近年は地域社会のコミュニティーが希薄なため、患者を持つ一家がより孤立しがちです。最近は何かと個人情報保護が叫ばれることもあり、ご近所さんの事情に深入りしない傾向も強まっている。今の日本社会で寝屋川の事件が発生したのは、ある意味必然でした」
精神科病院を全廃したイタリアの都市
一方、欧米では世間ではなく、あくまで個人と個人の関係で物事を捉える。
「ゆえに、欧米では世間体を気にして患者を閉じ込めるケースはほとんどない。隔離される患者もゼロではありませんが、自傷他害の危険が極めて高い、という物理的な理由のみによるものです。
精神疾患も認知症患者にも個人として向き合いますし、特にキリスト教文化圏では、“神の前ではみな平等”の思想のもと、隔離ではなく地域で受け入れる文化が浸透しています」(香山氏)
特筆すべきはイタリア北部の都市・トレントだ。すべての精神科病院を廃止した同町では、精神疾患患者とその家族が医療機関や福祉機関に「専門家」として従事し、同じ病気で苦しむ患者や家族たちの居住や就労など、日常生活の支援をしている。
「fareassieme(一緒にやろう)」という運動から生まれたこの試みは、当事者同士が支え合うだけでなく、行政や地域と結びつき、大きな成果を上げているという。古来の文化と社会の変化が入り交じって生じた難題に、私たちはどう向き合うべきか。
和歌山県精神保健福祉家族会連合会の障害者施策推進委員長で、精神疾患患者の家族の支援活動を続ける大畠信雄氏は、この問題の只中にいる当事者として、地域の受け皿づくりを地道に行っている。
官民一体となって現状を少しでも変えるため、精神疾患患者の家族による講演会を全国で開き、同じ苦しみを分かち合えるよう家族同士の交流も進める。
実際にトレントにも飛び、医療現場で患者を拘束しない「開放処遇」や、当事者が経験や知識を生かして別の患者を支援する仕組みを現地で学び、日本社会に還元しようと努力を重ねている。
「精神疾患は患者の家族だけで抱えたら、必ず追い詰められます。だからこそ、病気のことを社会が正しく理解して課題を共有する必要がある。“他人事”から“わが事”に意識が変わるように、あきらめることなく啓発するのが当事者としての義務だと痛感しています」(大畠氏)
患者の家族が勇気を持って周囲に相談することが必要
精神疾患の生涯罹患率は3人に1人ともいわれており、超高齢化社会の今、認知症は誰もが他人事ではない。
前出の香山氏もこう語る。
「精神疾患も認知症も、画期的な治療法はありません。ありきたりな話ですが、地域のみんなで支えるしかないのです。“明日はわが身”という気持ちで一人ひとりが患者に向き合えば、巡り巡って必ず自分に返ってくる。患者の家族が勇気を持って周囲に相談し、みながそれに応えられる社会になれば、悲しい事件もなくなるはずです」
日本は恥の文化であると同時に“思いやり”の心も強く根づいている。患者と地域住人が共に手を取り合う未来は、決して夢物語ではないはずだ。
※女性セブン2018年2月8日号
【関連記事】