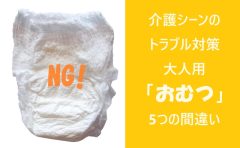顕在化しない在宅介護でのおむつ悩みへは「治療優先でおむつ対策の制度が必要」「失禁の原因となる疾病にアプローチすることが大切」おむつに向き合って10年の識者が発信中
排泄にまつわる悩みを抱えている人は多い。在宅介護や介護施設、病院などで使用される紙おむつに関しても、まだまだ情報が届きにくく、適切な使用がされていない場合も多いという。なかなか大きな声で語られることが少ない「排泄、おむつ」について積極的に発信を続けている八木大志さんに、現状や課題について伺った。
教えてくれた人/八木大志さん
WEBサイト「おむつ情報局」https://062.design/を主宰。理学療法士、福祉用具貸与事業所勤務を経て、「おむつ宅配便」を立ち上げるなど、おむつは自立支援の福祉用具と捉えて、適切な情報を届ける活動を続けている。
* * *
介護施設でも適切なおむつ使用は浸透していない
――八木さんがおむつに関心を持ったきっかけはなんだったんでしょうか。
八木さん(以下敬称略):理学療法士として4年間働いていたんですが、その際、患者さんの外出時の排泄、トイレの設備などの悩みが大きいことを知りました。その後、介護に必要な手すりの設置などをする住宅改修の事業所に勤務して、介護が必要な方におむつを配達する業務を担当したんです。そこでおむつの給付のことを知りました。おむつの給付は自治体よって差があるのですが、隠れたトラブルもいろいろとあり、おむつが必要な人は多いのに、適切な情報が届いていない実情を目の当たりにしたことが興味をもつきっかけになりました。
――2014年から10年以上、おむつにまつわることを発信されていますね。
八木:現在は、さまざまな介護の現場で、介護職としておむつの交換に関わり、指導をしたりしながら、最新のおむつ勉強会なども開催しています。
――介護施設でもおむつ交換は難しいという声があるのでしょうか。
八木:おむつの基本情報や交換の方法のカリキュラムは十分ではなく、施設がそれぞれ独自のやり方をしていることが多く、適切な使用は浸透していないという印象ですね。
――どのような問題がありますか。
八木:たとえば、尿とりパッドを何枚も重ねづけするようなことは、まだまだ起こっています。おむつ交換のときに1枚だけ抜けばいいから重ねておく。長時間、おむつを替えない状況になっている場合もあります。おむつを着けている人の使い心地が悪くなってしまうことも問題ですが、尿路感染症を引き起こしたり、おむつかぶれの原因にもなります。おむつかぶれを起こしている人は少なくないです。
行政主導でおむつの支給や使い方の指導が必要
――在宅でも同じようなことが起こっているでしょか。
八木:私の実感では、家庭の方が、施設より多いかもしれないですね。在宅では、排泄介助を家族だけで行っている割合が約50%、事業者と介護家族、事業者だけもそれぞれ20数%くらいというデータ(※)があるのですが、つまり、排泄ケアは、家族のみで担っている家庭がとても多いんです。その他のケアは支援を受けても排泄のことは家族がいる限り家族がやる。食事や入浴と違って、24時間起こることですし、夜間もありますから、どうしても家族に頼らざるを得ないんですね。なかなか外部からの風が吹かないので、適切な排泄ケア方法が浸透しない問題があると思います。
※平成19年国民生活基礎調査の概況「介護者の組合せの状況」
――デリケートなことなので、なかなか困りごとが顕在化しづらいですよね。どのようなアプローチをしたら適切なケアにつながるとお考えですか?
八木:やはり、行政主導で、おむつの支給や使い方の指導などあればいいのにと思いますね。私は、かなりマニアックな考えですが。
イギリスにはNHS(国民保健サービス、National Health Service)という 制度があり、失禁に対するケアサービスの一環として、必要に応じて尿とりパッドの提供制度があります。コンチネンス(排尿・排便管理)の専門看護師らが評価を行い、適切な製品を支給される仕組みがありまです。治療を最優先とし、それでも必要な場合に製品が提供されます。
医療・介護職の教育の中で、まず失禁の治療を優先し、その上で適切なおむつ選定を学ぶ内容を充実させるべきだと思います。
――在宅で、例えば高齢の親御さんのおむつを選ぶ場合、その選び方もわからない人は多いという印象です。
八木:紙おむつは、入院をきっかけに着け始める場合が多いんです。赤ちゃんだったら、親が自分たちで選んだおむつでスタートを切れますが、病院選定のおむつが最初になってしまうのですね。ただ、病院と在宅では 必要なおむつのタイプも変わってきます。赤ちゃんなら妊娠中の準備期間に勉強も用意もできますが、介護はもう突然ですので、おむつを選ぶゆとりはないですよね.
失禁の原因を医療機関に相談、治療することでおむつの使用量減らす
――介護を受ける人が着けているおむつが適切であるかどうか、 確認する方法や基準がわかりにくい面もありそうですね。
八木:おむつは毎日使うものなので、コストを重視するのは当たり前です。そのコストを削減するためには、不要なおむつを使わないということ、そして、かかりつけ医にちゃんと相談して、尿失禁、便失禁の原因を探り、治療できるものは治療していくことが大切です。 失禁が改善すれば、おむつの使用量を減らせたり、場合によっては使わなくて済むようになることもあるんです。
――治らないと諦めるのではなく、原因となる疾病そのものを治すという考え方ですね。
八木:そうです。イギリスのNHSの研究でも、適切な失禁治療を行うことで、尿路感染症や褥瘡などの合併症が減り、入院が減少することで、結果的に医療費全体のコストが抑えられることが示されています。おむつの価格は、メーカー側が努力しても、なかなか安くはできない。だからこそ、治療を優先する考え方を基本に、医療・介護の現場で適切な排泄ケアができる制度を整えることが大切だと考えています。
――まず、失禁を治そうという考え方は、目から鱗です。加齢が原因でも治すということは目標にするべきでしょうか。
八木:そうですね。確かに加齢に伴う変化はありますが、失禁は老化の必然ではなく、治療や改善が期待できる症状なんです。 例えば、咳やくしゃみでちょろっと漏れてしまう腹圧性尿失禁なら、筋肉を鍛えることで改善できる可能性があります。まずは、医療機関とつながって、失禁の原因を突き止めることが大事ですね。過活動膀胱の人は、薬で急な尿意が少し良くなって、トイレまで我慢できるようになることもあります。もちろん、おむつを使用することで活動範囲が広がることもありますので、おむつを使用しない方がいいという話では全くないですが。
おむつの正しい使い方は、おむつメーカーのサイトで発信されている
――在宅で、おむつを使用する場合のアドバイスをお願いします。
八木:おむつを使用するときは、まずは、メーカーのサイトをよく見てください。おむつを赤ちゃんのおむつのような感覚で使ってしまいがちなんです。それで適切ではない使い方になってしまっていると思います。おむつとパットの合わせ方など重要なことは、やっぱりおむつメーカーが発信しています。
そして、医療・介護職にしっかりと相談してほしいです。やはり、いろんな人に頼って、声に出して困りごとを伝えることが大事だと思います。
取材・文/介護ポストセブン編集部