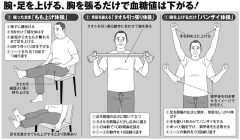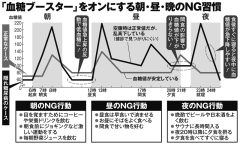《「脳に栄養を」でチョコはNG?》血糖値の乱高下が引き起こす認知症リスク 予防につながる「脂質起動」について医師が解説
私たちはゆるやかに糖質を控え、脂質やたんぱく質をしっかりと摂取することをお勧めしていますが、これよりもさらに糖質を控え、糖質の摂取量を1日50g以下までに制限し、さらに脂質をたくさん食べるという食事法があります。これをケトン体産生食とかケトジェニック・ダイエットと言います。
多量に摂取した脂質と、より糖質を控えることによって脂肪から分解された脂質(脂肪酸)は、全身に運ばれます。その際、一部が肝臓に到達しますが、肝臓に到達したアブラが多いと、肝臓はアブラをケトン体につくり変えます。ケトン体は水に溶けるため、血流に乗って脳を含めた肝臓以外のすべての臓器で使われます。
ケトン体産生食は、このケトン体を肝臓から出させることを目的にした食事法で、もともと、子どものてんかんという病気(一部の脳細胞の異常な興奮が原因と考えられています)の治療法として知られていました。
ケトン体はブドウ糖に替わって脳細胞のエネルギー源となるのですが、脳細胞の興奮状態を鎮静化する作用もあるのです。
このケトン体産生食が脳細胞の健康状態を改善するならば、ほかの脳神経疾患にも有効性があるのではないかという仮説があり、最近では(認知症は先述したように当然対象となりますが)パーキンソン病のような脳の変性疾患に対する有効性も期待されています。ケトン体産生食(言ってみれば、超脂質食)は、脳細胞にやさしいのです。
ただ、ケトン体産生食では、糖質量を1日50g以下に抑えるため、タマネギやニンジンのような糖質を多く含む野菜ですら食べられなくなります。中には野菜は完全に排除してしまい、ミート(肉)、エッグ(卵)、チーズだけの「MEC食」を推奨する医師もいます。
ここまでくると糖質制限食ではなく食物繊維も排除した炭水化物制限食となり、つらいだけでなく、ビタミン、ミネラルなども不足する恐れがあります。
実際、てんかんに対するケトン体産生食について、国際的な研究グループが出している勧告では、ビタミンやミネラルなどのサプリメントを同時に摂取することを推奨しているくらいです[*Epilepsia 2009; 50: 304-317]。
もちろん、必要な方にはケトン体産生食を提供すべきですし、ケトン体産生食においても食の楽しみが享受できるよう、医療従事者は最善の努力をする必要はあります。
ただ、てんかんの治療食としても糖質の制限をゆるめた修正版を推奨する先生もいます。ゆるやかであっても、血糖変動が抑制されているだけで、てんかんの治療になる(脳細胞の保護効果を持つ)可能性はあるのです。
一般の方は、超脂質食(ケトン体産生食)とまではいかずとも、まずはゆるやかに糖質摂取を制限し、糖質疲労を防ぎ、脂質起動を起こすだけでよいでしょう。