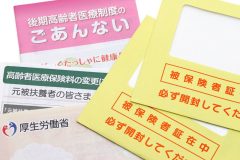「特別養護老人ホームは貯金があると入所できない?」実例相談をもとに特養の入所条件についてFPが解説
80代後半の母親の施設入所を検討しているご夫婦から相談を受けたファイナンシャルプランナーで行政書士の河村修一さん。「貯金が数千万円あるが、特別養護老人ホーム(以下特養)に入所できるのか?」というものだ。相談事例をもとに、特養の入所条件などについて解説いただいた。
相談事例「母親(80代後半)は預貯金が数千万円あるので特養は入れない?」
都内にお住まいのご夫婦から親を施設に入所させたいというご相談がありました。
要介護5の母親を在宅介護しているが、そろそろ限界とのこと。お話を伺ってみると、お母さまの預貯金が数千万円あるので、有料老人ホームを検討しているとのことでした。
お母様が今後どのくらい生きるかはわかりませんが、仮にいま検討している有料老人ホームに入居した場合、一時金など含めて5年で約2,000万円は必要になります。
また、100才まで有料老人ホームに入居した場合、預貯金はマイナスになり、年金生活の息子さん夫婦にとっては今後、支援は困難です。
そこで、今より安い郊外の有料老人ホームへの入居か、特別養護老人ホーム(特養)への入所をおすすめしました。
すると、ご主人様から「預貯金がある程度あるので特養には入所できないのではないでしょうか?」と聞かれました。
公的な施設の「特養」は、入所基準の要件に預貯金や収入、資産の有無は関係ありません。お母さまの介護については、奥様に任せっきりだったため、勘違いをされていたようです。
改めて特養の特徴や入所基準などを確認してみましょう。
特別養護老人ホームとは
特養とは、介護保険サービスを利用できる居宅型の施設です。寝たきりや認知症により生活全般に介護が必要な方で自宅での介護が困難な方が対象となり、原則、要介護3以上が入所の条件となっています。
※参考/厚生労働省 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group14.html
特養は、民間が運営する有料老人ホームなどに比べると一般的には低料金で利用できます。その一方で、待機者も多いため、地域によってはすぐに希望通りに入所できるとは限りません。
特養の利用者の費用負担額の目安は、毎月約5万~約20万円が相場となっています。内訳は、「介護サービス費用の1割~3割」に加え、「食費」「居住費」「日常生活費」を加えた金額になります。
介護サービス費用や居住費は、要介護度、居室のタイプなどによって異なります。施設と利用者の間の契約により基準額が定められていますが、たとえば多床室とユニット型個室では以下のように費用の負担額が変わります。
また、これらの費用は、本人や世帯を一緒にする人などの所得など条件によって軽減制度などもあります。
施設サービス費の1割|多床室:約25,200円 ユニット型個室:約27,900円
居住費|多床室:約25,650円 ユニット型個室:約60,180円
食費|多床室:約43,350円 ユニット型個室:約43,350円
日常生活費|多床室:約10,000円 ユニット型個室:約10,000円
合計|多床室:約104,200円 ユニット型個室:約141,430円
※参照/厚生労働省 サービスにかかる利用料
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
特養の入所条件【まとめ】
前述のご相談者様は、特養の入所条件に「預貯金」などが関係すると思い込んでいらっしゃいましたが、特養への入所には、所得や資産についての要件はありません。
特養の仕組みをご説明したところ、ご夫婦は母親の施設入所について、まずは特養に申し込みをするとともに、郊外の有料老人ホームも候補として検討していくことになりました。
なお、特養は原則要介護3以上でなければ入所できません。厚生労働省によると、毎月の費用は、要介護5でユニット型個室に入所した場合(介護サービス費の自己負担は1割)、約14万円強となっています。
特養への入所には預貯金の要件はありませんが、低所得者の場合には、施設利用が困難にならないように所得や資産によって「食費・居住費」の自己負担が軽減される制度があります。この制度を利用する場合には、預貯金や収入等の要件があるので注意が必要です。
→介護施設の食費が6万円も安くなるのはどんな人?|知らないと損する介護保険の話
介護については、なるべく多くの情報を収集することが大切です。制度を知らないと軽減制度が受けられず、損をしてしまうこともあります。詳しくは、お住まいの自治体や地域包括支援センター等に積極的に問い合わせてみましょう。
※記事中では、相談実例をもとに一部設定を変更しています。
執筆
河村修一さん/ファイナンシャルプランナー・行政書士
CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、認知症サポーター。兵庫県立神戸商科大学卒業後、複数の保険会社に勤務。親の遠距離介護の経験をいかし、2011年に介護者専門の事務所を設立。2018年東京・杉並区に「カワムラ行政書士事務所」を開業し、介護から相続手続きまでワンストップで対応。多くのメディアや講演会などで活躍する。https://www.kawamura-fp.com/