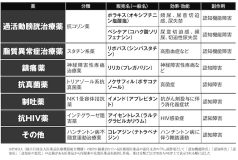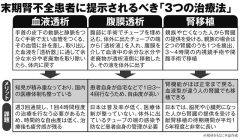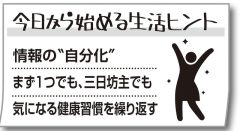「もの忘れ」「日時や場所の間違い」は薬の副作用が原因かもしれない | 認知機能障害につながる治療薬17種類<専門家監修>
病気を治す薬の副作用に「認知症」や「認知機能障害」がある場合、長期服用すると認知症の発症を早める一因になるという。加齢ではない薬の副作用による発症リスクの危険性を専門医が指摘。国内で処方されている薬の添付文書を徹底調査して判明した、飲み続けると認知症になる可能性がある薬とは。
教えてくれた人
長澤育弘さん/薬剤師、谷本哲也さん/ナビタスクリニック川崎院長・PMDA(独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」)審査専門員、眞鍋雄太さん/認知症専門医・指導医・神奈川歯科大学教授
治療薬の副作用で高まる認知症の発症リスク
厚生労働省の統計(2022年)によると、日本の認知症患者は443万人。2050年には586万人に増えると予想されている。今後は医療分野での認知症対策がますます重要になる。
そうしたなか、近年注目を集めているのが「薬」と「認知症」の関係だ。 近年の研究で認知障害や認知機能障害の副作用を持つ薬を長期間服用すると、認知症の発症リスクが高まるケースがあることがわかってきたという。
見逃せないのは、認知症の治療薬の副作用に、「認知症の悪化」が挙げられていることだ。
薬剤師の長澤育弘さんが言う。
「認知症薬のガランタミン臭化水素酸塩は、『もの忘れ』『問題解決能力の低下』『時間や場所の見当がつかない』など軽度から中等度のアルツハイマー型認知症の症状を遅らせる薬です。神経伝達物質アセチルコリンを増やす作用がありますが、これが増えすぎて脳内の神経細胞に負担をかけ、かえって症状の悪化という副作用を引き起こすこともあると考えられます」
飲み続けると認知症リスクがある薬17
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)のHPに掲載されている医療用医薬品の添付文書のうち、副作用として「認知機能障害」「認知障害」「認知症」「認知症の悪化」の記載がある医薬品から内服薬の先発医薬品を抽出し作成。薬は分類ごとにPMDAのHP上で表示される順に記した。
※薬/分類/販売名(一般名)/効果・効能/副作用
【1】抗がん剤/分子標的薬/スーテント(スニチニブリンゴ酸塩)/切除不能または転移性の腎細胞がんなど/認知障害
【2】抗がん剤/分子標的薬/オータイロ(レポトレクチニブ)/切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん/認知障害
【3】抗がん剤/分子標的薬/ローブレナ(ロルラチニブ)/切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん/認知障害
【4】抗がん剤/PARP阻害薬/ターゼナ(タラゾパリブトシル酸塩)/前立腺がんなど/認知障害
【5】抗がん剤/PARP阻害薬/ゼジューラ(ニラパリブトシル酸塩水和物)/卵巣がん/認知障害
【6】抗がん剤/抗アンドロゲン薬/イクスタンジ(エンザルタミド)/前立腺がん/認知障害
【7】抗がん剤/その他/タズベリク(タゼメトスタット臭化水素酸塩)/リンパ腫/認知障害
【8】抗がん剤/その他/オペプリム(ミトタン)/副腎がんなど/認知症
【9】抗がん剤/その他/ヴァイトラックビ(ラロトレクチニブ硫酸塩)/進行・再発の固形がん/認知障害
【10】抗がん剤/分子標的薬/ロズリートレク(エヌトレクチニブ)/切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんなど/認知障害
【11】抗精神病薬/ドパミンD2受容体部分作動薬/エビリファイ(アリピプラゾール)/統合失調症など/認知症
【12】抗てんかん薬/抗てんかん薬/トピナ(トピラマート)/てんかん患者の部分発作/認知障害
【13】抗てんかん薬/抗てんかん薬/ビムパット(ラコサミド)/てんかん患者の部分発作/認知障害
【14】認知症治療薬/コリンエステラーゼ阻害薬/レミニール(ガランタミン臭化水素酸塩)/アルツハイマー型認知症/アルツハイマー型認知症の悪化
【15】パーキンソン病治療薬/レボドパ製剤/スタレボ(レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン)/パーキンソン病/認知症
【16】パーキンソン病治療薬/レボドパ作用増強薬/トレリーフ(ゾニサミド)/パーキンソン病など/認知症の悪化
【17】遅発性ジスキネジア治療薬/VMAT2阻害薬/ジスバル(バルベナジントシル酸塩)/遅発性ジスキネジア/認知障害
パーキンソン病治療薬や抗がん剤にも注意
パーキンソン病治療薬でも、レボドパ製剤に認知症、レボドパ作用増強薬に認知症の悪化が副作用として明記されている。
いずれも脳内ホルモンの一種であるドーパミンを増やし、パーキンソン病特有の症状である手足の震えや筋肉などの強張りを改善する働きがある。
「しかし、これらの服用によりドーパミンが増えすぎると『錯乱』や『幻覚』などの副作用を引き起こすとされており、その延長線上に認知障害や認知症などの副作用を引き起こす可能性が考えられます」(長澤さん)
抗がん剤にも、副作用で認知症や認知障害が挙げられている薬がある。
「抗がん剤治療では記憶力や思考力、集中力など認知機能が一時的に低下する状態を指す『ケモブレイン』という言葉があります。抗がん剤はがん細胞だけでなく正常な細胞にもダメージを与えるため、脳の機能にダメージがあってもおかしくありません」(ナビタスクリニック川崎・院長の谷本哲也さん)
筑波大学大学院の研究(2009年)でも、抗がん剤の長期的な服用により高度の白質脳症が発症し、後遺症として認知症が発症するリスクがあると結論づけている。
谷本さんが言う。
「認知症は発症するのが高齢者というだけで、病気の始まりはもっと以前。アルツハイマー型認知症は40代から進行します。そして、薬は副作用として認知症の進行スピードを加速させかねない要素になり得るのです」
今年3月には慶應大と米ワシントン大の研究グループが「日本人の死因第1位は認知症である」との研究結果も報告した。
日本人の死因は2015年から「アルツハイマー病や他の認知症」がトップを占め、2021年の死亡数は「10万人あたり約135人」と世界最多であることがわかったというのだ。
「この研究では、認知症の進行が原因とみられる『誤嚥性肺炎』なども認知症による死亡としています。実際、食道に入るべき食物が肺に入って誤嚥性肺炎を発症し亡くなる認知症患者は多くいます。認知症により咀嚼機能が低下し、誤嚥の原因になっているというわけです」(認知症専門医・指導医の眞鍋雄太さん)
医学の進歩や健康意識の高まりにより、死因に占める脳卒中などの割合が減った反面、認知機能の低下がもたらす心身への様々な弊害が命に関わる病気を呼び寄せ、認知症が「死」の遠因となっている。
認知症予防の観点からも、常用する薬を改めて確認したい。
※週刊ポスト2025年5月9・16日号
●《新しい薬が続々登場》認知症は「薬」で治せるのか? 認知症専門医が明かす認知症治療の“いま”
●ラジオ体操で認知症のリスクが18%低下する可能性 研究者が語る効能と、誰でもできる実践のポイント
●飲み続けると認知機能障害につながる「過活動膀胱の抗コリン薬」「脂質異常症のスタチン系薬」「抗真菌薬のトリアゾール系抗真菌薬」など治療薬8種類<専門家監修>