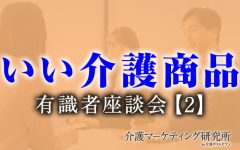《新しい薬が続々登場》認知症は「薬」で治せるのか? 認知症専門医が明かす認知症治療の“いま”
認知症といえば「アルツハイマー型」が代表的だが、実際には認知症の原因となる脳の障害を起こす病気は70以上もあることがわかっている。そして「アルツハイマー型」に加えて「血管性」「レビー小体型」「前頭側頭型」は4大認知症と言われている。そんな認知症を薬で治療することはできるのだろうか。
「恐れる」認知症から、「備える」認知症へと変わる「新しい認知症観」について現場を知り尽くす専門医が解説した『早合点認知症』(サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。
教えてくれた人:内田直樹さん
認知症専門医。医療法人すずらん会たろうクリニック院長、精神科医、医学博士。1978年長崎県南島原市生まれ。2003年琉球大学医学部医学科卒業。2010年より福岡大学医学部精神医学教室講師。福岡大学病院で医局長、外来医長を務めたのち、2015年より現職。福岡市を認知症フレンドリーなまちとする取り組みも行っている。日本老年精神医学会専門医・指導医。日本在宅医療連合学会専門医・指導医。編著に『認知症プライマリケアまるごとガイド』(中央法規)がある。
* * *
症状を改善しても、認知症の進行抑制はできない「抗認知症薬」
「認知症の薬での治療」などと読むと、認知症を治せる薬があるのかと、早合点されてしまうかもしれないので、最初に、それは違うとお断りして解説を始めましょう。
抗認知症薬は大別して「コリンエステラーゼ阻害薬*」と「NMDA受容体拮抗薬**」があり、医師が処方する抗認知症薬は現在、4剤あります。
アリセプト(ドネペジル *)
レミニール(ガランタミン *)
イクセロンパッチ(リバスチグミン *)
メマリー(メマンチン**)
これら4つは、どれもアルツハイマー型認知症の治療薬ですが、このうちアリセプト(ドネペジル)だけはレビー小体型認知症にも適用があります。
これらの薬の添付文書には効能として「認知症症状の進行抑制」と書いてあります。使用上の注意の項には(約すと)「認知症そのものの進行を抑える確認はされていないよ」「効果が認められなかったら、漫然と処方し続けちゃダメだよ」というようなことも書いてあります。
つまり、認知症の治療薬というのはやや語弊があって、「認知症症状の治療薬」なのですね。
どういうことかというと、これらの薬は、アルツハイマー型認知症の経過で、脳に起こる病変自体には一切効能がなく、脳の病変の過程で減ったアセチルコリンを増やしたり、NMDA受容体に作用したりする効果がある、ということ。薬の作用のメカニズムから言っても、認知症そのものの進行を抑制するものではないのです。
認知機能障害の変化をいくらか改善する可能性は否定できない。とはいえ臨床的に意味があると言えるほどの効果が必ず出るとは言えず、効果を判定するのも難しく、高齢の人の生活に影響大の副作用がいくつもあり、せん妄のリスクを上げる可能性もあり……と検討すると、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の人すべてに何らかの処方を、とは考えにくいものです。
そもそも、アルツハイマー型認知症(またはレビー小体型認知症)だと病型をきっぱり診断できなければ使用を検討する必要はないです。
そして、フランスでは日本と同じ4剤が保険適用で処方されていましたが、作用と副作用のバランスが悪いことなどを理由に2018年から保険適用外になっています。