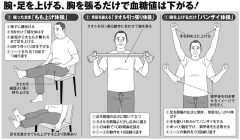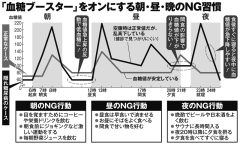糖尿病の治療薬で「低血糖」「脱水」「肝機能障害」になる危険性も<重大副作用&危ない薬の飲み合わせリスト>
処方数が多い糖尿病薬(内服薬)の効果と主な重大副作用、併用に注意すべき主な薬を一覧にまとめた。
厚労省の「第9回NDBオープンデータ内服 外来(院外)」(2022年4月〜2023年3月)、日本糖尿病学会の「2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム」、各分類の代表的な薬の添付文書、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「副作用が疑われる症例報告に関する情報」、「日経メディカル処方薬事典」、「治療薬ハンドブック」などをもとに本誌作成。
【1】ビグアナイド薬(血糖降下作用:高/低血糖リスク:低)
<一般名>
メトホルミン塩酸塩
<効果>
肝臓での糖の産生を抑えるなど、複数の作用によって血糖値を改善
<主な重大副作用>
乳酸アシドーシス・低血糖・肝機能障害・横紋筋融解症
<死亡例>
60代女性がメトホルミンを飲んで「乳酸アシドーシスを発症」のちに死亡
<併用注意の飲み薬と症状1>
・他の糖尿病治療薬
・解熱鎮痛剤のサリチル酸剤(アスピリンなど)
・不整脈や高血圧などで使われるβ遮断薬(プロプラノロールなど)
→低血糖が起こることがある
<併用注意の飲み薬と症状2>
高血圧糖尿病などで使われる利尿作業のある薬(利尿薬、SGLT2阻害薬など)
→脱水により乳酸アシドーシスを起こすことがある
【2】DPP-4阻害薬(血糖降下作用:中/低血糖リスク:低)
<一般名>
シタグリプチンリン酸塩水和物、リナグリプチン、ビルダグリプチンなど
<効果>
体内でインスリン分泌を促す物質の作用を強め、血糖値を下げる
<主な重大副作用>
低血糖・肝機能障害・急性膵炎・間質性肺炎・腸閉塞・類天疱瘡
<死亡例>
40代男性がビルダグリプチンを飲んで「劇症肝炎を発症」のちに死亡
<併用注意の飲み薬と症状1>
・他の糖尿病治療薬
→低血糖が起こる恐れがある
<併用注意の飲み薬と症状2>
・不整脈や高血圧などで使われるβ遮断薬
・解熱鎮痛薬のサリチル酸剤(アスピリンなど)
→さらに血糖が低下する可能性がある
<併用注意の飲み薬と症状3>
・血糖降下作用を減弱する薬(アドレナリン、ステロイドなど)
→血糖が上昇し、コントロール不能になる恐れがある
【3】SGLT2阻害薬(血糖降下作用:中/低血糖リスク:低)
<一般名>
エンバグリフロジン、ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物など
<効果>
尿としての糖排泄を増やすことで、血液中の糖を減らす
<主な重大副作用>
低血糖・脱水・ケトアシドーシス・腎盂腎炎・敗血症
<死亡例>
70代男性がエンバグリフロジンを飲んで脱水。「小脳梗塞を発症」のちに死亡
<併用注意の飲み薬と症状1>
・他の糖尿病治療薬
・不整脈や高血圧などで使われるβ遮断薬
→低血糖が起こる恐れがある
<併用注意の飲み薬と症状2>
・解熱鎮痛薬のサリチル酸剤(アスピリンなど)
→血糖降下作用が増強される恐れがある
<併用注意の飲み薬と症状3>
・高血圧や心不全などで使われる利尿薬(サイアザイド系利尿薬、ループ利尿薬)
→利尿作用が増強される恐れがある
【4】α-グルコシダーゼ阻害薬(血糖降下作用:食後高血糖改善/低血糖リスク:低)
<一般名>
ミグリトール
<効果>
腸での糖の吸収を遅らせて食後の急激な血糖値の上昇を抑える
<主な重大副作用>
低血糖・腸閉塞・肝機能障害
<死亡例>
60代男性がミグリトールを飲んで「薬物性肝障害を発症」のちに死亡
<併用注意の飲み薬と症状1>
・他の糖尿病治療薬
→低血糖が起こる恐れがある
<併用注意の飲み薬と症状2>
・不整脈や高血圧などで使われるβ遮断薬(プロプラノロールなど)
・解熱鎮痛薬のサリチル酸剤(アスピリンなど)
→血糖降下作用が増強される
<併用注意の飲み薬と症状3>
・心不全用薬のジゴキシン
→ジゴキシンの血中濃度が低下することがある
【5】グリニド系薬(血糖降下作用:食後高血糖改善/低血糖リスク:中)
<一般名>
レパグリニド
<効果>
服用後にすばやくインスリンを分泌させて食後の血糖値を改善
<主な重大副作用>
低血糖・肝機能障害・心筋梗塞
<死亡例>
50代男性がレパグリニドを飲んで「低血糖を発症」のちに死亡
<併用注意の飲み薬と症状>
・他の糖尿病治療薬
・不整脈や高血圧などで使われるβ遮断薬(プロプラノロールなど)
・解熱鎮痛薬のサリチル酸剤(アスピリンなど)
→血糖降下作用が増強されることがある
処方数が多い治療薬でも“万能”ではない
例えば、最も処方数が多い「ビグアナイド薬」は、他の治療薬よりも低血糖などの副作用が起きにくく安全とされるが、“万能”ではない。
「腎機能が低下した患者への投与は注意が必要で、重度の腎機能障害を持つ患者への処方は厳禁とされています。ビグアナイド薬は肝臓の糖産生を抑えることで血糖値を下げますが、肝臓の糖産生で消費される血液中の乳酸濃度が上昇し体内に酸が過剰に発生する『乳酸アシドーシス』を稀に発症することがあるからです」(竹村さん)
その症状は悪心、嘔吐、腹痛、下痢などの胃腸症状や倦怠感に始まり、過呼吸や脱水、昏睡へと進行し、重篤化すれば死に至るケースもあるという。
同じく処方数上位の「DPP-4阻害薬」は比較的新しい薬だが、「一部の製剤について心不全リスクが示唆されているほか、副作用として皮膚障害や重度アレルギーを起こした例もあるので要注意」(長澤さん)という。
心血管疾患や慢性腎臓病、心不全のリスクを高めず服用できる糖尿病薬として、近年は「SGLT2阻害薬」が注目されている。先述した学会の指針でも、それらの持病がある患者には処方が推奨されているが、副作用がないわけではない。
「糖を尿として排泄させる働きがあり、その糖を餌に細菌が繁殖し、膀胱炎を発症するケースがあります。細菌が膀胱からさかのぼって腎盂や腎臓にまで感染すると、重大な副作用の『腎盂腎炎』、細菌が血液中に入り全身に広がれば『敗血症』を引き起こす可能性もあります」(竹村さん)
腸での糖吸収を遅らせて血糖値の上昇を抑える「α-グルコシダーゼ阻害薬」についても効果に応じた副作用がある。
「大量のガスが腸管内で産生されるため、腹部の膨満感など消化器症状が強く出やすい人は要注意です。副作用で『腸閉塞』に至ったケースも報告されています」(竹村さん)