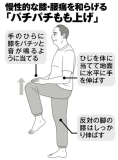90%以上が認知症へのイメージ変化!小・中・高校生を対象に「認知症」について出前授業を実施<調査レポート>
少子高齢化が進むにつれ、深刻になる高齢者の認知症増加。認知症当事者との共存社会を目指すためにも、一人ひとりが認知症への正しい知識を持つことが大事だが、まだまだ理解が進んでいないのが現状だ。そんな中、メディカル・ケア・サービスは小・中・高校生を対象に認知症教育の出前授業を実施。授業前後に行われたアンケート調査の結果と合わせて、その様子をレポートする。
一人でも多くの人に「認知症」を正しく知ってもらうために
急速な少子高齢化に伴い、認知症の増加が問題となっている現代日本。日本の総人口は、前年と比べ59万人減少している一方、65才以上の高齢者の人口は3,625万人で過去最多となり、総人口に占める割合も29.3%と過去最高となった(2024年9月15日現在推計・総務省)。
また、2025年はいわゆる「団塊の世代」が75才以上の後期高齢者になると共に、認知症とその予備軍の人が1,000万人を超えるとされており、誰でも自分や身近な人が認知症になる可能性が充分にある。そんな中、2024年1月には共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施工され、一人ひとりが認知症に対して正しい知識を持ち、誰もが暮らしやすい社会づくりに向けて行動していくことが必要とされている。
上記のような社会状況の中、学研ホールディングスのグループ会社で、「認知症を取り巻く、あらゆる社会環境を変革する」ことを企業ミッションとして掲げるメディカル・ケア・サービスは、小・中・高校生をはじめとした子供たちを対象に無償で「認知症教育の出前授業」を実施。2022年12月から2024年12月にかけて授業を実施した子供たちを対象に、授業前後にそれぞれ認知症や今後の自身の行動に対するアンケートを行った。
授業前は6%が「認知症について知らない」と回答
まず授業前のアンケートで、「認知症を知っているか」という質問に対し、「家族など身近な人が認知症」と回答したのは約12%。65才以上の人がいる三世代世帯は、年々減少し核家族化が進んでいるとはいえ、祖父母などを含め認知症当事者が身近にいる子供も一定数いることが明らかになった。また、約83%は、「身近にはいないが認知症を知っていると回答し、多くの子供たちが「認知症」という言葉を耳にしたことがある一方で、6%が「認知症を知らない」と回答し、認知症自体の認識がない子供もいることが浮き彫りとなった。
しかし、授業後のアンケートでは、「認知症を理解できたか」という質問に、86%が「理解できた」、14%が「少し理解できた」と回答し、合わせて100%の子供たちが認知症に対し理解を深めることができたようだ。
92%が授業後に「認知症が良いイメージに変わった」と回答
また、授業後のアンケートで「認知症や介護施設に対して良いイメージに変わったか」という質問には、92%が「変わった」と回答する結果に。
続けて「授業の中で特にためになった内容は」と尋ねると、「認知症状」と「認知症の人への声掛けや関わり方」という回答がそれぞれ約40%で最も多い結果となった。子供たちの中にも身近に認知症当事者がおり、授業後の感想では「私の祖母が最近認知症になってしまい、どう接したらいいかわからなかったけれど関わり方が知れた(小学6年生)」という回答も見られた。以上のことから認知症への正しい知識の普及が必要とされており、出前授業はその一助となっていることがわかる。
「介護職への興味関心」が授業後は「2倍」に
次に、授業前後でそれぞれ「介護職に興味があるか」を尋ねた。すると授業前は「興味がある」「少し興味がある」が約24%。対して、「あまり興味がない」「興味がない」という回答は約56%で半数を超えていた。
しかし授業後は、「興味がある」「少し興味がある」との回答が約50%と、授業前の2倍となる結果に。「あまり興味がない」「興味がない」も、約27%と半減した。
また、「そもそも介護福祉士についてあまり知らなかった。ニュースや新聞などで知られていなかったり、感謝されたりする仕事ではないかもしれないけれど、かげで支えていることに感動した(中学2年生)」「おじいちゃんおばあちゃんのお世話をするだけだと思っていたが、お世話をしたり、関わったりする中で、認知症の緩和などをすることができるし、素敵な仕事だと思った(中学2年生)」など、そもそも介護士や介護福祉士についてどのような職業かあまり知らなかったという意見も多く挙げられた。介護職は、特に子供たちの身近にある職業ではないことから、一つの職業としての関心や正しい知識に繋げることができる出前授業の機会は大事だと言えるだろう。
授業後、「困っている人への行動ができる」が2倍に
続いて、授業前後で「認知症の人を街で見かけたら、何か行動できるか」という質問を行った。授業前は、「やろうと思っても勇気が出ない」「人見知りなので声がなかなかかけられない」などの意見が多く、「したことがある・できる」という回答は約25%に留まっていたが、授業後には約50%となった。
「認知症は辛いということは想像しただけでわかるし、認知症でも誰もが住みやすい日本にしたいから道に迷っていたり、困っている人を見つけたら、一緒に警察に行って手助けをしてもらうなど、できる限りは協力したいからです(小学5年生)」「認知症の方も好きでなっているものではないので、相手が認知症で大変な分、私たちが上手にフォローしないといけないので困っていたら助けます(小学6年生)」など、勇気を出して行動してみようとする意見が多く見られた。
今までより多く祖父母と関わりたい<生徒の感想を紹介>
・これから、両親や祖父・祖母との(年を取ったときの)関わり方が少しわかったのでとてもためになった。
・介護については、簡単なイメージを持っていたが、コロナ禍に介護施設の人たちが頑張ってくれたおかげで今の日本があることを知り、すごく大きな仕事なのだと思った。また、世間では目立たない位置の介護福祉の大切さ・大変さもわかった。日本の介護は量より質を大切にすることで、人々の健康を守っていると思った。
・普段あまり聞かない仕事だったからとても興味深く楽しかった。人の気持ちを読み取ったり、誰かを元気に幸せにしたりするのは、友達の気持ちを読み取るのも大変なのに、それを日常的に行っている介護福祉士さんはすごいと思った。寿司屋のおじいちゃんの動画をみて、認知症になってしまってあんなに元気がなかった人でも、介護福祉士の力やその人の努力で、元気で幸せになれるのだと感動した。私は、周りの人がずっと笑顔で幸せにいてほしいと常日頃から思って行動しているので、介護福祉士はすごく魅力的な仕事に感じた。今度自分でも介護福祉士について調べてみようかなと思った。
・今回の講話を聞くまで、あまり認知症が身近なものだと捉えることができなかったが、誰にでもなる可能性はあると知り、驚いた。そして、認知症は「一度発症したら悪化するだけ」という考え方から、声掛けをすることで、忘れてしまっていることに不安で、元気がなくなっていた人が元気になることがあると知った。お年寄りの方、認知症の方を介護し、幸せにするプロが介護士や介護福祉士であるとも分かり、一日だけで良い仕事なんだと感じることができた。
・私の祖父は認知症で、今までは聞き返されるのが嫌で祖父母の家には行きたくないなと避けてしまっていたが、私たちと話したり、遊んだりすることで元気に過ごすことができると分かったので、これからは今までよりも多く祖父母の家を訪れ、元気に過ごしてもらえるようにしたいと思った。
* * *
以上の感想からも、多くの子供たちが「認知症教育の出前授業」を通して認知症への理解を深め、今後の自身の行動に役立てていきたいと考えていることが明らかになった。この先の地域社会の未来を担う子供たちと共に「認知症」について考え、一人でも多くの人が「認知症」への正しい知識をつけていけば、誰もが暮らしやすい共生社会へと繋がっていくだろう。出前授業の今後の展開にも注目していきたい。
【データ】
学研ホールディングス
https://www.gakken.co.jp/ja/index.html
メディカル・ケア・サービス
https://www.mcsg.co.jp/
認知症教育の出前授業
https://www.mcsg.co.jp/features/initiatives/dementia_education/
【調査概要】
調査期間:2022年12月~2024年12月
調査会社:メディカル・ケア・サービス(自社調査)
調査対象:同社が「認知症教育の出前授業」を行った小学生~高校生
※一部大学生や専門学生等も含む
回答数:1,993名 ※質問内容により対象者、対象者数が異なる
調査方法:授業前後にてアンケートを実施 ※学校により事後のみ実施
※株式会社学研ホールディングスの発表したプレスリリース(2025年1月16日)を元に記事を作成。
図表/メディカル・ケア・サービス株式会社提供 構成・文/秋山莉菜