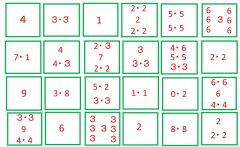命の危険にもつながる誤嚥性肺炎を防ぐ|予防法やトレーニング法【まとめ】
食物や唾液は、口腔から咽頭と食道を経て胃へ送り込まれるが、その際に誤って食道ではなく喉頭と気管に入ってしまう状態を誤嚥と呼ぶ。通常は、むせて気管から排出する反射機能が働くが、高齢になると、この機能が鈍って排出できなくなることがある。誤嚥は肺炎の原因ともなり、高齢者にとっては命の危険もある。
そんな誤嚥を予防する記事をまとめて紹介しよう。
誤嚥性肺炎を招く危ない兆候をチェック!
高齢者に多い誤嚥性肺炎。誤嚥により飲食物や唾液が肺に入ると中で細菌が繁殖し、炎症を起こして肺炎を引き起こす。肺炎は、日本人死亡原因の第3位で、75才以降の高齢者に多くみられるが、肺炎の70%以上が誤嚥に関係しているといわれ、特に、免疫力が低下していると炎症も併発しやすく危険度が増すという。
のど仏の機能低下は誤嚥を引き起こすが、それ以外にも、声を出さないことで誤嚥を引き起こしやすくなるという。“あー”と声を出して10秒以上続かない人や、声が小さくなったと言われるようになった人は、のどのトレーニングを! 「のどの筋肉の衰えチェック」や、「普段の生活で気をつけたい4つのポイント」、「簡単のどトレーニング」に関する記事はこちらから。
「のみ込み力」を鍛えるトレーニングで寿命をのばす
肺炎で亡くなる高齢者の約7割が患っているという誤嚥(ごえん)性肺炎。高齢者の場合、ムセたり、咳込むことのない誤嚥も多く、風邪のような症状が長く続き、知らず知らずのうちに誤嚥性肺炎を発症している人も多いという。「肺炎は老人の悪友」といわれるほど、実に身近に潜んでいる病気で、治療が遅れるほど回復が難しく、死に至るケースも少なくないのだ。
自覚症状はないものの、のどの衰えは40代頃から始まっている。でも、のみ込む力を鍛えれば、寿命を数年~10年延ばすことができるという。食事中にムセる、自分の唾液を誤ってのんで咳込む、錠剤がのみにくくなる、痰が絡まりやすくなるなどは、のみ込む力が低下してきたサインでもある。つまり、加齢とともに下がるのど仏を維持するために、のどの筋肉を鍛えることが長生きの秘訣になるというのだ。70代、80代からトレーニングを始めた人でも、みな数年は寿命が延びていたという例がある。早速、「のみ込む力を鍛えるトレーニング法」を始めよう!
→死を招く誤嚥性肺炎を防ぐ のみ込む力を鍛えるトレーニング法
“喉の老化”対策に効果的な「ねばり食」
喉が老化すると、寝ている間に唾液でむせたり、口が常に乾いていてネバネバしている、朝起きたときに声が出しづらい──などが起きてくる。足腰や肌の衰えとは違い、自覚できない人が多くいる喉の衰えは、40代から始まるという。高齢者では誤嚥による呼吸器の病気につながる恐れがある。
飲み込む機能の低下の他、唾液量の低下も一因。これらを解消して喉を元気にするために効果的なのが、食事に『ねばり食材』を加える「ねばり食トレ」だという。詳しい内容は、こちらの記事をチェック。
→むせたら要注意!誤嚥性肺炎を引き起こす“喉の老化”に「ねばり食トレ」で対策を
誤嚥性肺炎の予防に欠かせない「口腔ケア」
介護において、体の清潔には気を使うものの、つい後回しになりがちな口腔ケア。本来は「食事」「排泄」「体の清潔」と同じくらい重要で欠かせないケアだ。歯磨きと同時に、口腔内を清潔にし、口や顔の筋肉の機能向上訓練を行うことで、それまで口から飲食できなかった人が食べられるようなったり、表情のなかった人が笑うように、話すことのできなかった人がしゃべれるようになったりする例はたびたび起きているという。
中には、胃ろうをつけ、寝たきりだった人が、「口腔のケア」や「口腔機能訓練」を行うようになったことで、自分の口で食べ、自身の足で歩き、話すことができるようになった驚くべきケースもあるという。そのような、介護における「口腔のケア」の重要性について解説した記事は、こちらから!
→誤嚥性肺炎の原因は口腔機能の衰え!? 命を繋ぐ「口腔ケア」<第1回>
介護食に「とろみ」が重要なワケ
介護食は「とろみ」をつけて食べやすく、飲み込みやすくすることで、誤嚥を防ぐ――。介護食に欠かせないとろみだが、なぜ必要なのか? 加齢や病気によって、飲み込みのタイミングが合わなくなるとむせてしまうことがあるが、とろみをつけることで、口の中での水分や、液状の食べ物の動きを遅くする役割がある。
とろみをつける方法としては、水溶き片栗粉を入れて加熱する方法のほか、市販のとろみ調整食品を使う方法もある。実際に、とろみ調整食品を使うと食感はどうなるのか──。とろみの正しいつけ方や、とろみの濃度を実験した結果は以下をチェック。
構成/介護ポストセブン編集部