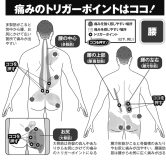平らな道でも足がもつれると感じたら。転倒しない体をつくる「1分片足立ち」体操をスポーツ科学の教授が解説
健康寿命を守るカギは“転ばない体”づくりにある。転倒は骨折を引き起こし、寝たきりや要介護状態を招く大きなリスクが。『よくつまずく 転ぶ・ふらつく 自力で克服! 名医が教える最新1分体操大全』(文響社刊)の著者であり、早稲田大学スポーツ科学学術院の金岡恒治教授(整形外科専門医)に、健脚を作る体操法を解説してもらった。
教えてくれた人
金岡恒治さん/早稲田大学スポーツ科学学術院教授・整形外科医
長く自立して歩くためには「健脚」を保つことが重要
人生100年時代、健康寿命を縮める最大の要因といわれるのが「転倒」だ。転倒は骨折を招き、要介護状態や寝たきりへとつながる危険がある。実際、日本人男性の健康寿命は平均寿命より約9年短い。長く自立して歩くためには、転ばない「健脚」を保つことが欠かせない。
そう指摘するのは、『よくつまずく 転ぶ・ふらつく 自力で克服! 名医が教える最新1分体操大全』(文響社刊)の著者で、早稲田大学スポーツ科学学術院教授の金岡恒治氏(整形外科専門医)だ。
「健脚を保つ第一歩は、日常生活で“美しい姿勢”をキープすることです。そのうえで『段差につまずく』『足がもつれる』といった日常のサインから歩く力の衰えの原因を見極め、原因別に対策を行なうことが大切です」(金岡教授)
美しい姿勢
・肩甲骨を背骨側に寄せる
・視線はまっすぐ
・あごを引く
・お腹をへこませる
平坦なところでも足がもつれる
歩行中にバランスが崩れそうになった時に転倒しないためには、脳からの指令に各筋肉が即座に反応する必要がある。しかし、加齢や運動不足などによって脳と筋肉の協調性が低下すると、状況に合わせた最適な動きをとることが難しくなると金岡教授は言う。
「例えば青信号に変わった時に足を踏み出すのがワンテンポ遅れるなど、『今までと違うな』と感じることがあったら、協調性の衰えが始まっているかもしれません」
この衰えを回復させるのが「1分片足立ち」だ。
「片足で立つと体がふらつきますが、あえて不安定な状態を繰り返し行なうことで、脳からの指令に対する筋肉の反応がよくなります。体操中の転倒が不安な方は、椅子の背に手を添えて行なうのがよいでしょう」
「1分片足立ち」のやり方
平坦なところでも足がもつれる、日常生活で思うように足が動かず、動作が遅くなったと感じ人への体操。1セット【1】~【2】を2~3回行う。1日2セット。
【1】両足を揃え、背筋を伸ばして立ち、両手を腰に置く。
【2】左足の太ももを床と平行になる高さまで持ち上げ、ひざを直角に曲げる。片足立ちの状態を1分キープ。右足も同様に行なう(ふらつく人は足が着いている側の手を椅子の背や壁にあててもよい。太ももが高く上がらない人は、足を床から少し離すだけでもよい)
転ばないために体幹力をつける「片足立ち足振り」
歩行で重心が移動しても上半身がぶれないためには「体幹安定性」の維持も肝要だ。転ばない体幹力を培うのが「片足立ち足振り」だという。
「体幹の筋力が弱ると背骨の支えが不十分になって背中が丸まり、首が前に出て腰が曲がるなど、姿勢の崩れが生じて足元の安定感が失われます。
この体操では、背骨を動かさない意識が重要です。お腹を軽くへこませ、腹筋で体幹を支えながら足を前後に振ると体幹安定性アップに効果的です」
「片足立ち足振り」のやり方
猫背、腰曲がり、首下がりなど姿勢が悪化した、急に立ち止まると足元がふらつくかたに実践して欲しい体操。1セット【1】~【3】を2回行う。1日2セット。
【1】右足を椅子の背側にして背筋を伸ばして立ち、右手で椅子の背をつかむ。口から息を吐いてお腹を軽くへこませる。
【2】左足を伸ばして前方に大きく振り上げる。
【3】そのまま後方に大きく振る。この動作を20回繰り返す。次に左右を入れ替えて同様に行なう。
取材・文/池田道大 イラスト/タナカデザイン
※週刊ポスト2025年11月7日・14日号