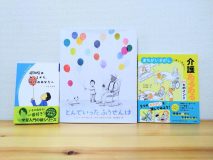障害のある母の言動にどう対応するのが正解?演劇ワークショップに参加して感じた「相手の見ている世界に入り込むこと」の意味
高次脳機能障害の母と暮らしているヤングケアラーのたろべえさんこと、高橋唯さん。母の言動に戸惑い、どう返答すべきなのか悩むこともあるという。そこで、介護や認知症ケアに演劇の手法を取り入れる注目のワークショップに参加。ヒントは見つかるだろうか?
話を聞いた人/菅原直樹さん
菅原直樹(すがわらなおき)1983年生まれ。俳優、介護福祉士。平田オリザが主宰する劇団「青年団」に所属し、介護福祉士として働きながら演劇活動を行う。2012年に岡山県に移住し、劇団「OiBokkeShi」を旗揚げ。介護×演劇をテーマに全国でワークショップを行う。徘徊演劇と名付けた代表作「よみちにひはくれない」は岡山、埼玉などで上演され、9月には台湾の国立劇場で上演されるなど注目を集めている。https://oibokkeshi.net/
執筆/たろべえ(高橋唯)さん
「たろべえ」の名で、ケアラーとしての体験をもとにブログやSNSなどで情報を発信。本名は高橋唯(高ははしごだか)。1997年、障害のある両親のもとに生まれ、家族3人暮らし。ヤングケアラーに関する講演や活動も積極的に行うほか、著書『ヤングケアラーってなんだろう』(ちくまプリマー新書)、『ヤングケアラー わたしの語り――子どもや若者が経験した家族のケア・介護』(生活書院)などで執筆。 https://ameblo.jp/tarobee1515/
「介護×演劇」ワークショップに参加
「介護と演劇は相性がいいんです。お年寄りほどいい役者はいません、介護者は俳優になってみると、案外コミュニケーションがうまくいくことが多いんです」
こう語るのは、劇団「OiBokkeshi(オイ・ボッケ・シ)」の主宰、俳優で介護福祉士の菅原直樹さんだ。2014年に岡山県で劇団を旗揚げした菅原さんは、『老い、ぼけ、死』をテーマとした芝居が文化庁の芸術新人賞を受賞するなど注目を集め、介護に演劇を取り入れる「老いと演劇」ワークショップを全国で開催している。
→認知症介護に演劇の知恵を!「老いと演劇」をテーマに取り組む俳優菅原直樹氏
高次脳機能障害の母とのコミュニケーションにおいて「何か学びがあるかもしれない」と、菅原さんのワークショップに参加してみることに。
千葉・多古町の住民ネットワーク
ワークショップの会場は、米どころとしても有名な千葉・香取郡多古町(かとりぐん・たこまち)の自然豊かな山間に建つ、障害者支援施設「ひかり学園」。多古町には、地域住民の交流を目的とした「タコ足ケアシステム」というコミュニティーがあり、様々な活動を行っている。この地に暮らすケアラーの知人を通して多古町の活動を知った筆者は、ゆるやかなつながりに魅了され、時折多古町を訪れている。
今回のワークショップを企画したのは、「ひかり学園」を運営する社会福祉法人・槇の実会に所属し、「タコ足ケアシステム」の活動を推進する在田創一さんだ。
「僕は菅原さんの大ファンなんです! ぜひ我が町にお呼びしたいと考えていたら、なんと多古町の老舗旅館の女将が菅原さんのお母様とお友達だったというご縁も(笑い)。
医療や福祉、介護の現場では演劇が役に立つということを、今日はみんなで学びましょう!」と在田さんの元気な掛け声の中、ワークショップがスタート。
演技レッスンでも活用されるゲームを体験「身体を使った遊びを」
参加していたのは、近隣住民や地元の商店街の人たち、介護・福祉関連や行政の職員など約30名。中には「タコ足ケアシステム」の活動に興味をもち、神奈川・鎌倉から訪れていた常連さんも参加していた。
まずは参加者全員で輪になり、介護現場でも実践されている「遊びリテーション」を体験。頭や肩、腕、脚など身体のパーツに番号を振り、指示役の一人が発声する番号通りにパーツに触れるというゲームを実践。頭ではわかっているのに身体がついていかないのがもどかしかった。その後は、俳優の演技力向上に用いられるという「シアターゲーム」なども体験し、みんなで身体を思いきり動かした。
「身体を使った遊びは、演劇の原点でもあります。ゲーム感覚で楽しみながら、できなくてもそれを面白がって笑う。心と体のリハビリにもなるんですよ」と、菅原さん。確かに身体と心がほぐれたのか、序盤から会場は笑いに満ちていた。
相手が見ている世界に入り込む演技の難しさ
「2人1組になって、介護者と認知症の人を演じてみましょう。介護者役は認知症の人役に食事の声かけをします。しかし、認知症の人役はまったく脈略のない返答をしてください」と菅原さん。たとえば、以下のような形だ。
介護者役「食事の時間ですよ、食堂に行きましょう」
認知症の人役「海に行きたいわ」
介護者役「海、いいですね。そしたら水着を探してきましょうか。あ〜、海の幸も食べてみたいですね」
こうした会話を繰り返し相手を肯定するという演技レッスンだ。
菅原さんによると、「相手が見ている世界に入り込めるかが、ポイント」だという。自分の都合や目の前の現実を相手に押し付けてしまうと、認知症の症状によっては混乱してしまうこともあるので、その加減が難しい。
筆者は母を含め、相手の言葉を否定しないようにしてきたつもりだったが、その人の世界に入り込むところまでには至っていなかった。相手が見ている世界の住人になりきって、その世界の中で自分の行動を考えるのは、なかなか難しかった。
認知症役の人の言葉を全否定してみると…
さらに、認知症の人の言葉を、介護者が「否定する」演技レッスンも行った。認知症役を演じた参加者は、「否定ばかりされると、相手が嘘つきに思えて、言うことを聞く気がなくなるものですね」と振り返った。
「介護者と認知症の人は見ている世界が違うだけで、どちらも悪気はないんです。相手は演技をする役者だと思って演じ続けてみると、案外コミュニケーションがうまくいくこともあるんですよ」と菅原さん。
相手の言葉にのっかり、もう一歩先へ
「認知症のかたと関わるとき、最初は演技だったとしても、うまくいけばその人の心の中にある大切なものに触れることや、感情の共鳴が起きることがあり、お互いに楽しい時間を過ごせることもあるんです。
僕の劇団の看板役者は今年99才なのですが、現在と過去の話が交錯して、現実なのか演技なのかわからなくなることがあって、とても不思議な体験なのですが、面白いと感じることもあります。
高齢のかたや認知症の人を“あしらう“のではなく、ときには俳優になって、もう一歩その先に踏み込んでいく楽しさをみんなで共有していくことができたら嬉しく思います」
参加した町内の介護職員からは「とにかくよく笑って、楽しい時間でした」「業務の中でいつも演技はしているが、演技をせずに向き合っている職員もいるし、これであっているのかなとも思っていた。今日はみんなの思いが聞けてよかった」「認知症のケアをするご家族の心の負担を軽くできるのではないかと思いました」といった感想があがった。
筆者は普段、母に話を合わせているとイライラしたり、母を騙しているような罪悪感を覚えたりすることもあったが、俳優になりきって演じることで、母とまた違った関係性を築けるかもしれない。(後編につづく)
ヤングケアラーに関する基本情報
言葉の意味や相談窓口はこちら!
■ヤングケアラーとは
日本ケアラー連盟https://youngcarerpj.jimdofree.com/による定義によると、ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている、18才未満の子どものことを指す。
■ヤングケアラーの定義
『ヤングケアラープロジェクト』(日本ケアラー連盟)では、以下のような人をヤングケアラーとしている。
・障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
・障がいや病気のきょうだいの世話や見守りをしている
・目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている
・日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている
・家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている
・障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
・障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている
■相談窓口
・こども家庭庁「ヤングケアラー相談窓口検索」
https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/consultation/
・児童相談所の無料電話:0120-189-783
https://www.mhlw.go.jp/young-carer/
・文部科学省「24時間子供SOSダイヤル」:0120-0-78310
https://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
・法務省「子供の人権110番」:0120-007-110
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
・東京都ヤングアラー相談支援等補助事業 LINEで相談ができる「けあバナ」
運営:一般社団法人ケアラーワークス
https://lin.ee/C5zlydz