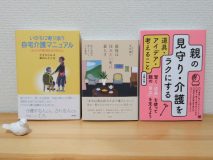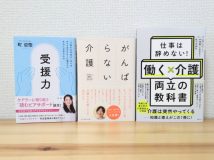書店員が選ぶ《子どもと一緒に読める介護の本》「老いは進み、忘れてしまうことの現実をあたたかく描く」名著3選
20代に母親の介護を経験した小黒悠さんは、図書館司書の資格を持ち、オンライン書店を運営している。あるとき「子どもと一緒に読める介護の本」について問い合わせがあったそう。小黒さん自身、祖母との思い出を振り返りながら、心温まる3冊をピックアップしてくれた。
教えてくれた人/小黒悠さん
元図書館司書。20代から母のケアを経験し、ケアする人を「ケアする本屋」を目指し、オンライン書店「はるから書店」を運営。ライターとしても活動中。https://harukara-reading.stores.jp/
子どもと一緒に読める「介護」の本はありますか?
こんにちは、ケアする本屋「はるから書店」の小黒です。介護に「やくだつ本」と、気持ちの「やわらぐ本」をセレクトしている、オンラインの書店です。
最近、お客さまからこんなご相談がありました。
「子どもと一緒に読める介護の本はありますか?」
どうやら夏休みに帰省した際、お子さん達が久しぶりに再会したおじいちゃん、おばあちゃんの変化に気付いたらしく、「老い」や「介護」について家族で話題になったそうなんです。
65才以上のかたがいる世帯のうち、3世代世帯はわずか6%(厚生労働省「国民生活基礎調査」2024より)。ここ数年は、コロナ禍で帰省や高齢のかたとの交流を控えていたご家庭も多かったかもしれません。子どもたちの目には「もの忘れ」や年齢による変化が、ちょっと不思議な現象に思えたのでしょう。
祖母との思い出
そういえば、私が子どもの頃はどうだったでしょうかでしょうか。同居はしていませんでしたが、母の実家に行くことの多かった私は、昔の祖母との会話を思い出しました。
「あら、A子」
孫の顔を見るなり、娘(つまり私の母)の名前を呼ぶ祖母。違ったわ、とすぐ訂正するものの、母のことを伯母たちの名前で呼ぶのは日常茶飯事(しかも四姉妹だったのでバリエーションが多い)。いわゆる天然だったのか、それともあれは老いによるものだったのか。
80代に入った頃だったでしょうか。大病もせず元気に一人暮らしをしていた祖母が、ある日、栄養失調になってしまったのです。よくよく尋ねてみると、どうやら卵かけごはんなど簡単なもので食事を済ませていたとのこと。作るのが面倒だった、という気持ちもあったようですが、それよりびっくりしたのは「作り方を忘れちゃったのよね」の一言だったのです。
「子どもと一緒に読める介護の本」をテーマに3冊の本をご紹介します。私の祖母の後日談は、そのあとに。
「老いの現実」を優しい目線で描く絵本
『とんでいったふうせんは』
ジェシー・オリベロス 文、ダナ・ウルエコッテ 絵
落合恵子 訳 絵本塾出版
一つ一つのふうせんには、その人の大切な記憶が詰まっている。おじいちゃんは「ぼく」よりもたくさんのふうせんを持っていて、「ぼく」はその思い出話を聞くことが大好き。でもおじいちゃんは最近、ふうせんを一つ一つ手放してしまう…。
少年と祖父の交流を通して、老いていくこと、忘れていくことのありのままが優しく語られている絵本です。大切な人に自分を忘れられてしまう悲しさを、少年はどのように受け止めるのでしょうか。
翻訳は、ご自身もお母さまの介護経験を持つ落合恵子さんです。
認知症当事者の言葉に勇気をもらえる
『認知症のわたしから、10代のあなたへ』
さとうみき 著 岩波書店
主に中学生に向けて、興味関心を広げることを目的として出版されているシリーズの一冊です。著者は43才で若年性アルツハイマー型認知症の診断を受けた、さとうみきさん。認知症は高齢者に限った症状ではありません
さとうさんがご自身の症状に気づかれたのは、認知症をテーマに扱ったドラマがきっかけでした。登場人物に自分と多くの共通点があり「まさか?」との思いで「もの忘れ外来」へと向かったそうです。
当事者のかたがどのように症状を感じ、何に困っているのか、さとうさん自身の気持ちの変化も綴られています
担当のドクターからの解説もあり、大人が読んでも参考になります。やわらかいタッチで描かれたイラストもあたたかく、前向きなさとうさんの姿勢に勇気をもらう読者も多いのではないでしょうか。
楽しみながら相手をいたわる方法を学べる
『まちがいさがしで楽しく学ぼう!介護あるある89のポイント』
石本 淳也 監修、永田 美樹 著 中央法規出版
自分の祖父母や周りの高齢のかたに、何かお手伝いをしたい、と思うお子さんもいるかもしれません。
こちらは介護施設などの現場の職員さん向けに書かれた書籍ですが、イラスト入り、ふりがな入り、更にまちがいさがしもあり、お子さんが読んでも楽しい内容になっています。杖を使って歩くかたをサポートするときのコツや、車椅子の押し方など、意外と知らない介護のポイントが満載です。
ヤングケアラーとしてではなく、人と人との自然なコミュニケーションの一つとして、相手をいたわる方法を知ることは大切なことだなと感じます。
祖母のその後
一緒に暮らしていたら自然と接していたであろう変化も、会うスパンが空くと、何かあってからじゃないと気がつかないんですよね。そして、なんだかとてつもない大きな変化が起きたように感じてしまうものです。
そういえば、子どもの頃は誕生日に食べていたお赤飯も、私の大好物のおいなりさんも、久しく食卓には登場していませんでした。当時高校生だった私は幼い頃ほどは祖母に会いに行っておらず、行ったとしても泊まらず日帰りで、一緒に食事をする回数は減っていました。そういえばお正月のおせち料理も品数が少なくなっていたような…。
こちらが気づかぬうちに、ゆっくりと老いは進み、いろんなことを少しずつ忘れていたのでしょう。生きていれば、それは自然なことのはずです。
幸い祖母はその後回復し「将来、何かあったときのために」と、ひとまず部屋のお掃除サービスを導入することになりました。電話をかけた母に「今日はお掃除の人が来るから部屋を片づけている」と告げ、忙しそうに電話を切ったおちゃめな祖母。サービスをお願いしたことで新たな人との関わりも生まれ、平坦になりがちな毎日に少し変化があったようです。
数年後、祖母は86歳で旅立ちました。最期は眠るように穏やかな顔をしていました。私はおいなりさんを食べると、祖母のふわふわの白い髪を思い出します。作り方を聞いておけばよかったなぁ。
■紹介した本はオンライン書店「はるから書店」で購入できます。
https://harukara-reading.stores.jp/