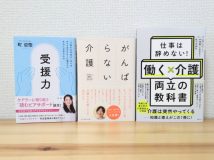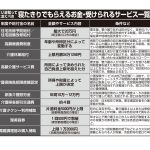4月から法改正「介護休業制度」働きながら介護をする人にどう役立つ?改正のポイントを社会福祉士が解説
介護休業についての法律が改正され、4月から施行された。働きながら介護をする人が増える中、新たな法改正によりどんなメリットがあるのか。正社員として仕事をしながら15年に渡って親の介護を続けてきた社会福祉士の渋澤和世さんに、制度の概要とポイントを解説してもらった。
この記事を執筆した専門家/渋澤和世さん
渋澤和世さん/在宅介護エキスパート協会代表。会社員として働きながら親の介護を10年以上経験し、社会福祉士、精神保健福祉士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を取得。自治体の介護サービス相談員も務め、多くのメディアで執筆。著書『入院・介護・認知症…親が倒れたら、まず読む本』(プレジデント社)、監修『親と私の老後とお金完全読本』(宝島社)などがある。
育児・介護休業法の改正で介護生活はどうなる?
2025年4月、育児・介護休業法の法改正が施行されました。正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「介護休業法」)です。
仕事と育児や介護を両立しやすくするための法律であり、改正は2025年4月、10月(10月の改正は育児のみ)と段階的に施行されます。
そもそもこの法律は、育児中の現役世代や仕事と介護を両立している“ビジネスケアラー”をサポートする目的で、2017年4月1日にできたものです。
仕事をしながら介護を続けている人が年々増える中、両立が難しくなると離職を選ぶケースも。「介護離職」は深刻な社会問題にもなっています。
現在介護中の人も、今後介護に直面するかもしれない人にとっても、制度を知っておいてほしいと思います。今回の法改正から、介護に関するものに絞ってポイントを確認していきましょう。
2025年4月の法改正のポイントは4つ
介護離職の原因は、家族の問題や介護サービスに起因すると考えがちです。しかし介護と仕事を両立するための支援制度があるのに、内容や申請の手続等を知らないために、利用が進んでいないことも介護離職の一因と考えられます。
今回の法改正では、「制度の周知」に関する項目が見直されました。企業からの情報提供を「義務化」、また、柔軟な働き方の環境整備としてテレワークの活用なども見直されています。主な改正点は、以下の4つです。
ポイント
【1】介護休暇を取りやすくするための要件緩和
→雇用期間6か月未満の人も取得できるように
【2】介護離職防止のための環境整備(義務)
→研修や相談窓口の設置、事例提供、方針周知のいずれかが必須に
【3】介護離職防止のための周知や意向の確認(義務)
→制度について早めに知らせ面談などを実施
【4】介護のためのテレワーク導入(努力義務)
→在宅勤務できる環境を整え、働き方を選べるようにする
参考/厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
介護休業法改正で働き方はどう変わる?
今回改正された内容を具体的に見ていきましょう。
【1】介護休暇を取りやすくするための要件緩和
介護休業を取得できる労働者の雇用期間の要件が緩和され、労使協定による継続雇用期間「6か月未満の除外規定」が撤廃されました。また、就業規則等の見直しも求められています。
ポイント
要件が緩和されたことで、継続雇用期間6か月未満の人でも介護休暇が取得できるようになりました。また、事業主側は継続雇用期間6か月未満の労働者を介護休暇の対象外としている場合、就業規則を改定し周知する必要があります。
要件のうち、「週の所定労働日数が2日以下」についてはそのまま維持されます。これは、週3日以上働いている人は、介護休暇を取得できるということです。正社員に限らず週3日のパート勤務や試用期間中でも介護休暇は取得できます。
【2】介護離職防止のための環境整備(義務)
介護休業や介護両立支援制度等を利用しやすい職場環境にするため、事業主には「研修の実施」「相談窓口の設置」「事例の収集・提供」「利用促進に関する方針の周知」のいずれか1つ以上(複数が望ましい)を実施することが義務付けられました。
ポイント
介護休業や介護両立支援制度などに関する情報が、会社全体に広く伝わることが大切です。制度は「知っていても使わない」のと、「知らなくて使えない」は大きな違いです。今回の改正では後者の「知らなくて使えない人」が減少することが期待できます。
【3】介護離職防止のための周知や意向の確認(義務)
周知や意向の確認について2つの項目が盛り込まれました。
介護に直面した人に対し、意思を確認して制度の内容を伝える
介護休業に関する制度や介護両立支援制度、人事部などの申し出先 、給付金に関することを説明し、意向の確認を個別に行わなければなりません。
介護に直面する前の早い段階での情報提供
事業者は、労働者が介護に直面する前に、介護休業や介護両立支援制度などについての等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。情報提供の期間が定められていて、40才を迎える年の1年間か、40才の誕生日から1年間のいずれかとなっています。
意向の確認や情報提供については、いずれも申し出た方に対して面談(オンラインも可能)などを実施することが義務づけられました。
ポイント
介護が始まって行き詰る前に、事業者側は情報を提供することが必要です。「介護休業の取得や利用の前例がないことを強調したり、事業者側の不利益をほのめかしたりといった、介護休業の取得や利用を控えさせるようなことは言ってはならないとされています。
【4】介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
ただし、テレワークに向かない業務の担当者を、テレワークが可能な職種へ配置転換することや、テレワークができる業務を新たに考えることを事業主に求めるものではありません。
ポイント
努力義務なので、罰則や強制力はありません。テレワークが可能かは職種によりますが、介護をする労働者がより柔軟な働き方が選択できれば離職防止につながるでしょう。
テレワーク勤務は、介護には有効ですが、つきっきりの介護や頻繁な介助が必要な場合には仕事に集中できないことも。思うように仕事が進まないストレスから要介護者に当たってしまうという声も聞かれます。時間を区切って仕事をするなどテレワークにしても工夫が必要かもしれません。
厚生労働省のテレワーク活用のためのパンフレット「テレワーク活用の好事例集 仕事と育児・介護の両立のために」を参考にしてみてください。
■厚生労働省「テレワーク活用の好事例集 仕事と育児・介護の両立のために」
tele-koujireisyuuH27.pdf
介護休業法改正【まとめ】
今回の法改正は、働く側にメリットが大きい内容でした。介護があるから仕事を諦める、そんな悩みも解決できる一歩ともいえます。
一方で、長年メーカーに正社員勤務しながら在宅介護を続けてきた筆者は「介護を理由に自分だけ特別扱いを続けていいのか」とも感じていました。介護休業を取得する年齢層は中堅層が多く、職場によっては「リストラの対象になるのではないか」「ポジションを失うかもしれない」といった不安の声も聞かれます。
制度自体をわかっておくのは前提ですが、まずは「有休休暇」に余裕がある場合はそちらから活用するといいでしょう。介護休暇は欠勤扱いにはなりませんが、有給か無給かは会社の規定によります※。
制度や受け皿がどんなに整っても、気持ちやお金の面など企業と労働者双方が納得できるものになるかどうかは難しい問題かもしれません。
■厚生労働省「介護休業制度特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/index.html