コメント
この記事へのみんなのコメント
-
さゆり
2020-10-15
私の母親は介護付きマンションに入っています。認知症、寝たきりになっても入居でいられるところです。 親の介護はプロに任せるべき。まして姑、舅が嫁に介護を求めるのは今の時代考えられず、まことに図々しいことと思います。
-
ふじもと
2018-02-23
嫁が介護するという考えが、既に時代遅れであることは同感ですが、著者のようにはうまくいかないケースもあると思います。実は、親が独居(遠距離でなくても)で、通い介護が基本の場合は、かなり柔軟な介護体制が取れます。介護保険制度でも、独居の老人がもっとも多くのサービスが受けやすくできています。 介護は、高齢者と1対1では厳しいです。少なくとも介護者は2人以上確保したい(これに公的なヘルパーや看護婦が必要になります)しかし、介護者の片方が同居している場合、その介護者は、気の休まるときがなくなってしまいます。介護を他の人に任せられる時間でも、介護される高齢者が隣の部屋にいる、階下にいると言う状態では、ちょっとした物音でも気になり、手伝ってしまったり、気が休まらなかったりで、睡眠すら十分に取れない事もあります。 介護疲れを解消するには、最低でも頭の切り替えが必要で、そのためには、介護する場所を離れて、環境を変える事がもっとも有効です。 さらに、この複数の介護者の連携が、介護ではもっとも重要な要素になります。連携や意思の疎通がうまくいけば、精神的も支え合っていけますが、往々にして、介護される高齢者に対する考えの違いや、立場の違いから、利害や感情の対立が起こりがちです。これはごく些細なことの積み重ねが多いので、こういうときに、独居の老人の家に互いが通いで介助すると言う方法は解決策になります。つまり介護者同士が顔を合わせる時間を減らせると言う事です。全く顔を合わせないわけにはいかないですが、メールでも電話でも、きちんと申し送りをして、たまには顔を合わせてと言う程度なら、感情的な部分を見せすぎない、良い距離感を保ちやすくなります。この微妙な距離感が、意外と重要です。 著者が妻を介護に参加させなかったというのは、ある意味賢明なのです。妻と介護上の問題で対立し、それを自宅に持ち込んだら精神的につらいでしょう。それに著者の場合、妻も自分の親の介護をするわけですから、介護の上での共感や、辛さを慰め合うことはできます。良い距離感の取り方かもしれません。 嫁が介護をすると言う概念が時代遅れであっても、もし1人の子供が親と同居し、その妻がいた場合は、この問題は現実味を帯びます。ともかく同居している介護者は頭の切り替えが難しいですし、他の兄弟などに助けを求めるにしても、家族以外の人間がしょっちゅう自分の家に出入りすると言う状況になります。赤の他人であるヘルパーが入ってくるよりも、身内に出入りされる方が結構負担になるものです。さらにここに嫁がいたら、出入りする身内に気を遣わざるを得ませんし、この環境で「私は介護に参加しない」というわけにはいかなくなるのが現実でしょう。嫁と、嫁ぎ先家族の微妙な関係がそのまま介護に反映されますので、嫁は大変です。 こういう関係性の時ほど、通い介護はもっともふさわしいと思います。もし介護者同士の関係がぎくしゃくしても、顔を合わせずに淡々と介護を協力し合うと言う事が可能です(皆が大人の関係に徹する) 嫁が介護に参加することの難しさは、他人である義両親の介護をすることが、感情的に難しいと言う事ではないのです。実際には介護に血のつながりは関係なく、実親だろうと、難しい事は難しい。それよりも、介護者同士の連携という点で、親との関係性が違うために生じる齟齬が一番難しいのです。 私も正直、義両親の介護をすることは特に抵抗はないのですが、連携する夫側の家族との関係の方が難しいですね。
最近のコメント
-
たけちゃんマン
2026-01-08
昨年暮れに退院しました虫垂炎でしたが色々有り三週間入院してしまいました医者や看護師さんには感謝しかありません^_どんな場面でも笑顔でありがとうと言う言葉に勇気を貰い自分を見つめる事が出来改めて病気を理解して退院に至りました、自分の置かれた立場を理解する事は大変でしたが介護をしてくれた人達がいたからの退院だと思います自宅静養では病気の苦しさを思い出し健康的に毎日を過ごしております。
-
ピカピカ
2026-01-08
最近目がどんどん見えなくなってきている父おやの介護がそろそろ必要なのかなと思っています 体も脳も健康で目だけなので必要ないといいますが勉強するのに登録してみようかな
-
梅干しババア
2026-01-07
柴田理恵さんの暗くて悲しい老後に涙が出てきました。
関連記事





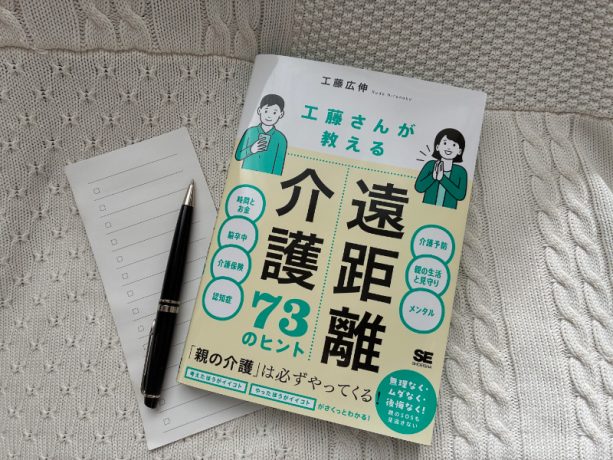
シリーズ








