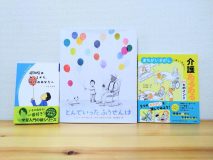【介護未満】親が「まだ大丈夫」と言っているうちにやっておくべきこと「地域包括支援センターに行く」「希望を聞く」「お金の話」
介護が必要なほどではないものの、体の不調や忘れ物が多くなったりと自立した生活が難しくなる「介護未満」の親。老いていく親との向き合い方や「介護未満」のうちにやっておくべきことを専門家に聞いた。
教えてくれた人
明石久美さん/相続・終活コンサルタント、太田差惠子さん/介護・暮らしジャーナリスト、カータンさん/ブロガー・著書に『健康以下、介護未満 親のトリセツ』(KADOKAWA)
親が高齢になったら地域包括支援センターへ。福祉の人とつながっていることが安心につながる
親が「まだ介護はいらない」と思っていても、実際には「要支援」や「要介護」の状態になっている可能性がある。
相続・終活コンサルタントの明石久美さんは、「まずは地域包括支援センターを使うこと」をすすめる。
「地域包括支援センターに行けば、要介護認定を受けていない場合でも相談に乗ってくれますし、さまざまな情報が載っている介護支援の冊子もある。早めに福祉の人とつながっておけば、いざというときにとても安心です」(明石さん)
自身の体験をもとに『健康以下、介護未満 親のトリセツ』(KADOKAWA)を著したブロガーのカータンさんも続ける。
「地域包括支援センターは、張り紙をしておきたいぐらい重要な場所。多くの人は“うちの親は大丈夫”と思っているし、親自身も自分がボケるなんて思っていないから、なかなか家族でそういう話に触れません。でも、いざ認知機能が怪しくなってくると、どうすればいいのかわからない。親も子供である私たちも、まだ元気なうちに備えておく方がいいです」
頭にしろ体にしろ老いが加速した場合、要介護認定が下りる前でも、受けられる行政サービスを活用するのも手だ。
「市区町村の総合事業サービスを使えば、“ちょっと援助が必要かな?”という状態でも、ヘルパーさんに来てもらえたり、デイサービスに行けたりします。
→要介護ではないが高齢のため日常生活のちょっとした困りごとが増えた!そんな人に頼れるサービスの探し方
多くの親御さんは介護はまだ関係ないと思いたいので“要介護認定”と言うと反発しますが、“予防のためのサービスがある”と言えば、すんなりいく可能性もある。かかりつけ医がいたら、医師から伝えてもらうのも効果的です」(介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さん・以下同)
無理に説得しない。“介護未満”の親が動き出す伝え方のコツ
食事が疎かになっているようなら食事の宅配サービス、遠方に住んでいて心配なら郵便局の見守りサービスもある。
“健康以下”の親とつきあうには、適度な距離感や行政サービスなど第三者の介入が必要だ。一人ひとり性格が違うため、効果的なアプローチ方法もさまざま。太田さんは介護未満の人を上手に動かす“コツ”があると話す。
「突然“○○ができない”“ヘルパーが必要”と言われたら誰でも反発します。少しずつ情報を親に伝えて、興味を持ってもらうとスムーズに行きやすい。雑誌などの情報も“まだお母さんには関係ないと思うけど、便利そう”と伝えれば抵抗はないでしょう。宅食サービスを嫌がっても、孫に“おばあちゃん、最近やせたね”と言われたら胸に響くかもしれません」
寝たきりを防ぎ、いつまでも歩ける体を維持するための運動習慣も、伝え方次第だ。
「“フレイル予防のための体操”と言われて嫌な顔をする人でも、流行りのジムなら楽しそうに通ったりする。若い人向けでおしゃれな感じがする『ピラティス』という言葉に反応するシニアも多いです」
親の考えは“介護未満”のうちに聞き出すべし
認知症など本当に介護が必要になってからでは、「親が望んでいること」を知るのが難しくなる。
「母はいま施設に入っていますが、介護未満のうちに親の希望を意思確認して、施設などを見学していました」(カータンさん・以下同)
いざというときのために「死」に対する本人の考えを知っておくことも大切だという。
「終末期医療をどうするか本人の希望を聞いておかないと、家族が選択を迫られて罪悪感を持つことになってしまう。普段から親と話をしておくことが、その後のいろいろな判断において大事になってきます」
終活でも、難しい選択を迫られる。カータンさんが直面したのは、父が亡くなった後の遺品整理だった。
「母にいるかいらないかと聞くと、全部“いる”って言う。でも、そのままにしておいて、私が死んでしまったら、今度は自分の子供たちに重荷を背負わせてしまうことになる。父も天国で“もういいよ”と言っていると思って、エイヤって捨てました。私も残しておくと迷惑になるものは元気なうちに処分しておこうと思っています」
「代理人カード」と「代理人登録」でお金のトラブルを防止
さらに誰もが避けて通れないのが「お金」の話だ。認知機能が低下して本人が思い出せなくなる前に、預金などの財産や保険の“ありか”を聞いておかないと、いざ介護費用がかかるようになったときや相続のときに苦労することになる。
「お金については要介護になる前から話しておくことがとても大切。私はそれをやっていたので問題ありませんでした。私自身、万が一に備えて、娘たちに暗証番号なども伝えてあります」
明石さんは介護未満のうちにやっておくべき、「2つのこと」を紹介する。
「ひとつは銀行で代理人カードを作成しておくこと。銀行によって要件が異なりますが、そのキャッシュカードを使って親の代理で入出金ができるうえ、親から通帳を預からなくても財産管理が可能になります。
もうひとつは代理人登録をしておくこと。判断力が低下したとき、本人に代わって窓口での手続きができます。家庭裁判所が選ぶ後見人がついてしまうと、本人名義の財産をすべて管理され、家族の要望を聞き入れてもらえなくなる可能性もあるので、どちらもやっておいた方がいいです」(明石さん・以下同)
銀行口座をひとつにまとめた方が管理は楽そうだが、やめた方がいい。
「銀行の判断で口座が使えなくなったときのために、一本化はリスクが高い。もしものときのために、2〜3の口座を残しておけば、ひとつの口座が凍結したとしてもほかの口座は使える可能性もあり得策です」
介護未満の親とのつきあい方で、親の老後やあなた自身の暮らしが大きく変わることを知っておきたい。
写真/PIXTA
※女性セブン2025年11月6日号
https://josei7.com
●《すみちゃんねる》60代の人気YouTuberが明かす壮絶介護生活「認知症のおばを20年介護して得たもの」
●《コロナ禍から5年続ける》ジェーン・スーさん、要支援2・87歳の父親の生活支援に必要なのは「テクノロジー、そして稼ぐこと」
●《親の死後に問題になりがちなお金問題》親が元気なうちにやるべきこと…通帳やクレジットカードの明細で見落としてはいけないポイント