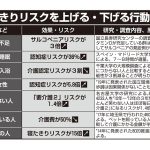世界的な長寿研究の第一人者が指南する歳をとっても頭を元気に保つための方法「いつまでも挑戦を続ける」「ボランティアへの参加」
取り組む場所にかかわらず、継続的な学びで脳を刺激する必要がある。認知科学者が勧める2つの優れた方法は、新たな言語の学習と、楽器の演奏だ。ただし、国連認定の通訳や、プロのミュージシャンなら別だ。その場合、これらの能力はすでに十分に身についているので、ほかのことに挑戦したほうがいい。これらが新しいスキルであれば、個人レッスン、コミュニティセンター、自習などで学べる。
また、言語の習得においては、その言語が使われている場所に身を置くのも有効だ。旅行は、新しい言語スキルを実践するだけでなく、人と会い、ふだんと違う食事を試し、遠くの場所の歴史や文化を学べる優れた方法だ。
自分自身を停滞させない
教育は決まった方法で行わなければならない、と考える理由はない。じっと座って学ぶのがあまり得意でなければ、アクティブで実践的に学べる、これまでずっとやりたかったことに挑戦しよう。庭いじりを始める、地元の劇団に参加する、野外観察用の図鑑を買ってハイキングをする、クラシックカーのレストアといったガレージで行うプロジェクトに取り組む、水彩絵の具をもって海辺へ出かけるなど、いろいろ考えられる。
自宅で学習するのがいちばん安心だという人には、オンラインクラスや、ビデオや本などの教材がある。堅苦しくない、和気あいあいとしたグループで学びたいなら、読書クラブやハイキングクラブに参加したり、地元の大学、図書館、美術館や博物館、芸術性の高い映画を上映する映画館などで実施される講義を受けるのもいい。
大切なのは、自分が深くなじんでいる行動ばかりとったり、自分がよく知っている分野の専門書ばかり読んだりして、自分自身を停滞させないことだ。得意分野以外で何かに挑戦してみよう。たとえば、もしあなたが会計士であれば、夜間の数学クラスよりもバンジョーを演奏する講座のほうが、認知機能の発達に役立つ。もし、すでに3つの言語を流暢に話せるなら、4つめの言語を学ぶよりも陶芸をしてみたほうが認知機能を刺激するかもしれない。
◆著者・監修者・訳者情報
【著者】
ローラ・L・カーステンセン(Laura L. Carstensen)さん
スタンフォード大学心理学部教授、ならびに同大学フェアリー・S・ディキンソン・ジュニア記念講座公共政策学教授。スタンフォード大学長寿研究所の設立者で所長も務める。カーステンセン博士の研究は20年以上にわたってアメリカ国立老化研究所から支援を受けている。グッゲンハイム・フェロー、アメリカ国立衛生研究所(NIH)メリット賞受賞者、マッカーサー財団高齢化社会ネットワーク会員でもある。カリフォルニア州ロス・アルトス・ヒルズ在住。
【監修】
米田隆さん
早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所招聘研究員、公益社団法人日本証券アナリスト協会プライベート・バンキング(PB) 教育委員会委員長、株式会社青山ファミリーオフィスサービス取締役。早稲田大学法学部卒業。日本興業銀行の行費留学生として、米国フレッチャー法律外交大学院修了、国際金融法務で修士号取得。金融全般、特にプライベート・バンキング、ファミリービジネス及びファミリーオフィスの運営、ファミリーガバナンスの構築、新規事業創造、個人のファイナンシャルプランニングと金融機関のプライベート・バンキング戦略などを専門とする。著書に『世界のプライベート・バンキング[入門]』(ファーストプレス)、訳書に『新版 究極の鍛錬』(サンマーク出版)、『50 歳までに「生き生きした老い」を準備する』(ファーストプレス)、『ファミリービジネス 賢明なる成長への条件』(共訳、中央経済社) などがある。
【訳者】
二木夢子さん
国際基督教大学教養学部社会科学科卒。ソフトハウス、産業翻訳会社勤務を経て独立。訳書に『スケーリング・ピープル』『TAKE NOTES!――メモで、あなただけのアウトプットが自然にできるようになる』(ともに日経BP)、『Creative Selection―Apple 創造を生む力』(サンマーク出版)、『われわれは仮想世界を生きている』(徳間書店)、『EMPOWERED』『両立思考』(ともに日本能率協会マネジメントセンター)、『オリンピック全史』(共訳、原書房)などがある。