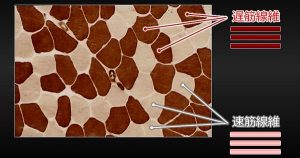もしLINEが五七五だったら……和歌は超便利装置
「和歌の五七五七七ってパッケージだったんです。なんでもかんでもこれに入れてしまうのが日本文化なのです」と語る、早稲田大学教授の兼築信行先生。和歌から入る日本文化論はなかなか刺激的だ。
なんでもかんでも五七五七七にする日本人
五音と七音の組み合わせって、古臭い感じもするのに、どうしてこんなにしっくりくるのだろう。「笑う門には福来る」「一姫二太郎三茄子」など、昔からのことわざだけかと思ったら、今のテレビ番組のタイトルにもあるではないか。視聴率20%超えを連発している『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ系)、昨年の大ヒットドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』(TBS系)。どちらも覚えやすいタイトルだ。
「日本人にとって伝えたいことを普遍化する装置が、五七五七七です」と語るのは、早稲田大学エクステンションセンターで和歌講座をもつ兼築信行先生(早稲田大学文学学術院教授)だ。和歌は古くから男女が思いを通わせるためのコミュニケーションツールだったと兼築先生は言う。
「漢字から生まれた仮名は、女手(おんなで)と呼ばれていました。仮名は漢字をやわらげたものですが、とくに女性が使うものでもありました。それで日本人は何をしたかというと、和歌を作って思いを通じ合わせたんですね。つまり、男と女が互いにアクセスできる文字が仮名であり、そのパッケージが和歌だったのです。同じ漢字文化圏だった朝鮮で、ハングルが文字の読めない人のためにできた文字だとすれば、日本では、男女が愛し合うために仮名文字をつくったともいえます」
事実、今に残る和歌で最も多いのは恋の歌だ。待つ恋、忍ぶる恋、初恋……。ここで記者は目からウロコの話を聞いた。この有名な歌について、だ。
女は待つ恋、男は忍ぶる恋
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへばしのぶることの弱りもぞする
「私の魂よ、絶えてしまうなら絶えてしまえばいい! 生きながらえていると、心に隠したこの思いがもれ出てしまうから……」と、秘めた恋をうたうもので、『新古今和歌集』恋一に収録されている。
後白河院の皇女である式子(しょくし)内親王の歌だとされてきたが、最近では男性が詠んだ歌だとする説が有力になってきたという。
「恋のテーマには、初恋、待つ恋、忍ぶる恋など、たくさんの種類がありますが(一説には200種類とも)、女性はアプローチの歌は詠まないのです。忍ぶる恋も初恋も男性のもの。逆に男性は待つ恋を読まない。なので、忍ぶる恋を歌った“玉の緒よ絶えなば絶えね……”は男性が詠んだ歌と言われています」(兼築先生。以下「 」内同)
和歌の形だからこそ、防人歌も東歌も残った
ちなみに、男が女に成り代わって読んだり、童心にかえって幼き恋を詠んだりすることもある。兼築先生は、和歌には人間関係を学ぶための一種のロールプレイングとしての面もあったという。
「昔の人の歌を参考にしながら、今の自分でない誰かに成り代わって歌をつくるということは、その人の気持ちを推し量り、その気持ちが生まれた背景を考えることにつながります。つまり、和歌というかたちで先人や他人の経験を追体験することになります」
そして和歌はまた、類型性を持っているがゆえに、とても便利な記録装置であり、記憶装置であったという。
「日本で一番古い歌集は今から約1300年ほど前に生まれた『万葉集』です。その中には、唐や新羅から日本を守るために徴兵された防人(さきもり)の歌や、東国の民謡や歌謡を収めた東歌(あずまうた)などもあります。1300年もの間、私たちはそれらの歌を詠んで、徴兵されて遠く離れた故郷を思慕する思いとか、貧しい中でも家族を思う心とか、自然を愛でる気持ちとか、そういった心に触れてきました。もしそれらの歌が和歌のかたちを取っていなければ、残らなかったでしょう。防人歌や東歌を収集・編集したのは大伴家持ですが、彼は元の民謡や歌謡を多少手入れして、和歌の形にしたのではないかと思います」
もしLINEが和歌だったら
「俵万智さんは、短歌とはメッセージだといっていますが、そのとおりなんです。日本人は小さくて短いものが大好き。そういったものにメッセージをこめたがる。もしLINEが五七五七七の三十一文字だったら、その枠の中ですてきなメッセージを送ろうと知恵を凝らすでしょう? つまり和歌とはスペシャルなパッケージなんです。同じ言葉でも、五七五七七にすれば、老舗百貨店のリボンをかけられたような立派な贈り物になる」
そう言う兼築先生は、フェイスブック上での誕生日メッセージはすべて和歌にしているという。
「日本人が生み出した、このとても便利でおしゃれな和歌という装置、この五七五七七のパッケージを、現代生活でも使ってもらいたいと思います」
〔あわせて読みたい〕
変体仮名、パズルのように読み解いて日本文化を鑑賞
古典って何のために読む?「日本を楽しむためですよ!」
取材・文・写真/まなナビ編集室
初出:まなナビ