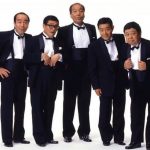『鎌倉殿の13人』34話「きのこ!大好きなんです!」だが、菊地凛子がそれで済むわけがなかった
NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』34話。3代鎌倉殿の源実朝(柿澤勇人)の政務が開始され、同時に縁談話が進みます。また、北条義時(小栗旬)にも思いがけず再々婚話が持ち上がって……。「理想の結婚」(副題)の回を、歴史とドラマに詳しいライター、近藤正高さんが、歴史書を紐解きながら考察します。
成長著しい実朝
『鎌倉殿の13人』第34回では、第3代鎌倉殿の源実朝を演じる俳優が子役から柿澤勇人へと交代した。とはいえ、今回描かれた時期は、前回、実朝の兄・頼家が殺されてからまだ数ヵ月しか経っていない。この年=元久元年(1204)当時、実朝は数え年で13歳。いまでいえばまだ小学6年生である。それがわずか数ヵ月でここまで成長するなんて……とついツッコみたくなるが、『鎌倉殿』にあってはもはやそれも野暮だろう。
思えば、頼家役の金子大地と泰時(当時・金剛)役の坂口健太郎も、富士の巻狩りの回で初登場したときの設定年齢は、それぞれ12歳と11歳だった。さすがに坂口が180センチを超える長身のせいか、「成長著しい金剛」というテロップが入っていたが。そもそも小栗旬演じる義時の初回における年齢は、今回の実朝と同じ13歳だった。演じ手が子役から交代する年齢も、これが一つの基準になっているのかもしれない。
実朝は今回、いよいよ政務を開始した。ただし、それはあくまで形のうえでのこと、実権は外祖父にあたる執権の北条時政(坂東彌十郎)が握ることになる。その代わり、実朝は立派な鎌倉殿となるべく、武芸の特訓を受けたり、政治の心得を学んだりと、いきなり多くの課題を背負わされる(相撲の稽古で投げ飛ばされる実朝を見たら、たしかに子役が演じるのは無理だと思わされた)。
権力の頂点に立った時政はすっかり調子に乗っていた。そのなかで畠山重忠(中川大志)と軋轢が生じる。原因は、畠山氏の所領のある武蔵国を、時政が亡き比企氏に代わり支配しようと企んだことにある。前回の話では時政自身が武蔵守(武蔵国の長官)になるつもりでいたが、今回一転してこれを重忠に任せることにした。だが、畠山氏は代々、武蔵において惣検校という官職を継いできた。そこへいきなり時政から、武蔵守にしてやるから惣検校職は返上しろと言われ、戸惑うばかり。そもそも時政にそんな権利があるのか……。悩んだ重忠は義時に相談する。
時政は訴訟の裁きにおいても、あろうことか自分に付け届けを贈ってきた者に手心を加えていた。義時がまずその件で問いただすと、時政は煙たがり、聞く耳を持たない。だが、続けて武蔵をどうしたいのか、畠山と一戦を交えるつもりなのかと訊かれると、途端に顔色を変え、「誰もそんなことは言っておらん!」と怒鳴ってその場を立ち去ってしまう。むきになるあたり、やはりそのつもりなのかとかえって訝しく思われ、どうにもきな臭い。
時政はまた自らの権威を高めるべく、実朝の正室は京から迎えると決めていた。そこで選ばれたのが、前の権大納言の坊門信清の娘で、後鳥羽上皇のいとこにあたる千世だった。時政の妻・りく(宮沢りえ)と実朝の乳母・実衣(宮澤エマ)は大江広元(栗原英雄)とともに、これ以上の相手はいないと、実朝の生母である政子(小池栄子)を説得する。政子はあまり気乗りしない様子ながら、御家人の家から正室を取ればまた争いが起きかねないとして、この縁談を認めた。
こうして実朝の結婚相手が決まり、元久元年(1204)10月には、千世を迎えに行く使者として、時政とりくの一人息子である政範(中川翼)が鎌倉から京に向け出発した。京にはすでに時政の娘婿の平賀朝雅(山中崇)が滞在していた。
政範死去の報
今回は「理想の結婚」(昔、そんな題名のドラマがあったっけ)というサブタイトルどおり、実朝の縁談とともに、義時にも再々婚の話が持ち上がる。ここしばらく毎回のように人が殺されてきただけに、今回は一息つくような回になるのか……と思いきや、途中で背中がゾクッとなるような出来事が起こった。
発端は、政範の到着を前に、朝雅に源仲章(生田斗真)がささやいたことにある。仲章は、朝雅に執権になる気はないのかと切り出した。これに対し朝雅は初めこそ否定していたものの、仲章から、仮に政範が病で突然亡くなり、代わって朝雅が千世を連れて鎌倉に凱旋すれば、時政も必ず次の執権に選んでくれると言葉巧みに誘導され、その気になってしまったらしい。じつはこれは後鳥羽上皇(尾上松也)の差し金であった。上皇が乳母の藤原兼子(シルビア・グラブ)を招いた席で、仲章は「渡したものを(朝雅が)大事に使ってくれるとよいのですが」と思わせぶりに言うと、慈円(山寺宏一)も「あとは、あの男にどれだけの度胸があるか……」と口走った。
その後、11月に入り、京に到着した政範を出迎えた朝雅は、酒宴の支度をしてあると館へ招き入れる。が、場面変わって、鎌倉に伝えられたのは、政範死去の報であった。長澤まさみのナレーションで「急な病であったといわれているが、真偽は不明」と説明されていたように、先ほどまでの流れを見ると、どうしたって朝雅の関与を疑わざるをえない。真相は次回にもあきらかになるのだろう。
ともあれ、実朝を自分の側に引き寄せ、北条をつぶそうとする後鳥羽上皇の姿勢は、かつて後白河法皇が義経を自分のもとに置こうとして、頼朝と対立したことを思い起こさせる。ただ、義経と頼朝の分断は、後白河法皇の策略というよりは、法皇の義経への個人的な思い入れから結果的にそうなってしまったところがあった。これに対し後鳥羽上皇は、すべては朝廷のためという確たる意志のもと、実朝と北条を切り離そうとしている点で大きく異なる。
今回は、後白河法皇のわがままぶりにさんざん振り回された九条兼実(田中直樹)も久々に登場した。慈円の実兄である兼実は、法皇の死後、土御門通親との権力闘争に敗れ、政治から退いていた。その兄から「鎌倉はこの先どうなる?」と問われた慈円は、「世の理に反すれば、見えざる力、冥の道理(目に見えない道理)が必ず鎌倉がつぶします」と答え、さらに「大事なのは朝廷の繁栄」と強調した。それを聞いて兼実は「頼んだぞ、慈円」と、希望を弟に託すのだった。彼はこの3年後、建永2年(1207)に亡くなる。
このように実朝の結婚をめぐって人々の思惑が渦巻くなか、当の実朝は周囲に従うがままであった。そこに不安を覚えてか、顔色がすぐれない状態が続く。そんな息子を心配した政子は一計を案じる。朝廷より頼朝に贈られた和歌集から彼女自ら歌を選りすぐって書き写した分厚い紙の束を、実朝に渡すよう三善康信(小林隆)に預けたのだ。
このとき、和歌を写した政子の達筆ぶりに、彼女が頼朝の生前、その浮気相手である亀から、御台所としてそれにふさわしい教養を身につけるよう諭されたことを思い出した。当時は和泉式部も知らなかった政子だが、おそらくそれ以来、人知れず努力してきたのだろう。そうやって身につけたものが、今度は息子のため活かされようとしていた。
それにしても亀もそうだったが、りくといい実衣といい、『鎌倉殿』に出てくる女性には野心家タイプが目立つ。それというのもこの時代は、権力者の妻や愛妾、あるいは乳母ともなれば、女性でも権力の中枢に入り込める可能性が、その後の時代とくらべても大きかったからだろう。今回登場した藤原兼子も、後鳥羽上皇の乳母という立場から朝廷で重んぜられ、権勢を振るった。のちに実朝の後見人として義時とともに政子が実権を握ると、京の兼子とあわせ、《日本国は女人が最後の仕上げをする国であるということは、いよいよ真実であるというべきではあるまいか》と慈円が記しているほどである(『愚管抄 全現代語訳』大隅和雄訳、講談社学術文庫)。
「きのこ!大好きなんです!」
やはり今回初めて登場した、義時の縁談の相手であるのえ(菊地凛子)もまたこのタイプの女性であった。しかし、彼女はその本性を隠して義時に近づくのだが……。
そもそも、のえとの縁談は、義時が文官の二階堂行政(野仲イサオ)から孫娘をもらってほしいと強く勧められたのが発端だった。これをなぜか大江広元も後押しする。義時が察するに、文官たちはどうやら時政と対抗するため、義時を自分たちの側に取り込もうという思惑もあって、この縁談を持ちかけてきたらしい。
ひとまず、のえと会うことにした義時は、彼女が結婚相手にふさわしいかどうか見定めるべく、こっそり八田知家(市原隼人)に立ち会ってもらうことにした。これまで女性についてはもっぱら親友の三浦義村(山本耕史)に相談してきた義時だが、「あいつはいまひとつ信じきれない」と、今回は知家に頼んだのだ。
初対面ののえは、義時の肩に紅葉がついているのに気づくや、それを取ってみせた。これに彼は好印象を抱く。知家からも「非の打ちどころがない」「おまえが断ったら、俺が名乗りをあげてもいいぐらいだ」とお墨付きを得る。義時は念のため、裏には別の顔があるかもしれないがと問うが、知家は「裏表なし」と断言した。
後日、のえは義時の館を訪ねてきた。そこでさっそく、床に散らかった着物に気づいて畳み始めたかと思えば、義時の幼い息子たちに対しても、彼らの目線に立って元気に遊んでくれる。しかも義時が山盛りのキノコを差し出すと、「きのこ! 大好きなんです!」と快く受け取ってくれた。
きのこといえば、義時が「おなごが好きなもの」と思い込み、のちに結婚する八重と比奈、さらには嫡男の泰時がいまの妻の初(福地桃子)にアタックする際にも贈っては、ことごとく拒否されてきた。それだけに、のえが喜んでくれて義時はうれしかっただろう(ただ、女子は必ずしもきのこ好きではないとこれまで何度も思い知らされながら、なぜ、のえにそれを贈ったのかという疑問は湧くが)。
しかし、のえの「大好きなんですぅ~」という口調はいかにもあざとく聞こえた。そもそも菊地凛子が、ここまで男性に都合のいい女性を演じるなんてことがあるだろうか……と思っていたら、案の定、ラストで彼女の本性があきらかになる。
泰時が御所の台所の前を通りかかったところ、のえがきのこは嫌いだと、同僚と思しき女房(侍女)たちに分け与えているのを目撃してしまったのだ。どうやらのえは義時に好意を持ったわけではなく、御所の女房という境遇から抜け出すため、縁談に乗ったにすぎなかったらしい。泰時はもともと、義時が手前勝手な理由で比奈と別れておきながら、すぐ再婚するとは何事かと反対していただけに、果たして真相を知ってどう動くのか? それにつけても、今回、実朝や義時を館に招き、鹿汁を振る舞った和田義盛(横田栄司)が、妻の巴御前(秋元才加)とかつての恩讐を越えて仲睦まじくやっているのを見せられると、義時と比奈にもこのようになる道はなかったのかと、つくづく惜しまれる。
ちなみに、のえにとって二階堂行政は母方の祖父にあたる。彼女の父親は藤原朝光という関東の豪族で、のちに伊賀守となり、名字も伊賀とした。彼女の名も「伊賀朝光女(いがともみつのむすめ)」あるいは「伊賀の方」として歴史に残っている。
さて、三善康信は政子から預けられた例の紙の束を、こっそり実朝の部屋に置いておいた。それに気づいた実朝は、書き写された和歌をむさぼるように読み始める。政子の思いは無事に伝わったのだ。
和歌はこの時代、実朝の兄・頼家が得意とした蹴鞠と同様に、朝廷との重要なコミュニケーションツールであった。頼朝もまた和歌を詠み、上洛したときには慈円と歌をやりとりした。政子はそれをよく覚えていたがゆえに、実朝に和歌を学ばせようと思ったのだろうという見方もある(五味文彦『源実朝――歌と身体からの歴史学』角川選書)。
ただ、『鎌倉殿』において、蹴鞠は頼家が現実を忘れるための逃げ場所となってしまった。そう考えると、実朝にとっての和歌はどうなるのか。筆者の希望としては、実朝が、同じく和歌を得意とする後鳥羽上皇と堂々渡り合う姿をぜひ見てみたいところではある。
文/近藤正高 (こんどう・ まさたか)
ライター。1976年生まれ。ドラマを見ながら物語の背景などを深読みするのが大好き。著書に『タモリと戦後ニッポン』『ビートたけしと北野武』(いずれも講談社現代新書)などがある