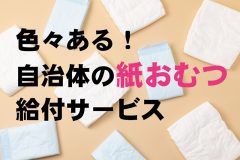【ソーシャルコンチネンス】を目指そう!いま、大人のおむつ界隈で起こっていること「フェスや防災で若い世代がおむつを活用する時代に」「赤ちゃんから高齢になるまで絶え間ないおむつ利用ができる社会へ」
大人のおむつ使用に関して、新たな風が吹いてきた。おむつの課題解決や情報発信を長年続けている理学療法士で「おむつ情報局」を運営する八木大志さんに現状を伺った。
教えてくれた人/八木大志さん
WEBサイト「おむつ情報局」https://062.design/を主宰。理学療法士、福祉用具貸与事業所勤務を経て、「おむつ宅配便」を立ち上げるなど、おむつは自立支援の福祉用具と捉えて、適切な情報を届ける活動を続けている。
注目の「ソーシャルコンチネンス」とは
――八木さんは、【おむつ】を通じ、その背後にある自立支援という大きなテーマに取り組んでいらっしゃいます。
八木さん(以下敬称略):理学療法士や介護のための住宅改修の事業所に勤務した経験をきっかけに、おむつや排泄にまつわる課題は大きいことに気づき、情報を発信する活動を始めて10年になります。いまは、「ソーシャルコンチネンス」という考え方が、国際的にも注目されてきています。
――ソーシャルコンチネンスについて教えてください。
八木:水洗トイレで排泄できることだけが「トイレの自立」ではありません。おむつを使っていても、自分の皮膚をきれいに保ち、おむつを適切に交換・処理できて、社会生活の中で困らないのであれば、それは排泄における社会的な自立だと考えています。
おむつを恥ずかしいと思って使用するのではなく、自信をもって、うまく活用してほしいんです。
――おむつを使用しながら、社会的に自立した暮らしを送ろうという考えですね。
八木:ちゃんと皮膚のケアをしなければいけませんし、周囲を汚さずにおむつの処理をする。そのためにおむつを捨てる場所のインフラなど環境整備も必要ですね。
おむつは、赤ちゃんの頃に使って、その後は高齢期になってから再び使用を始めるというイメージが一般的です。しかし、赤ちゃん期と高齢期のあいだにはとても長い期間があります。私は、その間の年代でも、状況に応じておむつを活用しても良いのではないかと思います。
キャンプやフェスで、おむつを活用する若い世代の姿も見られるようになってきた
――例えば、どういう使用シーンがあるでしょうか?
八木:キャンプやフェス、防災などです。若いうちに、おむつを使う経験があれば、赤ちゃんから高齢期まで途切れなく使えるアイテムとして身近な存在になります。実際、若い世代では、おむつに対する偏見が以前より少なくなってきていると感じています。
――若い人が、実際におむつを活用されている例などはありますか?
八木:私に直接届いたものではありませんが、SNSなどでは「登山で使用している」「フェスで最前列をキープするために使っている」といった声が見られます。シーンによっては、おむつが一つの選択肢として受け入れられつつあると感じます。
――若いうちから利用をしていたら、おむつへの抵抗感はなくなりそうですね。
八木:そうですね。災害時は状況によって、トイレがすぐに使えないこともあります。そのような非常時には、一時的な選択肢としておむつを活用する方が安心できる場合もあります。おむつに対する意識が変われば、非常時に備えた選択肢の幅も広がると思います。
「おむつ防災」というのを1回やってみようという話も出ています。おむつ体験を、防災訓練に入れてみようという話なんですが、いざおむつを穿いてみても、みんながいる場で漏らしたらどうなるか、ニオイとかも含めて、なかなかできないんですね。でも、そういう防災体験のような形で、一回でも経験したら、次は利用しやすくなるかもしれないですよね。
大盛況だった「未来のおむつコレクション」
――八木さんは、おむつの概念を変えるさまざまな取り組みをされていますね。6月には、「関西・大阪万博」で「未来のおむつコレクション(ファッションショー)」が開催され、話題になりました。
八木:日本福祉医療ファッション協会代表理事の平林景さんをはじめ、同じ志を持つメンバーとおむつを主役にしたイベントができたらと思い奔走し、実現したのですが、大変話題になりました。世界最大規模のおむつコレクションを軸に、トークショーも行い、世代や身体的特徴などさまざまなバックグラウンドの人たちが「もっと穿きたい」と思えるようなおむつの提案ができました。
イギリスの大手新聞社やNHKなど100媒体以上から取り上げられたんですよ。SNSなどを通して発信される内容も含めて、ネガティブなものはほとんどなくて、驚きました。
直近では、10月8日~10日に開催された国際福祉機器展(H.C.R)でも、「おむつミュージアム」(「O-MU-TSU MUSEUM at H.C.R.」)として、広いスペースで展示を行い、大勢の方が来場されました。
――多くのおむつメーカーの協賛もありましたね。
八木:はい。お陰様で、たくさんのご協力をいただき、メーカーさんにとってもポジティブなイベントだったのではないかと思います。おむつに対するイメージが変わるきっかけになったと思います。
――誰にとっても身近のテーマとして、おむつを使用することをポジティブに捉える人が増えたと思います。
八木:ただ、こうやって理想として掲げることはいろいろありますが、現実的には、商業ベースにのせて、永続的にできるようにするためには、まだまだ超えなければいけない壁がたくさんあるんです。
若いインフルエンサーにもおむつ活用を発信してほしい
――おむつは、その使われ方にまだまだ可能性があるのだとお話を伺って思いました。おむつ利用は特別なことではないという社会になるためにはどうしたらいいでしょうか?
八木:おむつを日常的に使用される方は高齢者が多いため、現在のコマーシャルやマーケティングの多くは高齢者向けに展開されています。海外に目を向けると、若い人がおむつのモデルをして、若い人に向けた訴求がされている場合があります。日本も若いタレントさんがおむつを穿いたコマーシャルを作るとか、例えば妊娠中、産後にも尿漏れに悩む人は多いので、若いインフルエンサーが、おむつを活用している発信をしてくれたりすると世の中の見る目も変化するのではないかと思っています。
――タレントのテリー伊藤さんは、紙おむつの積極的な利用を発信されていますね。
八木:はい。そうですね。亡くなられたアナウンサーの小倉智昭さんも紙パッドの利用についてお話しされていましたよね。そして、男性は、トイレにサニタリーボックスがないから捨てる場所に困っているという問題提起をしていましたね。
社会全体で取り組まなければいけない課題は、まだまだあると思いますが、発信を続けることは大切だと思っています。
*
八木さんのお話を通して、社会通念が変わり、おむつのイメージがもっとポジティブになる日はもうそこまで来ていることを実感した。「下着を選ぶように、状況に合わせておむつを選ぶ」ことができたら人生は豊かになるに違いない。
取材・文/介護ポストセブン編集部