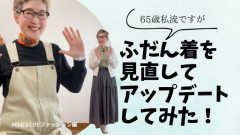73才インフルエンサーきょうかのばあばさん、孫のプロデュースで高齢者のデジタルライフの楽しさを発信
SNSを駆使して注目を集めるシニア世代のインフルエンサーにインタビューする企画。70才を過ぎてから始めたインスタグラムやTikTokでさまざまな挑戦をしているきょうかのばあばさん。総フォロワー数は3万人を超えるシニアインフルエンサー・きょうかのばあばさんとは、どんな人なのか。その素顔に迫ります【Vol.1/全2回】
きょうかのばあばさん・73才/プロフィール
1952年三重県生まれ 1975年に同志社大学工学部電子工学科を卒業し、新卒でプログラマーとしてキャリアをスタート。塾の先生や数学の教員などを経て、夫の赴任でドイツに4年間在住。60才で教員を退職後、自宅で茶道教室を開く。67才のとき、孫のきょうかさんのすすめでTikTokやInstagram(以下インスタ)をスタート。現在、SNS 総フォロワー数は3万人を超える。TikTok Instagram きょうかのばあば公式ホームページ
SNSをはじめたきっかけ
――きょうかのばあばさん(以下、ばあばさん)がSNSを始められたきっかけはなんだったのでしょうか。
孫のきょうかが仕掛け人なんです。彼女は私のプロデューサー兼マネージャー、兼カメラマンです。どんな投稿をするかはきょうかが決めています。
6年前、当時大学3年生だったきょうかから『世の中、若い子のインスやTikTokはたくさんあるけど、ばあばみたいなシニア世代がやったらバズるよ!』と誘われていまして。当時はバズるなんて言葉も知りませんでした(笑い)。3年間断り続けていたのですが、「きょうかのためなら」と、67才のときやってみることにしました。
SNSを始める以前、きょうかさんが大学生だった当時から、ばあばはモバイルパスモやPayPayなども活用し、スマホを使いこなしていたという
――最初はどんな動画を投稿されたんですか?
インスタグラムにばあばが外貨をチェンジ(両替)するところを載せたら、いきなり100万回再生されたんです。その頃はまだシニア世代のインスタグラマーは珍しかったので、何をしてもバズっていたという感じでしたね。
スマホがあれば新幹線も飛行機のチケットだって取れますし、地図も見られるから旅行も1人で行けますからね。73才のおばあちゃんがなんでもやっているんだから、シニア世代の人たちに何でもできるんだと思ってもらえたらいいですよね。
――スマホを使いこなしていますが、どのように覚えていったのでしょうか。
SNSを始めるにあたり、きょうかからお古のiPhoneをもらったんですね。そもそもデジタルには抵抗がなかったんですよ。ばあばは、もともとリケジョだったのです。
同志社大学で電子工学を学んでいました。当時、電子工学を学ぶ女性はかなり珍しかったですね。50人のクラスに女性ひとり、紅一点でした。
大学では電子工学科を選びましたが、本当はお医者さんになりたかったんです。というのもね、子供の頃からアルベルト・シュヴァイツァーやキュリー夫人に憧れていたんです。
お医者さんになって世界中の人を助けたいという思いがございまして、医学部を受けたんですが、落ちてしまいました。それで次はプログラマーになろうと思って、工学科を受けたら受かったのです。数学が得意で国語が苦手だったので、自然と理系に進んだんです。
73才でデジタル機器を駆使「元祖、リケジョ」
――プログラマーを目指すとはまた当時として珍しかったのでは。
そうですね。私が学生の頃は、テープに穴を開けて『0』『1』などの情報を読み込ませていた時代でした。大学卒業後は大阪にあるプログラム専門の会社に就職し、晴れてプログラマーになりました。プログラマーがプログラムを組んで、キーパンチャーという人たちがコンピューターにデータを打っていましたね。プログラムといってもまだ原始的な時代、女性プログラマーも少なかったですよ。
プログラマーになって間もなく、挫折を味わいました。仕事が本当に大変でね…。大量のデータを処理して納期に間に合わせるために徹夜もありましたから、なかなか過酷な環境で。就職して1年目のときに子供を授かったこともあり、2年半で辞めてしまったんです。
――就職されたときにはすでに結婚されていたんですね。
はい。大学の同級生と結婚していました。夫は同じクラスで席もいつも隣でした。私が授業でわからないことを丁寧に教えてくれる人でした。何かと助けてくれていて、いつの間にか交際に発展。大学卒業と同時に結婚をしました。夫は大学卒業後、半導体の会社に勤めました。
プログラマーが過酷すぎて退職した後、しばらくして息子が生まれたので、子育てをしながら塾をやることにしました。子供たちを集めて勉強を教えていたんですよ。
塾の仕事は子供たちの学校が終わってから始まるから、どうしても夜の時間対になってしまうでしょう。だんだん子育てと塾の仕事の両立が厳しくなってきたので、昼間働く仕事にしようと思って。思い切って中学校の数学教師になることにしました。大学のときに中学と高校の教員免許を取っていたおかげですね。
38才ぐらいまで数学教師として働いていたんですが、夫が仕事でドイツに赴任することになりまして、ドイツのデュッセルドルフで4年半暮らしました。
ドイツ生活で日本の文化「茶道」に開眼
――ドイツではどんな生活をされていたんですか?
学生の頃にお茶を習っていて師範の資格を持っていましたので、ドイツの教会などでドイツ人相手にお茶を教えていました。現地には日本人の男性のお茶の先生がいたので、その先生のもとで一緒に教えていましたね。
ドイツに行った当時は言葉の壁があると思っていたんですが、お茶を通して、「この人たちとは言葉ではなく、文化が違うんだ」と気づいたんです。
ドイツにはドイツの素晴らしい文化があるように、私たち日本人にも茶道という素晴らしい文化がある。それを海外の人に伝えることで、日本の素晴らしさをわかってもらえたらいい。日本の文化を知ることで真の国際人になれるんじゃないかと感じたのです。それからは、どんどんお茶の世界にのめり込んでいきました。
ドイツから帰国してからはまた数学教師として復帰し、60才まで学校の先生を続けていました。60才のときに夫に先立たれ、それを機に自宅の1階を改築してお茶室を作って茶道教室を始めました。
――旦那さんはご病気だったのですか?
肺がんでした。健康診断では何の問題もなかったので青天の霹靂でした。あるとき変な咳をしているなぁと思っていたのですが、健康診断では異常なしで帰ってくる。それでも咳が続いていたので無理やり病院に連れて行きました。レントゲンを撮ってみたら肺の様子がおかしいということで、詳しく調べてみたら、肺がんだったんです。
当時夫は、会社の社長という責任のある立場でもありましたし、常に仕事第一の人でしたから、入退院を繰り返しながら闘病中も仕事を続けていました。
私が『仕事なんてどうでもいいじゃない』と言うと、『本気でそんなことを言っているのか!』ときつく言われたこともありましたね。
病気が進行してからも『今度の6月に株主総会があるから、それだけはどうしても出席する』と。株主総会を終え、会社の人たちから花束をもらって帰ってきて、2か月後に亡くなりました。
『もっと早く病院に連れて行っていれば違ったのではないか』と、いまでも悔いは残っています。
夫を早くに失って一人暮らしを続けていますが、いまはお茶という日本の文化を通じてたくさんの人たちと繋がっていますし、スマホやSNSという新たな文化によって、出会いや発見もたくさんあります。
ばあばの暮らしは温故知新ともいるでしょうか。古いものも新しいものも知るって大事なことですよね。
取材・文/廉屋友美乃