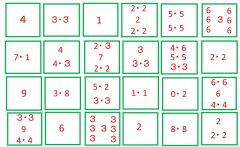【連載エッセイ】介護という旅の途中に「第5回 臨終」
初めて直面する「親の介護」を写真家でハーバリストの飯田裕子さんに写真とともにリアルタイムで綴っていだだく連載エッセイ。
容態が思わしくない父の在宅での医療態勢が整った矢先、母から父が苦しがっていると緊急電話が入り…
* * *
入浴サービスを受ける当日、母からの緊急連絡が入るとは、まさか思いもしなかった。
が、私が勝浦に到着すると、血の気が引いた顔色の父の呼吸は、今まで知る限りで最も切羽詰まっていた。
「ハアハア…、点滴を入れて…くれ…」
K病院の看護師さんもこちらに向かっているはずだったが、その到着前に予定されていた入浴サービスのチームが来てしまった。
本来なら「今日は中止にしてほしい」と事前連絡をすべきだったのだが、私も母もそれどころではなかったのだ。
「病院の人が到着するまでの間、私が付き添います」
入浴サービスチームの専任看護師さんが助け船を出してくれた。
冷やしタオルを額に載せたり、手を握ったり、背中をさすったり、辛さを軽減できるのは今や薬よりも何よりも、人の手の力だった。
肉体の痛みはどうあがいても他の人が替わってあげることはできないが、心を添わせ、言葉よりもスキンシップで伝える。
命が果てる時と始まる時…どこか似ていて
その様子を私はどこかで見たような記憶があった。
ふと私の脳裏に、取材で立ち会ったことのある“出産シーン”が蘇ってきた。陣痛に苦しむ妊婦のそばでひたすら祈るように腰をさすっていたご主人や看護師さん…
「間質性肺炎でしたね…。肺疾患の方は苦しさが…」と入浴サービスチームの看護師さん。眠るように逝く、という表現があるが、父の場合はそうは行かなかった。だからこそ、命が果てる時と命が始まる瞬間が私の中で交錯したのだろう。
「始まりと終わりの中間にあるのが今の生。だとしたら、やはり懸命に生きなくてはならないよ」父は苦しい呼吸の中でこんなメッセージを伝えてくれたように思う。
やがてK病院からO医師とN看護師が到着。
「入院ではなく、このままお家でよろしいですね」
父は、目をO医師と合わせてはっきりと頷き、意思確認された。
渇望していた点滴も「血管が脆いので1時間しか入れらません…」と、N看護師より伝えられ、父は頷いてそっと目を閉じた。
そして、2人はK病院へ検査のため戻っていった。
父の呼吸の速さや苦しさはあまり収まらず、家族として為す術もなかった。少しでも気分的に和らぐことはできないかと、タオルを電子レンジで温めた蒸しタオルで首元を温め、南太平洋のフィジーで作られたタモレ(フィジーのホーリーバジル)の蒸留水を顔の周りにスプレーした。
ベッドの周りの爽やかな香りに、父の表情も和らいだ。
私が撮影によく通っていた南太平洋の島々に、父は一度も行ったことがない。楽園と称されるような、豊かで明るい島の暮らしや、さえずる鳥の鳴き声で目覚める朝も知らないままだったが、肉体を離れた意識が楽園に行ってゆっくりビールでも飲んでいてほしい。
タモレのスプレーには、そんな思いを込めた。
モルヒネが導入された
O医師とN看護師が検査結果持参で再び戻ってきた。データの数値から、内臓の機能がもうボロボロであったことを私は理解した。そして、医師は静かに「苦しさを緩和するお薬を投入します。よろしいですね?」と話す。それはモルヒネの導入のことだった。
言葉にならない言葉で父はO医師に同意表現をした。死への覚悟のようなものが、父の中で決まったように思えた瞬間だった。
骨と皮だけになった太ももに皮下注射針を固定。分量と効果時間が制御される仕組みの機械が針に繋がっていて、容体が苦しそうに思えたら追加ボタンを家族が押す。すると自動でモルヒネが増量投与され、1日の規定量に達したらそれ以上入らない仕組みになっている、と説明を受けた。
酸素器具も最大のものに取り替えられた。にわかに家中に緊張のムードが走った。
父も覚悟を決めた以上、看取るこちらも覚悟を決めなくてはならない。
その数日前、母と私は延命に関するドキュメンタリーのテレビ番組を見ていた。救急で運ばれたが故に患者は正しい死の時に逝けず、管に繋がれた状態で延命されている現実が問題提起されていた。いくら生前に本人が「自然死を希望」と家族に伝えていたとしても、救急で運ばれた患者には病院は最大の手当てをする。すなわち、ありとあらゆる手法で命を救うのが救急の使命なのだ。そして、その管無しでは生きながらえない状態の患者を前に、家族は決断を迫られていた。その管を抜くことはすなわちち、死を意味する。
そんな選択を迫られた時、どこまでが自然死なのかとの判断は難しく、かけがえのない家族との別れ方としてはあまりに残酷な決断だと思った。管を外すことを同意したら、きっと後々に気持ちは塞ぎ、自分を責めることになリかねないだろう。
母と私は「モルヒネでパパは苦しさからは解放されてる。だから自然の成り行きを信じていようね」そう言って頷きあった。
それから私は自分の布団を父のベッドに近いリビングに運び、24時間態勢を整えた。
数日この状態が続くとして、まず自分たちが食べるものは大丈夫だろうか?
我ながら可笑しいが、それは大自然でのキャンプやラリーなどのサバイバル体験を彷彿とさせ「食べなきゃ保たない!」と逆に食欲すら沸いたのだ。
愛犬のナナは神経質そうな目をキョロキョロさせていたが、私以上に状況をわかっているという顔をしていた。
誕生日に贈ったブランデーを口に垂らし
父は動作で口を指し「み・ず」と要求した。
乾きの感覚はあるようだが、体はもう水すら拒否しているので、すぐに吐いてしまう。
ベテランのN看護師は臨終の現場に幾度となく立ち会ってこられた人だ。「もう何かを飲める段階ではないので、どうぞお好きな味を口元に感じさせてあげてください」と小声で言った。
以前、ホスピス医師の内藤いづみ先生の講演に友人が誘ってくれた時に聞いた話を思い出し、父の誕生日に贈ったレミー・マルタンを薄めて数滴垂らしたら父の喉が美味しいそうにゴクリと鳴った。
お酒の匂いに釣られて意識が回復した患者さん。臨終から生還し数日延命して宴会を開いたという話は、その講演のハイライトだった。
家族全員で父のベッドを囲む
普段英国に暮らしている弟も仕事で偶然来日していたので、仕事が終わると即座に勝浦へ駆けつけてきた。
そんなタイミングもありえない奇跡だった。
家族全員揃って父のベッドを囲む。父は飲めず、食べられず、点滴もなく、息をしながら、目だけでの会話が時々…そんな状態が続いた。
看護師さんが1日数回訪問し、様子を見てくれた。飲まず食わずでもウンチは出る。私も看護師さんの見よう見まねオムツを替えた。
「かわいい赤ちゃんのオムツも替えたことないあなたが..」と涙ぐむ母。人生、そんなこともある。
3日目の夜が明け、父の顔を見ると目が窪(くぼ)み、まぶたを開ける力もなかった。
か細い呼吸を感じ、私は「パパ、ナナの散歩から戻るまで頑張ってて!」と声をかけた。
戻って間もなく、母と弟を起こして皆で父の手をとった。
そして間もなく父は、息絶えた。
*
濃密だった3日と3夜が終わった。
残された私たちの胸には、もちろん悲しさがあったものの、それより苦しみから解放された父に「お疲れさま」の声をかけ、無事に一つの命を見送れた安堵感に満たされていた。
ゆっくりと病院に電話を入れた。医師と看護師が到着し、死亡時刻は9時50分と報告書に記入された。
その朝、寒さは少し緩み、ゴルフ場ではグリーンの旗が緩やかな潮風にはためいていた。
「パパ、ようやく辛い肉体を離れてゴルフしてるのかな?」
(つづく)
写真・文/飯田裕子(いいだ・ゆうこ)
写真家・ハーバリスト。1960年東京生まれ、船橋育ち。現在は南房総を拠点に複数の地で暮らす。雑誌の取材などで、全国、世界各地を撮影して巡る。写真展「楽園創生」(京都ロンドクレアント)、「Bula Fiji」(フジフイルムフォトサロン)などを開催。近年は撮影と並行し、ハーバリストとしても活動中。Gardenstudio.jp(https://www.facebook.com/gardenstudiojp/?pnref=lhc)代表。老老介護生活を送る両親のバックアップも始まった。
【バックナンバーを読む】