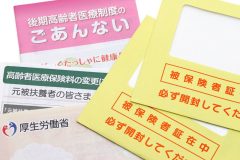「80代の父の在宅介護にかかるお金が心配…」覚えておきたい「高額介護サービス費」の仕組みや利用方法について実例相談をもとにFPが解説
80代の父親と同居する50代の娘さんから将来の在宅介護にかかるお金が心配だという相談を受けたファイナンシャルプランナーで行政書士の河村修一さん。そこでアドバイスしたのが「高額介護サービス費」の制度。実例相談を交え、「高額介護サービス費」の仕組みについて解説いただいた。
相談事例「父親の今後の介護費用が心配です」
80代の父親と同居をしているSさんの相談事例を紹介します。
ひとり娘のSさんは、父親に介護が必要になった場合、在宅での介護を考えていますが、今後の介護費用などが心配になったとのことで、ご相談を受けました。
父親の収入は年金収入のみで約300万円あり、介護保険の自己負担割合は2割負担。仮に父親に介護が必要となり、要介護3で支給限度基準額まで利用すると毎月の自己負担額が約5万円強かかります。さらに、要介護5になると、毎月約7万円強になります。
「高額介護(介護予防)サービス費」(以下「高額介護サービス費」)をご存じなかったSさんは、毎月の支払いを心配されていました。
「高額介護サービス費」の制度により、自己負担額には上限額があるので、Sさんの父親の場合、毎月の上限額は44,400円(下の表を参照)となります。
上限額を超えた分は申請することで「高額介護サービス費」として払い戻されます。Sさんは、高額介護サービス費のことを知ってホッとされていました。
介護施設のサービス費も適用される
また、介護施設で受けたサービスの場合も高額介護サービス費は適用されます。
特別養護老人ホームに入所したAさん(住民税非課税単身世帯:収入は、公的年金収入のみで約60万円、介護保険1割負担)の場合、「高額介護サービス費」の設定区分は第2段階の「個人」となり、上限は毎月15,000円です。利用額は34,137円でしたが、上限額の差額が返金されました。
Aさんには、「高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書」が送付され、19,137円が高額介護サービス費として戻ってきました。
「高額介護サービス費」とは?
公的な介護保険サービスの利用料は、介護度が進むことで負担が大きくなります。相談事例で紹介しましたが、そこで活用したいのが「高額介護サービス費」です。
「高額介護サービス費」は、介護保険サービスの1か月の利用額が負担上限額を超えた場合、払い戻しされる制度のこと。申請することで払い過ぎた分が支給されます。
制度の概要や支給額の要件など細かい注意ポイントについて、以下で解説します。
介護度別、介護保険サービスの負担額
「高額介護サービス費」の制度を利用するには、まず、介護保険サービスの仕組みについて理解しておく必要があります。
居宅サービスを受ける場合、介護保険サービスの利用額は、月の上限額が決まっており、要介護度によって異なります。これを区分支給限度基準額(以下、「支給限度基準額」)といい、要介護度が高いほど支給限度基準額は高くなります。
また、自己負担額は、1割~3割(第1号被保険者)ですが、支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。
なお、介護保険のサービス利用料や支給限度基準額は、全国一律で定められ、「単位」で表されます。基本は1単位10円で計算されますが、地域によって多少の差があります。
区分支給限度基準額
また、支給限度基準額に含まれないサービスには、次のものがあります※1。
・居宅療養管理指導
・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
・福祉用具購入費・住宅改修費
※参考/厚生労働省「区分支給限度基準額について」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000049257.pdf
介護保険サービスの自己負担割合は1~3割
介護保険サービスを利用するときの自己負担は、原則1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割負担、2018年8月からはさらに3割負担も設けられました。
介護保険サービスの自己負担(1~3割の要件)
●1割負担:下記以外の人
●2割負担:本人の合計所得が160万円以上220万円未満の住民税課税者
・同一世帯に65歳以上の人(本人を含む)が1人の場合(単身世帯)
「年金収入(公的年金所得控除前)+それ以外の所得金額」の合計が280万円以上
・同一世帯に65歳以上の人(本人を含む)が2人以上いる場合(夫婦世帯)
「年金収入(公的年金所得控除前)+それ以外の所得金額」の合計が346万円以上
●3割負担:本人の合計所得金額が220万円以上の住民税課税者
・同一世帯に65歳以上の人(本人を含む)が1人の場合(単身世帯)
「年金収入(公的年金所得控除前)+それ以外の所得金額」の合計が340万円以上
・同一世帯に65歳以上の人(本人を含む)が2人以上いる場合(夫婦世帯)
「年金収入(公的年金所得控除前)+それ以外の所得金額」の合計が463万円以上
※市区町村民税非課税、生活保護受給者は1割負担
自己負担が原則1割といっても、夫婦ともに介護保険サービスを利用すれば、費用負担は重くなります。負担を軽減するために、さらに毎月の自己負担額には上限が設けられています。上限額を超えた分は、申請することによって「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻されます。
上限額は、利用者本人または同一世帯の人の所得によって決まります※2。ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、施設での食費・居住費、支給限度基準額を超えた自己負担額は、高額介護(介護予防)サービス費の限度額の対象外となります。
「高額介護サービス費」の設定区分
※2厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索 介護保険の解説 サービスにかかる利用料」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
申請方法は?
該当者には、市区町村から「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」が送られてきます。初回のみ申請書などを送付することで、以後は自動的に払い戻しを受けることができます。
高額介護サービス費【まとめ】
・介護保険サービスを利用するとき、自己負担額は原則1割
(ただし、一定以上の所得がある場合は2割負担または3割負担)
・1か月の自己負担額には上限が設けられていて、上限を超えた分は申請することによって高額介護サービス費として払い戻される。
・福祉用具購入費や住宅改修費、支給限度基準額を超えた全額自己負担額分などは、高額介護サービス費の限度額の対象外。
高額介護サービス費について詳しく知りたい方は、お住まいの自治体や地域包括支援センター等に問い合わせてみましょう。
※記事中では、相談実例をもとに一部設定を変更しています。
執筆
河村修一さん/ファイナンシャルプランナー・行政書士
CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、認知症サポーター。兵庫県立神戸商科大学卒業後、複数の保険会社に勤務。親の遠距離介護の経験をいかし、2011年に介護者専門の事務所を設立。2018年東京・杉並区に「カワムラ行政書士事務所」を開業し、介護から相続手続きまでワンストップで対応。多くのメディアや講演会などで活躍する。https://www.kawamura-fp.com/