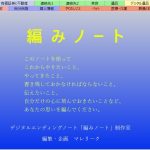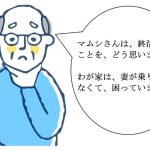スマホやPCに遺された「デジタル遺品」相談件数が増加 相続や処分方法を弁護士が解説
デジタル遺品とは、故人が遺したスマホやパソコンなどデジタル機器に保存したデータ等のことだ。プライベートな情報や貴重なデータが入っていることもあり、取扱いに困るケースもあり、専門業者への相談件数も増えているという。デジタル遺品はどう処分すればいいのか、相続の対象になるのか?デジタル遺品について詳しい終活弁護士の伊勢田篤史さんに話を伺った。
デジタル遺品とは?
「デジタル遺品とは、おもにパソコンやスマホなどのデジタル機器に保存されたデータ等やインターネットサービスのアカウントなどを指します」
亡くなった親のデジタル遺品を家族が処分する、自分自身が終活の一環として処分しておくこともあるだろう。実際にどのような手順になるのか、伊勢田さんに解説いただいた。
「デジタル機器に保存されたデータは、2種類に分けて考えます。
1つ目は、ハードディスクなどに残してある『オフラインのデジタル遺品』、2つ目は、インターネット上に保管したものやインターネットサービスのアカウントなどの『オンラインのデジタル遺品』として分類できます」(伊勢田さん、以下同)。各デジタル遺品の具体例は、以下のとおり。
【1】オフラインのデジタル遺品例
・パソコンやスマホに保存された、文書や写真のデータ
・インターネットサイトの閲覧履歴
・DL(ダウンロード)済みのアプリなど。
【2】オンラインのデジタル遺品例
・SNSのアカウント
・ネット証券のアカウント
・Amazon等その他アカウントなど。
デジタル遺品をそのまま捨てたり、放置したりしては危険だと伊勢田さんは警鐘を鳴らす。
「デジタルデータには、故人のプライベートに関する写真や動画、仕事関係の重要なデータ、知人・友人の住所録、取引のある金融機関関係の情報など大切なものが含まれています。
SDカードなども含め、データが入ったままハードを捨てたり譲渡したりすると、そのデータが流出したり悪用される危険性があるので、適切な対応や処理をすることが重要です」
デジタル遺品を適切に処分するには?
【1】オフラインのデジタル遺品の処分方法
「パソコンやスマホは小型家電リサイクル法により、住んでいる市区町村が指定する専門業者に回収してもらう方法があります。
また、民間のパソコンサービスの会社でも出張や引き取りなどをやっていますし、家電量販店に下取りに出す、中古パソコンショップに売りに出す方法などもあります。
スマホの場合は、キャリアショップに持ち込んで処分してもらうこともできます。
どの方法も有料の場合が多いので、条件や信頼度などよく考えて選びましょう。
パソコンもスマホも処分時には、初期化(工場出荷時の状態)に戻すことが基本となりますが、初期化してもデータ流出(情報漏洩)のリスクをゼロにすることはできません。完璧をきすためには、データが保存されているHDD(ハードディスク)などを物理的に破壊して処分することをおすすめします。
ご自身で処分するには、ネットなどでも処理方法が載っていますが、不慣れな方やより安全に完璧に処分したい方はデータ消去・破棄まで信用できる専門業者に依頼するのがおすすめです。
なお、ハードディスク等の物理的破壊については、目の前で破壊してくれるような業者がより望ましいでしょう」
【2】オンラインのデジタル遺品の処分方法
オンラインのデジタル遺品は、ホームページやSNSのアカウントなどさまざまなものがある。適切な処分方法は以下の通りだ。
・ホームページ
「故人が事業活動などをしていてホームページやブログなどが残ってしまうことで支障が生じるようであれば、削除を検討すべきでしょう。
しかし、国内の取引所以外で保管されている場合、IDやパスワード等がわからないと引継ぐことが難しい可能性がありますので、注意が必要です」
・SNS(フェイスブック、インスタなど)
「SNSにおいては、故人のアカウントとしてそのまま残すのか、削除するのか、どちらかを選択することになります。なお、故人のSNSは、そのまま残されている(放置されている)ケースが多いのが現状です」
・暗号資産
「仮想通貨などの暗号資産については、まずは取引所を特定し、相続手続の連絡をする手順をとります。しかし、国内の取引所以外で保管されている場合、IDやパスワード等がわからないと引継ぐことが難しい可能性がありますので、注意が必要です。
以上のようにデジタル遺品は、パスワードなどがわからなければ、そのままオンライン上で残されてしまうため、親が元気なうちにデジタル品の処分について話し合っておくといいのかもしれない。
デジタル遺品は相続の対象になる?
デジタル遺品は残された家族などの相続人が相続できるものなのだろうか?
【1】オフラインのデジタル遺品
「デジタル機器に保存された『データ』は、データ自体に所有権が成立しないため、相続することはできません。
しかし、オフラインのデジタル遺品が保存されている『デジタル機器』自体には所有権が成立します。つまり、デジタル機器に残されていた、故人の有していたデータを相続したい場合は、各データが保存されているデジタル機器を相続する必要があります。
【2】オンラインのデジタル遺品
「インターネットサービスのアカウントについては、LINEなどのように利用規約で『相続できない』と明記されているものもあり、相続できるものとできないものがありますので、利用規約等を確認してみてください」
デジタル遺品のトラブルが増えている
「デジタル遺品サポートサービス」をしている日本PCサービスによると、サポート開始当初の2017年8月の相談が272件だったが、2022年6月では318件にまで増加しているという。
相談内容は、2位の「パソコンを継承した後のトラブル」21件に比べ、1位の「パソコンのパスワードの解除」が233件と突出している(日本PCサービス調べ・2021年9月~2022年6月末)。
実際、伊勢田さんもパスワード関連のトラブルをよく聞くという。
「お葬式の際、葬儀に使用する遺影の写真や連絡先をスマホやパソコンから取り出せず、トラブルとなるケースもあります。遺影に古い写真を使わなくてはならず、親族から『もっといい写真なかったのか』と、嫌みを言われたというケースもあります」
また、友人や知人の連絡先などもスマホから取り出せず、葬儀に呼べないというケースもよくあるという。
「解決策としては、パソコンやスマホのログインパスワードを家族で共有しておくこと。できれば、ご自身がエンディングノートなどに写真のデータなどの保管場所や連絡先を書き残しておくのがいいでしょう。これをデジタル終活と呼んでいます」
トラブルを避けるため生前に「デジタル終活」のすすめ
生前からしておくべきデジタル終活とはどんなものがあるのだろうか。
「まずは、ご自分のパソコンやスマホのログインパスワードを残しておくことが大切です。これだけやっておけば、8~9割の問題は解決します。
生前は家族に知られたくないという場合は、エンディングノートなどの紙に残しておき、いざというときに家族に見てもらえるように保管しておくといいでしょう」
デジタル終活でメモしておくべきこと
・パソコンやスマホのログインパスワード
・引き継ぎが必要なインターネットサービスのIDやパスワード
・サブスク契約などをしているインターネットサービスのサービス名
・取引しているネット証券会社の名前(取引内容は不要)など。
「2015年ごろからデジタル遺品という言葉が広まり始めましたが、2022年の現在でもまだまだ認知度は低いようです。終活というと、なかなか気が進まない人も多いようですが、親が元気なうちに、また、ご自分が亡くなった後に遺されたご家族が困らないように、少しずつでもいいので準備しておくといいですね」
***
先日、記者も壊れたノートPCとデスクトップを自治体が提携する業者に引き取ってもらった。後日、消去作業実施日や消去方式などが記載された「データ消去証明書」が届き、安心した経験がある。
残された家族に負担をかけないように、現在活用中のパソコンをはじめ、家で眠っている古いパソコンやスマホも一度見直してみてはいかがだろうか。
教えてくれた人
終活弁護士、公認会計士・伊勢田篤史さん
日本デジタル終活協会代表理事、となりの法律事務所パートナー。「相続で苦しめられる人を0に」という理念を掲げ、終活弁護士として、相続問題の紛争予防対策に力を入れている。近著には古田雄介さんとの両著「デジタル遺品の探しかた・しまいかた・残しかた+隠しかた」(日本加除出版)がある。
http://tonarino.jp/
https://shuukatsubengoshi.net/
取材・文/本上夕貴