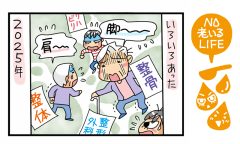【連載エッセイ】介護という旅の途中に「第7回 1人暮らしになった母のこと」
老老介護を続けてきた両親のサポートしている写真家でハーバリストの飯田裕子さん。長く闘病生活を送ってきた父が旅立ち、母を支える日々となった。
親の介護をリアルタイムで綴る連載エッセイ。
* * *
元号が新しくかわりひと月が経った。
父は90歳まで生きたい、と話していたが、新しい元号に立ち会うことは叶わなかった。
父が他界して、早、半年が過ぎた。夏の気配を感じるこの頃、父が暮らした勝浦の庭では草も伸びてきた。今は母が1人暮らすこの家に行く度に、私は草刈り機やチエーンソウで雑草や枝を払う作業をしている。
緑の綺麗な芝生と花壇のある庭であることを当たり前と思っていたが、今や芝生が厚かましく伸び、雑草の茂みには蛇まで見える。やぶ蛇とはこのことか。
思えばこれまで、芝生に雑草が気になったことがなかったのは、父が小まめに手入れしていたからだったのだ。こうなってみてようやく気づく。
父はいったいどれだけのエネルギーを庭に注いできたのだろう。かつて暮らしていた船橋の庭も今頃は花々が満開だった。父は意外とロマンチストだったのかもしれない。
気力が続かなくなった母
この頃は母と買い物に出かけると、花や野菜の苗を買ってくる。母も、庭に出ている時間は気持ちいいらしい。剪定鋏を持ち、仏前に供える花を日々摘んでいる。
母が1人になって半年。彼女の心の中には「本当に1人になったのだ…」という感慨深い思いがひたひたと潮が満ちるように迫っている。決してそう口には出さないけれど、私にはそんな気持ちが伝わってくる。
父が旅だった直後は「私はミシン仕事で布の整理をしなくちゃならないから、やる事がいっぱいあるの。暇なんてないわ!」と、いつも母は豪語していた。
しかし、近頃はお茶ばかり飲み、耳も急に遠くなったようだ。テレビもほぼつけず、さらにミシンにも向かわない日も増えてきた。気力が続かないらしい。
そして、昔の話をよくするようになった。彼女の思い出はバラ色に輝いている。人生、終わりよければ全て良し。そんなものかもしれない。今の日々に特別な不満がなければ、過去に何があっても全ては丸く収まる。母はある意味精神力が強い人だと感心している。
とはいえやはり街から離れた別荘地での1人暮らしは、車が無いと何処へも行けず、夜も物音がすると怖がる。のんびりしているように見えても、かなり緊張していたのかもしれない。
そんな事情が重なったせいか、最近、急に物忘れだけでなく、冷蔵庫や食事の管理ができなくなってきた。お風呂の回数も激減し、認知症と思われる症状が見えてきた。
母の要介護申請をした結果…
こんな折、私は久しぶりの海外取材で、フィジーへ10日間旅に出ることが決まっていたので、母の様子に不安を覚えた。その時の為に、母が介護サービスを受けられるようにしたほうがいいと私は感じ、早速準備を始めたのだった。
実は、父亡きあとすぐは母を勝浦の家に1人では難しいと思い、私のマンションの部屋に母用のベッドを用意し、一緒に暮らしてみたことがある。
母と暮らすことを友人、知人に話すと、皆口を揃えて「それは大変ですね。飯田さんが大変じゃないですか?」と言った。しかし、私はまだ父を見送ったばかりという事もあり、母との同居を疑いもなく「大丈夫」だと信じていたのだった。しかし、2か月ほど経ってくると、部屋の様子が変わってきた。
私は仕事どころではなくなった。心ここにあらずというか、母の事が気になる。そして、その感情にはトゲも含まれるようになり、部屋に広げられた布が目に入ると嫌悪感すら覚えるようになったのだった。そんな私の気持ちは態度にも現れていたのだろう。きっと母を傷つけていた。
結局、母は勝浦で1人暮らしをしてみる、と決めたのだった。そして、今まで父を介護する側だった母は、今度はヘルパーさんに介護される立場になる。
要介護申請をするにあたり、ケアマネージャーさんは父の最期の時についてくださっていたMさんにお願いした。それは、これまでの経緯を知り、何度も家に足を運んでくれれていたので、母の事もよくわかてってくださっていると感じていたからだった。
介護の認定をとるためには、医師の診断も必要になる。母は今まで医者には、ほぼかかったことが無かったので、父の往診に来ていただいていた近所のクリニックのK先生を頼りにした。
「どう?元気?」と先生が尋ねると、「はい、私は元気ですよ。でも寂しいですね…」
先生を前に、普段あまり口にしないことを母は正直に言った。その言葉に、私の胸が痛んだ。
その後、血液検査と認知度のテストがされた。
血液検査では、母はなんと貧血との診断で、鉄分が足りないと指摘された。1人でいると好物のパンだけで済ませたり、と偏食になっているようだ。時折、私が料理を作るとパクパクなんでも食べてくれていたので、気にしていなかったのだが。
クリニックで待っている間、いつも往診に来てくださっていた看護師さんとの会話も弾み、母の機嫌は良かった。普段は「人と会うよりも1人で針仕事やってるのが好き」という母だが、やはり、人と会うと会話やコミュニケーションを楽しんでいるようだった。
診察結果は市役所の福祉課へ報告され、支援度や介護度が決まるとのこと。
市役所の職員さん面会もすでに済み、私がフィジーへ出かける直前に、認定が下りた。
「要介護2」
それは父の最期の介護度と同じ度合いだったので、私は少し動揺した。
父は体が病に冒され、日常の暮らしを行うことができなくなったが、頭はほぼクリアだった。対して母は、べつだん病もなく、歩行に杖もいらない元気な状態だ。だが、認知症が進んでいるということだ。
もはや、母は幼子のようなものかもしれないとも思った。
でも、私自身にも人生があり、仕事がある。プロの手を最大限に借りながら日々の暮らしに折り合いをつけていくしなないだろう。ケアマネさんと相談し、ヘルパーさんが週2回、掃除と買い物、調理に入っていただけることになり、私は、ホッとしてフィジーへ旅立った。
フィジーの人々の幸福度が高い理由
フィジーへの訪問は約10年ぶりだった。どんなに変わっているのだろう?と期待と不安が胸に去来した。
リゾートなどの近代施設はそれなりに進化していたが、村を訪ねると、以前とさほど変わったこともなく、首長による歓待のカヴァという飲み物を振る舞う儀式で迎えてもらった。子供達ははしゃぎ、清潔に洗われた家族の洗濯物が長いロープにずらりと太陽を浴びている。こういったアナログの世界があることに安堵する。
フィジーの村では、家に垣根もなく、もちろん鍵もなく、広場を介して人々は自由に家々を行き来している。子供は共同体で育てるのが当たり前で、いわば村は大きな家族だ。個人所有という概念も薄いフィジーの村では、家族の境界線も曖昧だ。
日本ほど長寿でないにせよ、高齢者が孤独になることは無い。幼い頃から顔見知りの中で適度な距離でお互いを見守っているように見える。
近年の調査で「現在、自分は幸せを自分で感じている」と答えた人が世界で最も多い国の一つに選出された。
人間は物質的な豊かさがいくらあっても、隣人との関わりなくしては幸せは感じることはできないという生き物。フィジーで幸福度が高い理由にも頷ける。大きな体で強面そうな大人の男も「ブラ!」と笑顔で挨拶をする。
自然や人との緩やかな信頼関係がフィジーにはあるのだ。
さて、そんな旅から戻ると、懸念していた通り、母は、認知症の症状はさらに進んでいた。
冷蔵庫の中に、本来入れ必要のないものが入っていたり、お風呂にもあまりに入っていない様子だった。保険証を入れたバッグを置いた場所がわからなくなり、てんやわんやとなったりもした。
しかし、コースターやクッションなど布製品は夢中で創っていたようだ。縫い物の話をする時の目は輝いている。はて?と思うことはあれ、基本的な生活面では、さほど支障はない。この感じで少し様子を見ていくことにした。
(つづく)
写真・文/飯田裕子(いいだ・ゆうこ)
写真家・ハーバリスト。1960年東京生まれ、船橋育ち。現在は南房総を拠点に複数の地で暮らす。雑誌の取材などで、全国、世界各地を撮影して巡る。写真展「楽園創生」(京都ロンドクレアント)、「Bula Fiji」(フジフイルムフォトサロン)などを開催。近年は撮影と並行し、ハーバリストとしても活動中。Gardenstudio.jp(https://www.facebook.com/gardenstudiojp/?pnref=lhc)代表。