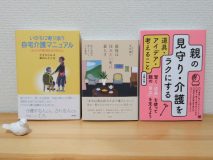仕事と脳梗塞の母親の介護「どちらもうまくいかず自分を責めた」経験者がピックアップした【介護と仕事の両立に役立つ本】3選
図書館司書の資格を持ち、オンライン書店を運営する小黒悠さんは、20代に母親の介護を経験。働きながら母のケアを続ける生活は、自分を責めてしまうことも多かったという。母のケア経験をふまえ「仕事と介護の両立」をテーマにした名著をピックアップ。働きながら介護をする人の支えになるヒントが――。
教えてくれた人/小黒悠さん
元図書館司書。20代から母のケアを経験し、ケアする人を「ケアする本屋」を目指し、オンライン書店「はるから書店」を運営。ライターとしても活動中。https://harukara-reading.stores.jp/
仕事と介護の両立、当時の私は…
こんにちは、ケアする本屋「はるから書店」の小黒です。この春から育児・介護休業法の改正があり、企業では介護離職防止のための雇用環境整備が義務付けられました。
私自身も20代から30代にかけて、仕事と介護の両立をしていた時期がありました。母が脳梗塞を発症して、私の生活は一変。当時のことを振り返りながら、介護に役立つ本をご紹介したいと思います。
***
朝起きると母の着替えや身支度を手伝い、洗濯、朝ごはん、食器洗い、大急ぎで自分のメイクや準備を済ませたら、洗濯物を干して駆け足で職場へ。徒歩3分の職場なのに、到着はいつもギリギリセーフでした。
昼休みはいったん母のもとに戻り、一緒に昼食を食べたり、午前中の困りごとを解消したりした後、再び職場へ。仕事が終わると、スーパーへ買い物、夕飯の仕度、入浴の手伝い、後片付け…。
私はマルチタスクな職業人なわけでも、スーパー家政婦のような家事の達人なわけでもなく、すべてのことが滞りなく進むはずはありません。必然的に寝不足や疲れが続いてしまいました。
それに介護というものは、こちらのスキルや要領の良さだけで乗り越えられるものでもないんですよね。家族とはいえ自分以外の人、言ってしまえば「他人」の生活に直接的に関わるということは、こちらの意思ではどうにもできないことばかり。
後遺症による疼痛を訴える母は、リハビリをして自分でできることを増やそうとしていましたが、母のペースに合わせなければならず、おのずとこちらは母の行動を見守り、待つ時間が増えます。
出勤前の忙しいときに限って意思疎通がうまくいかず口論になったり、夜の疲れている時間に頼まれごとをされ、いい加減な対応をしてしまったり。介護の大変さを味わうだけでなく、不本意ながら優しくできない自分にうんざりすることも多々ありました。
この生活をどうやって続けていけばいいのか。どうしたら、お互いに気持ちよく暮らしを続けていけるのか――。
『介護マーケティング研究所 by 介護ポストセブン』が実施した「介護と仕事の両立」についての実態調査※によると、悩みの1位に「時間に自由がきかない・足りない」、2位に「心身疲労」が挙がっています。
※「介護と仕事の両立」について調査を実施!両立できていないと考える人は35%、実際に離職した人は2割にのぼる実態が明らかに
私自身も、時間のやりくりと気持ちのやりくりは、欠かすことのできない要素だと感じています。
そこで今回は、こうした悩みの解決にヒントをくれるような本をご紹介したいと思います(私と母のエピソードの続きは後述します)。
介護と仕事の両立に欠かせない制度を解説
『仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書』木場猛、佐々木裕子(共著)、日経クロスウーマン(編)/日経BP
仕事と介護を両立するために使える制度や、要介護認定の手続きの流れ、介護施設選びのポイントなどが、要点を絞って解説されています。
著者のひとりは20年以上介護の現場で働いてきた介護福祉士。仕事を通じて出会ったご家族の暮らしを1週間のタイムスケジュールで表すなど、両立生活をリアルに想像できるように紹介をしています。
こちらの本によると、仕事をしながら介護を続ける上で、介護にかける時間は最大でも「平日2時間、休日5時間」までがよいそうです。このラインを超えると継続がつらくなる一つの目安としておくといいでしょう。サービスを利用したり、プロに頼ったり、環境を整えることが必要だと教えてくれます。
元祖ビジネスケアラーによる「人の助けを借りる」重要性
『受援力』 町 亞聖(著)/法研
元日本テレビのアナウンサーで、現在はフリーで活躍されている町亞聖さんは、18才の高校生の頃にお母さまがくも膜下出血で倒れ、介護が始まりました。
今でこそ「ヤングケアラー」という言葉が浸透していますが、町さんはまさに、若くして介護と学業、そして仕事を両立されてきた経験者です。前半は学生時代、後半は就職してからのエピソードに触れながら「困った時に誰かに助けを求める力」=「受援力」の大切さが綴られています。
町さんは就職のスタート時からビジネスケアラー。周囲には介護をしていることを伝え、フレックスな働き方を上手く利用しながら両立を続けたそうです。仕事に行くことは、暮らしにメリハリをつけるスイッチのONとOFFにもなったという一言に、私も共感します。
介護の悩みを職場で打ち明けるのは甘えではない
『がんばらない介護』橋中 今日子(著)/ダイヤモンド社
3人の家族を21年に渡って介護してきたという著者。あるとき職場の上司から「辞めてもらう」と言い渡され、そこで初めて、大変な状況は言わなくても分かってくれているだろうと思い込んでいたこと、相談することは甘えだと思っていたことに気付いたそうです。
「言ってくれないと僕たちもどう助けていいかわからない」「もっと周囲を信頼して相談して」という上司の言葉から、状況は変わっていきます。
介護をしているとつい、職場で周りが見えなくなってしまうことも。同僚とランチでコミュニケーションを取る、挨拶を大切にするなど、介護をしながら働く上での心掛けについて、実体験を交えて書かれています。
仕事と介護の生活で私の背中を押してくれた言葉
仕事と介護の両立生活中、私の励みになった言葉があります。それは一緒に働いていた年上の女性がかけてくれた一言でした。
「たとえ週1日になっても、ここで仕事を続けたほうがいいよ。履歴書に書いちゃえば、週5も週1も同じなんだから」
彼女がちょっぴりいたずらっぽく笑いながら話してくれた背景には、一度仕事を離れてしまうと同じ場所に戻ってくることの難しさ、厳しさが、彼女自身の実感としてあったのだと想像します。
23才から図書館で働いていた私ですが、介護が始まったのは就職後4年が経った頃。仕事の面白さを知り、勉強して資格を取り、ますます力を注いでいきたい、挑戦してみたいこともある。
それなのに、母の介護のためにシフトは遅番を免除してもらい、突然お休みする日もしょっちゅう。好きな仕事だからこそ余計に、できない自分へのジレンマと、周囲への肩身の狭さ、迷惑をかけていることへの申し訳なさを感じていました。
今のまま仕事も介護もずっと続けられるのか、漠然とした不安を抱えながら働いていたとき、先輩女性にかけられたその言葉に、私は背中を押されました。
職場で介護のことを伝えるときに大切なこと
その後の私は、用意されたデフォルトの働き方に合わせてひとりで悩むのではなく、どうすれば介護と両立ができるか、具体的に考えて上司に相談するようになりました。
以降、働く日数はそのまま、1日の勤務時間を日によって短くすることで、少しずつ自分に余裕を持つことができるようになりました。
通院の付き添いなどには介護休暇を使い、長くサポートが必要だった時期には介護休業を取ったこともありました。
正直に相談することで思いがけず折衷案が生まれたり、たとえ希望通りにならなくても、状況を知ってもらうことで心理的な負担が減ったり、良いことはたくさんありました。
相談する前は、いっそ退職して拘束時間の短いアルバイトでも探そうかと考えたこともあったのですが、既にそれまでの信頼関係ができている場所で、仕事を続けて来られたことは、精神的に良かったと思います。
今の時代、転職は珍しいことではありません。でも、もし介護を理由に転職や退職を考えるなら、まずはその前に相談してみて欲しいです。大切なのは、今ここでどんな働き方をしたいのかを考えて、それをきちんと伝えること。あなたの背中を、本がそっと押してくれると思っています。