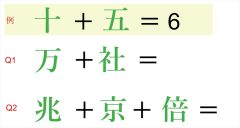私の認知症体験記|風見しんごら語る認知症の親への感謝の思い
あの芸能人・家族が語る――。今から知っておきたい老いの迎え方とは?人生100年時代に、誰もが無関係ではいられないその瞬間のために、私の素敵な認知症体験記。
* * *
城戸真亜子「介護を通じて、自分も成長できた」
タレントや画家としてマルチに活躍する城戸真亜子は’04年、末期がんの義父の入院を機に義母との同居を始めたとほぼ同時に、義母の認知症がわかった。
同じ話を繰り返して物忘れの激しい義母のため、城戸は「オートロックなので気をつけてください」「指輪は金庫に入れてあります」などのメモを家中に貼った。義母はひとりで徘徊して警察に保護されることもあったが、そのたびに城戸には発見があったという。
「認知症になると、精神が病んで本人ではなくなるというイメージがあったけど、それは誤解で、実は行動にはすべて理由があるんです。たとえばお茶の道具を忘れたという思いがフッと浮かべば、早く取りに行かなくちゃ、と家を飛び出すし、何か失敗して恥ずかしい時はとにかく隠す。いたずらで、後先を考えない子供のようで、義母にとても魅力的なかわいさを感じました」(城戸・以下同)
城戸にとって義母は、とことん「かわいくて、愉快な人」だった。
「ある時は夜中にいなくなって捜し回ったら、お風呂の浴槽の中で寝ていました。『どうされましたか』と声をかけたら、『あら? 向きが反対だったかしら?』って(笑い)。もともと専業主婦だったから、夕方になると台所が気になるようで、遠慮しながら覗いてきたことも。ふとした姿がすべてかわいかったんです。あとは、夫に対してかわいいと思う仕草と、お義母さんの仕草がそっくりだったりして、親子なんだなって、そういう発見もおもしろかったです」
13年間に及ぶ介護の末、義母は’17年に95才で亡くなった。義母と過ごした時間は宝物だと城戸は語る。
「介護を始めたのは私が40代半ばになり、いろんなことがうまくいかなくて自分の存在理由を見失っていた時でした。でも義母と向き合って同じ時間を過ごすことで、人が喜んでくれることが自分の喜びであることを改めて教えられました」
義母の小さな手を握った時、自分が幼い頃に手をつないでくれた母の愛情を思い出すこともあったという。
「介護を通して自分が成長できたことを心から感謝しています」
介護は与えるだけでなく、与えられるものでもある。
風見しんご「娘を亡くした時、認知症の親父のおかげで立ち直れた」
’00年4月、高齢者を家族だけでなく、社会で支えることを目的とした介護保険制度が始まった。
「父の認知症がわかったのは、ちょうど介護保険制度が始まった頃でした。まだ認知症が“ボケた”といわれる時代で病気についての情報も少なく、お先真っ暗でした」
今から17年前、65才だった父親が認知症になった当時の心境を、タレントの風見しんご(56才)はそう語った。底知れぬ怖さを感じたという。
「週末は東京から父の住む広島を訪問して、遠距離介護を始めました。“強かった親父のこんな姿を見たくない”という思いもあって、イライラが抑えきれない上、“最高の介護をしないといけない”というプレッシャーを勝手に感じて、自分を追い込んでいました」(風見・以下同)
不安、恐怖、苛立ち。家の中から笑顔が消えていったという。
「母はすでに他界していたのですが、ある時、親父が『母さんは?』と尋ねてきたんです。思わず、「母さんは死んだでしょ!」と返したら、涙を見せたことのない親父が泣き始めたんです。その時に、これは大変だと気がついた。親父は、お袋が亡くなったことを忘れるたび、涙を流してつらい思いをしなくてはならない。その時、ぼくは、この病気は父にとって、ものすごく怖くてつらいものだと理解しました」
笑顔の残っている介護を徹底した
その場しのぎでやり過ごすのではなく、認知症と向き合う覚悟を決めた風見が出した結論は、自分にできることの優先順位を決めることだった。
「“よい息子でありたい”というエゴがあり、すべてをこなそうとしていたけど、本気でやるからこそ優先順位が必要だとわかった。ある程度はプロに任せることにして、親父を施設に入れました」
父との接し方も変え、“笑顔の残っている介護”を徹底することに決めたという。
「親父が何を言っても否定せず、笑いに変えることを心がけました。たとえば、親父がぼくの妻を、行きつけのスナックのママと勘違いしたことがあって、妻が『もう社長さん、最近来てくれないから』とママを演じてくれたんです。親父もノリノリで、娘はお腹を抱えて笑っていました。施設の中で、そんなことをやっているのはうちの家族だけでしたね(笑い)」
世の中には介護より大変なことがある
家族に笑顔が戻った矢先、悲劇が襲う。’07年、当時10才の長女えみるちゃんが通学中に交通事故で亡くなった。
「それ以降、介護を大変だと思うことはなくなりました。世の中にはもっと大変なことがあると知り、認知症を大変なことだと思っていてごめんね親父、と思いました」
’13年に父が他界するまでの11年あまり、さまざまな経験を積んだ風見が振り返る。
「ぼくの場合、長女を亡くして生きる意味を見失った時、親父の介護があったから家の外に出ることができました。“こうしていられない、親父のところに次女を連れて行かなくちゃ!”って。家の中で悲嘆に暮れていたぼくと家族を無理やり外に引っ張り出したのが親父の病気だったんです」
介護はいくら大変でも永遠には続かない。天国と思うか地獄と思うかは自分次第だ。
「ぼくは、認知症になった親父に感謝しています」
風見はそう語った。
*
認知症の家族と向き合った経験者たちは、共通して、学ぶべきことは多いと言う。苦労の先に、必ずあるのは、認知症でなければ得られなかった素敵な人生だ。
※女性セブン2019年6月20日号
●私の認知症体験記|つちやかおり、岩佐まり…「認知症と幸せに過ごす」日々