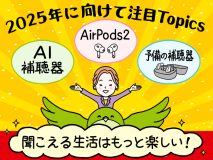知らないと損!《補聴器の助成金》あなたの街には制度がある?簡単に調べるコツを紹介【専門家が教える難聴対策Vol.27】
補聴器を必要とする高齢者を対象に、各自治体が実施している助成金制度をご存じだろうか。区長選の選挙の公約に上がるほど注目を集めているこの制度。「お得な制度であることはもちろん、その後の補聴器活用についてもメリットがあります」と、認定補聴器技能者の田中智子さん。お住まいの地域に制度があるのか、調べる方法や活用の仕方について教えてもらった。
教えてくれた人
認定補聴器技能者・田中智子さん
うぐいす補聴器代表。大手補聴器メーカー在籍中に経営学修士(MBA)を取得。訪問診療を行うクリニックの事務長を務めた後、主要メーカーの補聴器を試せる補聴器専門店・うぐいす補聴器を開業。講演会や執筆なども手がける。https://uguisu.co.jp/
全国に広がる補聴器の助成金制度「杉並区長選の公約にも」
2022年6月に杉並区長選に立候補した岸本聡子さんは、公約のひとつに「聴力が低下している高齢者を対象に補聴器購入費助成制度の導入」を掲げ、見事当選。公約通り当選から1年後、杉並区ではその助成制度が開始され、さらに2024年には助成金額の拡充が図られています。助成限度額は4万8300円(住民税非課税世帯)となっています。
※参考/区長公約(さとこビジョン)達成状況のご報告(令和6年6月末現在)
https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/533/mokuji_20240917-2.pdf
補聴器購入のための助成金制度は、全国の自治体に広がりを見せています。補聴器販売店協会の調査※によると、2023年時点では、全国の市区町村(1,747件)のうち、約14%にあたる237の自治体が実施しています(※補聴器販売店協会「全国自治体の補聴器助成金」)。今後、さらに増えていくことが予想されます。
助成される金額については各自治体で異なりますが、全国で一番高額の助成金を給付しているのは東京・港区で14万4900円となっています。前述の調査によると、2万円台が47自治体、2.5万円が24自治体、3万円が64自治体、5万円が50自治体となっています。
※一般社団法人日本補聴器販売店協会「全国の自治体における補聴器購入費助成制度の実施状況」(2023年12月1日)。
https://www.jhida.org/common/updatefiles/jyoseiseido.pdf
お住まいの地域に助成制度があるかを調べるコツ
Googleやヤフーなど検索サイトでは、「〇〇市 高齢者 補聴器 助成」と検索してみてください。
ポイントは、「高齢者」を入れることです。補聴器の助成制度として、「(軽度)中等度難聴児補聴器購入費補助」という制度もあります。これは、国の制度である身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、自治体が、補聴器の購入費用の一部を助成する制度です。
「検索して、出てきたので、市役所の高齢福祉課に行ったけど、そんな制度はないと言われた」などということもありますので、対象者が、「高齢者」なのか「18才未満の児童」なのかなど確認しましょう。
助成金の対象者かどうか確認を
各自治体の助成金の支給要件は、「住民税非課税世帯」が一般的で、購入前に申請が必要なケースが多いので、注意が必要です。
補聴器を購入する前に、まずはご自身が助成金の対象となるのかどうか、自治体に確認しておきましょう。
医師の診断が必要
補聴器購入の助成金を申請するには、医師の診断が必要になります。
補聴器を作るには、まず耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査や医師の診察を受ける必要があります。検査を実施し、医師が「補聴器が必要」という診断をもらって初めて、申請が可能となります。助成金の申請書には、医師の署名が必要になります(有料)。
自治体によっては、受診する耳鼻咽喉科の指定や補聴器相談医に限るなど、条件がある場合もあります。かかりつけの病院がある場合は、制度に対応しているかどうか確認しておきましょう。
なお、お住まいの自治体の医師会に所属している耳鼻咽喉科であれば、医療機関への受診時の負担額が減額されるなど、特例を設けている自治体もあります。
たとえば、東京・板橋区の場合、板橋区医師会加入の医療機関であれば1000円となっています。
補補聴器購入費助成金制度の流れ
補聴器購入に助成金を活用するための流れを確認しておきましょう。以下は一般的な流れなので、自治体によって異なるので、詳細は自治体窓口の説明に従ってください。
【1】 自治体に申請書をもらう
ご自身が住んでいる自治体の窓口に問い合わせし、ご自身が対象者(住民税が課税か非課税かで助成内容が異なることが多い)か確認してもらい、申請書をもらう。
【2】 耳鼻咽喉科を受診
耳鼻咽喉科で医師の診断を受け、補聴器が必要かどうか確認し、申請書に医師の署名をもらう。受診する耳鼻咽喉科については、補聴器相談医や自治体が指定する医師であることが求められる場合があるので、受診前に自治体窓口で確認しておく。
【3】 自治体窓口に申請書を申請
【4】 審査
自治体で審査が行われ、支給が決定する。支給が決定すれば郵送で自宅にお知らせが届く。(1~2か月かかることが多い)
【5】補聴器販売店で補聴器を購入
助成金を利用して補聴器を購入するには?
助成金利用の準備が整ったら、いよいよ補聴器を購入です。購入する店舗については、自治体によって異なりますが、前述の調査によると「認定補聴器技能者のいるお店からの購入」を条件としている自治体は28自治体となっています。
認定補聴器技能者とは、公益財団法人テクノエイド協会が、厳しい条件のもと、基準以上の知識や技能を持つことを認定して付与する資格です。4年間の講習期間を経て、試験に合格することで初めて資格が得られます。2025年7月現在、認定補聴器技能者は全国に5226名います。
資格取得後も、5年ごとに更新の審査があり、講習の受講や症例データの提出・医療機関との連携の実施など、さまざまなハードルがあります。補聴器を扱うプロとしての知識や技術力を有し、補聴器を購入する人にとっては頼りになる存在と言えます。
ちなみに、助成金額が日本一の東京都の港区では、認定補聴器技能者からの購入を義務付けています。
助成金を活用して補聴器を購入した人の満足度
東京・港区では令和4年度中に助成を受けて補聴器を購入した人に、アンケートをとって、その結果を公表しています。
※港区高齢者補聴器購入費助成事業アンケート集計結果
https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/122393/riyousyakekka.pdf
調査結果によると、「港区の事業で購入した補聴器の使用状況はいかがですか?」という設問には、「日常で常時装用している」が59.9%。「聞こえの改善に役に立っていますか?」という質問には「とても役立っている」が70.4 %となっています。
また、「補聴器の購入後、補聴器相談医や認定補聴器技能者に対し、使用方法や聞こえの再調整について相談をしたことがありますか?」という質問に対しては82.7%と、高い数字を示しています。
この結果からもわかるように、まずは適切な医療機関で受診し、次に認定補聴器技能者のいる販売店で相談して購入することで、その後の満足度も高いということがわかります。
助成金制度については、「お金がもらえてよかった!」「お得に購入できた」という金銭的なメリットはもちろんあります。それだけでなく、制度を活用した結果、専門家の指導を受け正しく補聴器を知り、納得して購入することになり、その後もしっかりと生活の中で使いこなせるようになる、これはとても良い循環といえます。

お得な助成金制度を活用し、快適な補聴器ライフの実現を目指しましょう
取材・文/立花加久 イラスト/奥川りな