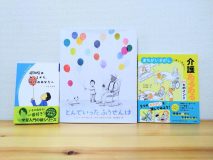介護の強い味方となる「地域包括支援センター」の役割は主に4つ 相談できることや活用法について解説
高齢者や高齢者支援を行う人のサポートをする「地域包括支援センター」。介護が始まったときも頼りになる存在となる地域包括支援センターについて、詳しく知っておこう。そこで、節約アドバイザー・ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに利用方法やどんな支援が受けられるのか、教えてもらった。
* * *
教えてくれた人
丸山晴美さん/節約アドバイザー。ファイナンシャルプランナー
22歳で節約に目覚め、1年間で200万円を貯めた経験がメディアに取り上げられ、その後コンビニの店長などを経て、2001年に節約アドバイザーとして独立。ファイナンシャルプランナー(AFP)、消費生活アドバイザー、宅地建物主任士(登録)、認定心理士などの様々な資格を持ち、ライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなどをテレビやラジオ、雑誌、講演などで行っている。
地域包括支援センターは高齢者を総合的に支援する施設
地域包括支援センターは市町村が主体となって設置されている機関で、対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者や、その支援のための活動に関わっている人が利用可能です。
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、介護、医療、保健、福祉などさまざまな面から総合的に支援を行うための窓口となる施設です。2024年4月時点で全国に5451か所、ブランチ・サブセンターを含めると7362か所あります(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001401860.pdf)。
無料で相談できる地域包括支援センター
地域包括支援センターは、全国どの地域でも無料で利用できます。そのため、保健師や社会福祉士、ケアマネジャーなど、専門家の力を借りたい場合に、費用の心配なく相談することができます。
また、介護疲れなどから家族が要介護者に対して暴言を吐いたり暴力をふるったりしてしまうなど、虐待などの問題やトラブルが発生することもあります。こうした問題について、被害を受けている要介護者だけでなく、虐待に気が付いた別の家族が地域包括支援センターに相談することもできます。
地域包括支援センターの4つの業務
地域包括支援センターの主な業務は、4つに分類されます。
総合相談
相談内容を踏まえて、必要なサービスや制度、専門機関を紹介します。福祉や医療のサービスだけでなく、日常生活に関することなども含めて、幅広い相談に応じます。例えば、「親の介護が必要になったが、まず何をすればいいのか」といった介護の入り口としての相談から、「親の介護について本人と話したいが、全然聞いてくれなくて困っている」、「一人暮らしの親が心配」といったような、高齢者の親に関する不安や悩みの相談まで受け付けています。
介護予防ケアマネジメント
要介護・要支援認定で「要支援」と認定された人などを対象に、要介護状態にならないようケアプランの作成などを行います。要介護の人に対するケアプランとは異なり、要介護状態になることを防いだり、遅らせたりするのが目的のため、主に直接的な介護のサービスではなく、運動機能の維持・向上のための専門家による自宅での運動プログラム指導のサービスや地域の健康教室の紹介、社会参加のための地域の交流イベントの紹介などを行っています。
権利擁護
判断能力が低下して金銭の管理や契約などを自分で行うことに不安がある人に対し、成年後見制度の活用の案内などを行います。成年後見制度は、判断能力が低下した人を法的に保護・支援するための制度で、高齢者が騙されて不要な契約をしてしまった際などに、あらかじめ選任された後見人が契約の取り消しなどを行うためのものです。後見人を選任するためには家庭裁判所への申し立てなどが必要ですが、地域包括支援センターではこの申し立てなどを支援しています。
このほか、虐待防止のための相談や、詐欺などの消費者被害に関連する相談なども受け付けており、必要に応じて警察や行政などとも連携します。
包括的・継続的なケアマネジメント
高齢者の方への直接的な支援だけでなく、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を続けられるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援といった様々なサービスを包括的に結びつけ、切れ目なく継続的に提供するための後方支援のような役割も担っています。
具体的には、複数のサービスや関係機関と適切に連携・調整し、要介護状態になっても必要なケアが切れ目なく提供されるよう、長期的な視点で高齢者やその家族をサポートする継続的な支援が行われます。
そしてケアマネジャーに対する指導や助言、個別相談会などを通じて、ケアマネジャーを支援することで、地域全体での高齢者支援を充実させるための体制整備を行っています。このほか、地域ケア会議の開催や、地域の福祉や医療に関わる人たちのネットワークづくりなどにも対応し、地域ネットワークの構築をしています。
少しでも不安が出てきたら地域包括支援センターに相談を
地域包括支援センターは介護が始まっていなくても利用できます。「日常の生活や行動に少し不安が出てきた」といったレベルで相談してもいいですし、子が親の相談をしに行っても問題ありません。ただし、その場合は、親本人が住んでいるエリアを担当する地域包括支援センターに相談する必要があります。
地域包括支援センターは自治体窓口で紹介してもらえる
地域包括支援センターは、自治体の福祉課や介護保険課で紹介してもらうことができます。1つの市内でも複数の地域包括支援センターがある場合もあり、担当区域はそれぞれ異なるため、まず自治体の窓口で相談するのがいいでしょう。
直接地域包括支援センターに行く場合は担当区域を確認してから
担当区域の地域包括支援センターを自分で探して直接相談に行く場合は、インターネットで検索をしてお住まいの自治体HPから探すか、厚生労働省の「介護サービス情報 公表システム」(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)にアクセス調べることもできます。「介護サービス情報 公表システム」を使う場合は、まず自分の居住する都道府県を選び、「地域包括支援センターを検索する」のボタンから検索しましょう。
無料でさまざまなことが相談できる地域包括支援センターは介護の心強い味方のため、うまく活用するようにしましょう。